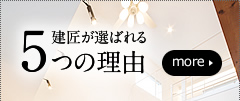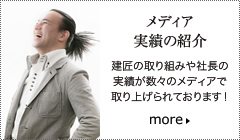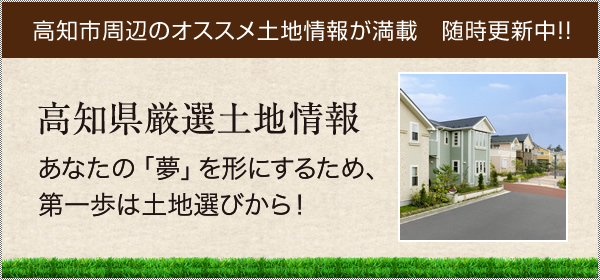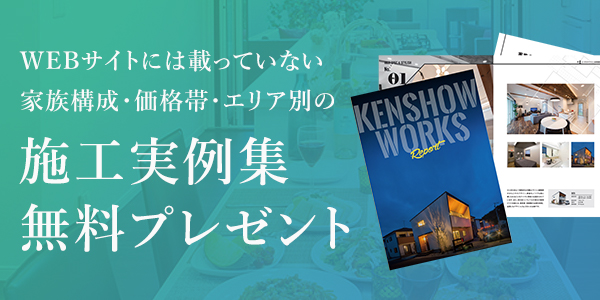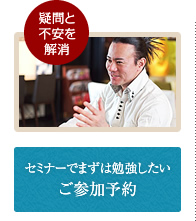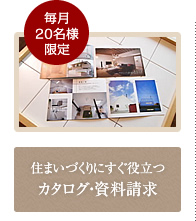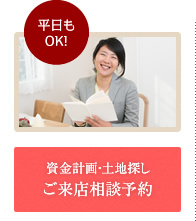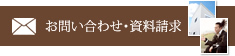夢のマイホームを建てるには、家を建てるための土地が必要です。
土地はどこも同じではなく、人によっては分譲住宅を選ぶ人もいるので周辺環境によっても住みやすさが大きく変わってきます。
建物も大事ですが、土地選びを疎かにしてしまうと住み始めてからさまざまなトラブルに悩まされる可能性が考えられます。
今回は、分譲住宅のデメリットや分譲住宅が向いている人などを紹介していきます。
分譲住宅とは?
そもそも分譲住宅とは、購入予定の土地に建物が既に建っている住宅のことです。
土地を「分譲地」と呼び、建物のことを「分譲住宅」と呼びます。
注文住宅は建物とは別に土地を別で購入しなければなりません。
一方で分譲住宅は、既に土地の上に住宅が建っているので土地と建物をセットで購入することが可能。
分譲住宅の多くが似たような外観をしており、町並みを形成するように並んでいることがほとんどです。
どのため周辺の住宅はどれもコンセプトを持って作られているため、似たような間取りになっています。
分譲住宅とよく間違われる「建売住宅」との違いは、土地が分譲地かどうかという部分のみ。
複数の土地をまとめて売りに出しているのが「分譲住宅」で、一戸だけ個別で売りに出しているのが「建売住宅」です。
分譲住宅のデメリット
ここからは分譲住宅のデメリットについて紹介していきます。
分譲住宅のデメリットは、大きく分けて以下3つが挙げられます。
1.間取りや仕様が決まっている
2.同じような外観の家が多い
3.郊外にあることが多い
それぞれチェックしていきましょう。
間取りや仕様が決まっている
分譲住宅のデメリットの1つに、自分で好きなように間取りや外観が選べないというもの。
注文住宅なら一から間取りや設備などが自由に決められます。しかし、分譲住宅の場合だと自分たちが思い描く理想がそのまま形となることはありません。
建物の工事が行われている段階で購入したとしても、基本的に間取りや外観のデザインなどの変更は行えません。
複数の土地をまとめて売りに出しているのが分譲住宅ですが、販売戸数が多いため自分たちにあった一軒が見つかる可能性も高くなります。
ですが、ほとんどコンセプトが同じ物件なので、細かい希望が実現しにくい傾向にあります。
自分たちの理想を100%叶えたいという人は、分譲住宅ではなく注文住宅を検討するのが良いでしょう。
同じような外観の家が多い
先ほども紹介した通り、分譲住宅は周辺の建物が似たような外観をしているため間取りが類似していることがほとんど。
間取りや外観にこだわりたいという人には不向きだといえます。
そのため分譲住宅で100%の理想を実現することは難しいとされています。
さらに分譲住宅は同エリアに複数の住宅が一斉に建設されるため、似たような外観の建物には同じ建材が使われているのです。
そのため、間取りはもちろん外観に自分たちの個性を出したいという人にもデメリットになります。
ですが決まった間取りや外観ではあるものの、家具の配置や敷地内なら柵を立てたり玄関ドアまでの道に砂利などを敷いたりすることで個性を出すことは可能な場合があります。
郊外にあることが多い
分譲住宅の大きなデメリットとして、郊外に立地するケースが非常に多いです。
分譲住宅が郊外に多い理由としては、都市部のマンションより手頃感を出したいというのが挙げられます。
その分注文住宅などに比べて販売価格が大幅に安くなっている傾向にあります。
駅から遠いなどの理由で郊外に集中しているものの、建物自体はしっかりと作られているので普段から車移動を中心とした生活を送っている人ならさほどデメリットを感じないでしょう。
分譲住宅はデメリットばかりではない
上記では3つのデメリットについて紹介してきましたが、デメリットばかりが分譲住宅ではありません。
・購入前に住宅を確認できる
・注文住宅よりも費用が安い
上記2つについて紹介していきます。
購入前に住宅を確認できる
購入前からその土地には建物が建っているので、賃貸物件の内見のように事前に住宅を確認できるのは大きなメリットだといえます。
購入前にどのような物件なのか確認することができるので、住む前から具体的にどのような暮らしができるのかイメージしやすいです。
この部屋は夫婦の寝室として家具は何をおいて、将来的にこっちの部屋は子供部屋として使いたいなどと明確に決められるのが分譲住宅ならではの特権でもあります。
日当たりの良さや収納スペースなど、生活環境を左右する要素の確認が行えます。
内見の際に感じたデメリットなども確認できるので、事前に対処法が見つかりやすいのも大きな特徴だといえます。
注文住宅よりも費用が安い
郊外に立地していることが多い分譲住宅ですが、先ほども紹介した通りなんといっても注文住宅より安く購入できるのは嬉しいポイント。
住宅購入は多くの人にとって大きな買い物ではありますが、できることなら費用を押さえたいものです。
分譲住宅なら一から建物を設計する必要がないので、本来注文住宅でかかる費用を大幅に削減することが可能です。
一から家を建てるだけの購入資金は用意できないけれど、分譲住宅なら購入に必要な費用と返済していく住宅ローンのことだけを把握しておけば今後の予定が立てやすいです。
分譲住宅が向いている人
将来的にマイホームを検討しているが、可能ならリーズナブルに購入したいという人は分譲住宅がおすすめです。
賃貸物件からすぐにマイホームを持って引っ越したいという人にも最適で、とにかく土地エリアを優先したいなら分譲住宅が最適です。
実際に自分の目で建物はもちろん街並みなどの確認ができるので、100%細かく決められなくて良いという方は分譲住宅を検討してみてください。
まとめ
分譲住宅のデメリットや特徴などについて紹介してきました。
マイホーム選びはたくさんの要素の中から最終的にいくつか絞って購入していくもの。
間取りや立地、さらには入居時期などこだわりたいポイントは人それぞれです。
コストを抑えて、マイホームの購入を検討している人は分譲住宅を視野に入れて考えてみてはいかがでしょうか。
家づくりの流れやおおよその期間を詳しく解説!工程ごとのポイントも丸わかり
家づくりの理由はさまざまですが、家を建てよう思ってから引き渡しまでにどのくらい期間を要するのか分からない人は結構います。
しっかりと計画を立てることで、今の暮らしからスムーズに新しい家への移行が可能です。
今回は、家づくりの流れやおおよその期間を詳しく紹介していきます。
家づくりの流れ
家づくりの流れとしては、以下の通り。
1.情報収集や予算の決定
2.施工会社の選定
3.土地探しや購入
4.住宅ローンの事前審査
5.間取りや設備を検討
6.建築請負契約を結ぶ
7.住宅ローンの本審査
8.着工から引渡し
それぞれチェックしていきましょう。
情報収集や予算の決定
まずは理想の住まいを手に入れるために、さまざまな情報収集を行いつつ予算を決定していきます。
あなたが理想とする快適な暮らしを、大まかで良いのでイメージするところから始めましょう。
・生活の拠点となる住みたいエリアへのこだわり
・間取り
・デザインなど
自分にとってこれだけは絶対に譲れないというポイントを明確にしてください。
イメージが全然湧かないという人は、住宅展示場に行って全体のイメージ像を膨らませるのもおすすめ。
現時点で時間に余裕がないという人は、空き時間にでもネットなどで良いなと思った物件を参考にするのも良いでしょう。
ある程度暮らしをイメージしたら、理想を実現できる予算を決めます。
物件の購入金額はいくらが良いのか知りたい人は、各不動産サイトなどでおおよその購入予算をシミュレーションするのもおすすめ。
提示された金額の住宅がかならずしも購入できるとは限らないので、予算を決める段階の目安として活用してみましょう。
施工会社の選定
大まかなイメージと予算が一通り決まったら、施工会社の選定へと移ります。
施工会社は住宅設計から建築までをしてくれるので、できるだけ早めに住宅を完成させたいという人は施工会社選び早めの方がメリットは大きいです。
住む家のイメージを決めつつ施工会社も選びたいという人は、実際に住宅展示場などに足を運んで相談している人も少なくありません。
ここで注意して欲しいのは、流れに任せて会社を決めてはいけないということ。
相談の段階で親身にサポートしてくれる会社がおすすめです。
担当営業との相性は家づくりをする上でとても重要で、理想を提示した際にメリットだけでなくデメリットもしっかりと話してくれるのが理想。
対応力の高さはもちろん、こちらの要望などをすぐに反映してくれる会社を選びましょう。
土地探しや購入
家を建てる場所となる土地探しはとても重要。
住宅に力を入れたいのは分かりますが、住みやすい家を手に入れるためにはベースをしっかりする必要があります。
土地選びにおいて妥協点が多い、いざ住み始めた時に不便だと感じる部分が目立ちます。
長くその土地に住む予定なので、あとから暮らしに支障が出ないためにもじっくりと条件を照らし合わせながら探していきましょう。
住む家のイメージよりも、先に土地を決める人も多い傾向にあります。
土地探しで注目してほしいポイントは、大きく分けて6つ。
1.土地周辺の環境確認
2.自宅と駅までのアクセス
3.通勤や通学の利便性
4.土地の形や広さ
5.商業施設の確認
6.災害に向けた安全度の高さ
土地周辺の環境確認の際は、車通りの多さや街灯の多さやなどを中心に確認しましょう。
昼間に確認するのも良いですが、夜に行って実際に街の雰囲気を感じることで見えてくるものもあります。
住宅ローンの事前審査
住宅ローンには「事前審査」と「本審査」の2つが存在しています。
会社を決める段階で、同時に金融機関で住宅ローンの審査を進めて行くと後々スムーズに物事が運べます。
事前審査は本審査よりも簡易的で、申込者本人の年収や物件購入に充てられる自己資金などの割合で審査が行われるのです。
審査内容は以下の通り。
・年齢
・健康状態
・担保評価
・借入時年齢
・年収
・勤続年数
・連帯保証
審査項目は利用する金融機関によって異なるものの、書類に記入してから平均して3日~1週間で結果が出ます。
間取りや設備を検討
理想とする暮らしをイメージするだけでしたが、本格的に希望を実現していくには会社との細かな打ち合せを元に間取りや設備などを決定していきます。
各部屋の空間設計はもちろんのこと、それぞれ取り付けたい設備などを施工会社と相談していくことで理想とするライフスタイルの実現に繋がるのです。
ここでは間取りや内装を決めて行くだけではなく、建物の外壁などにもこだわりを追求していくので非常に細かく設定していくことを覚えておきましょう。
人それぞれ予算が決まっているのでどれだけ調整が効くかはその人次第ですが、1つずつ全体のバランスを見て決めて行くことをおすすめします。
建築請負契約を結ぶ
間取りなどを決めて行く段階でこれから自分たちが住む家が建つという実感が湧いてきますが、住宅の全体像が固まってくるのは、おおよそこの段階。
・工事請負契約書
・見積書
・設計図書
契約はそんなに時間はかからないので、上記3つの契約書類を受け取って契約内容に納得したら建築請負契約を結びます。
住宅ローンの本審査
住宅ローンの事前審査が通ったら、今度は本審査へと移行します
ここで注意してほしいのは、本審査は事前審査よりも厳しくチェックが入るので事前審査が通ったとしても本審査で落ちてしまう場合があります。
審査の基準となる内容は以下の通り。
・借入申込金額と頭金
・返済負担率
・返済完了時の年齢
・契約者の所得(年収)
・健康状態など
最後の健康状態が意外と盲点になりやすく、住宅ローンの審査では団体信用生命保険の加入に影響する項目となります。
もちろん金融機関によって審査項目は異なりますが、多くが審査対象の項目に設定しているところがほとんど。
健康状態の良し悪しでも判断されるので、注意してください。
着工から引渡し
見積り内容に加えて、住宅完成までのスケジュールを確認したら工事を開始します。
工事をしながら随時内装材や設備機器の確認をしながら進めて行くので、完成までの工程も楽しめます。
予算にある程度余裕があるなら、この際に内装材の追加などを検討することも可能。
完成した建物は、外観はもちろん実際に内覧して問題がないかのチェックが入ります。
確認後は登記をして、晴れて物件譲渡となります。
家づくりにかかるおおよその期間
家づくりの期間は注文内容によって多少異なるものの、最大でも約15ヶ月は目安として考慮しておくと完成までの予定が立てやすくなります。
・情報収集や予算の決定…1ヶ月
・施工会社の選定…1ヶ月
・土地探しや購入…3ヶ月
・住宅ローンの事前審査…1週間
・間取りや設備を検討…1ヶ月
・建築請負契約を結ぶ…1ヶ月
・住宅ローンの本審査…1ヶ月
・着工から引渡し…5ヶ月
施工会社にいつまでに完成して引き渡しまで行えるかを相談するのも、家づくりの準備をする上でとても大切。
まとめ
家づくりの流れやおおよその期間を紹介してきました。
スムーズな家づくりをしたいなら、家族でしっかりと認識をすり合わせておくことをおすすめします。
間取りや設備を決める段階で決めるのも良いですが、前もって流れや期間をイメージしておくとスムーズに家づくりを行うことが可能。
認識違いで完成までに時間がかかってしまうというケースも多いので、トラブル回避のためにも譲れないポイントなどはあらかじめ相談しておきましょう。
快適な空間を実現した家づくりを目指したいと誰もが考えるもの。
しかし、理想を求めすぎると生活し出した時に不便だと気付く場合もあります。
おしゃれな暮らしに憧れを持つのは良いことですが、せっかく建てた家に後悔が残るのは非常に残念。
今回は、家づくりで後悔しないために注意して欲しい7つのポイントを紹介していきます。
陥りやすい失敗例を挙げていますので、家づくりの参考にしてみてください。
家づくりで後悔したこと7選
一般的に、子供が生まれるタイミングや、小学校に上がる時を狙って家づくりをする人が多い傾向にあります。
もちろん理由は人それぞれですが、家づくりをする目的は共通してこだわりのあるマイホームを建てたいというもの。
人生において大きな買い物の1つとして家づくりが挙げられるので、できることなら後悔のない家を建てたいのは誰もが思うものです。
1.リビング
2.収納
3.配線
4.資金面
5.日当たり
6.土地選び
7.水回り
上記7つのポイントごとにそれぞれチェックしていきましょう。
リビング
家族の時間が最も多く取れる場所がこのリビングなので、多くの人がとにかく広く面積を取りがちです。
広ければ広いほど快適に過ごせると考えている人が多い傾向にあるのですが、設計次第では冷暖房の効きが悪い場合が考えられます。
例えば空間が広すぎて夏場のクーラーが効きにくいや、天井を吹き抜けにしたリビングだと暖房が上に行って床付近が全然暖まらないというデメリットが生じることもあります。
広すぎるリビングは空調面で不便だと感じることが多く、光熱費が高額になる場合も。
広々とした快適なリビングにしたいなら、移動が自由にできる引き戸などの仕切りを設置するのもありです。
天井を吹き抜けにしたリビングにしたいなら、床暖房の設置も最適です。
収納
奥行きのある収納スペースを多く作ってしまうと手前に余計なスペースを生む可能性があるので、収納はあればあるだけ便利という考えは逆にデメリットになる可能性が考えられます。
階段下に収納スペースを作るところもありますが、元々持っていたもしくは新しく買った棚や収納ケースのサイズが合わなかったというケースもあります。
いつか役に立つからと、とにかくたくさんの収納スペースを確保しておきたい気持ちはありますが、後々使いにくさからデッドスペースになりやすくなる可能性があるのです。
逆に元々物が少ないからという理由で収納スペースを最小限にしていると、物が増えた時に後悔したという人も多い傾向も。
「どこに何を収納したいか」というのを明確にしておくのが家づくりのコツです。
配線
家づくりにおいて配線問題は、多くの人が後悔しやすいポイントだといわれています。
賃貸物件に住んでいた頃は、便利な位置に当たり前のように配置されていたコンセント。
住んだ後の家具配置など、設計の段階でしっかりとイメージしておかなければ家電を使う場所に制限が出ます。
・テレビ
・Wi-Fiルーター
・エアコンなど
上記以外にも日常で家電は必ず使うものなので、コンセントなどの配線まわりは特に重要視したいポイント。
コンセントの数はもちろん、設置したい場所もある程度イメージしておくのが重要です。
コツは先に家具の配置場所を決めると、コンセントの位置と数が割り出せます。
資金面
住宅の購入資金はもちろん、土地代などにも気を配りたいところ。
理想をある程度実現するためには、可能な限り多くの資金が必要となります。
・住宅の購入資金
・土地代
・住み出してからの生活資金など
住宅や土地の購入資金を意識し過ぎてしまい、実際に住み出してから生活が苦しくなったという人もいます。
借入金が多過ぎてローン審査に落ちてしまったり、住宅ローンの返済計画が甘かったりなどの失敗例が挙げられます。
資金面はとにかく予算とのバランスが重要。
住宅や土地の購入プランを考えている間に予算を大きくオーバーしてしまうことも考えられるので、購入資金にはある程度余裕を持たせることをおすすめします。
住み始めてからの税金面も発生しますので、しっかりと把握しておきましょう。
日当たり
間取りを考えた時に無計画で窓の位置を決めてしまうと、陽が当たり過ぎて厚くなり過ぎたり、逆に寒くなり過ぎたりしてしまう場合があります。
よくあるのが、1階に洗濯機やバスルームがあるのに2階にサンルームを設けるというもの。
これがデメリットしかないわけではないのですが、洗濯物を2階まで持って行く労力を考えるとサンルームは1階がおすすめ。
ただし、2階にサンルームを設けると干して取り込んだ洗濯物をそのまま2階の寝室などに運べるというメリットもあります。
家づくりの設計段階で生活動線を考えながら決めるのがおすすめです。
土地選び
地域によっては、印象が昼と夜で大きく変わってしまうところも存在しています。
昼間に土地探しをすることが多いのですが、日中の街の雰囲気は良かったのに夜になると人通りや街灯が少ないと感じることがあります。
人通りや街灯が少ないと防犯面でも不安を感じる人もいるので、土地探しをする際は昼夜どちらの確認もしておきましょう。
また、子どもがいる世帯は平日と休日の交通量も確認しておくことをおすすめします。
水回り
キッチンやバスルーム、さらにはトイレなど水回りについてももっとこうしておけば良かったと後悔する人に多い傾向にあります。
・脱衣所と洗面所を分ければよかった
・脱衣所をもう少し広く作ればよかった
・水回りに防音素材をあまり使っていないため、寝室まで音が響くなど
どうしても位置的に排水管の移動が難しい場合もあります。
その場合は、防音素材を使って音や振動をなるべく別の部屋に響かせないという工夫が必要です。
家づくりで後悔しないためのコツ
ポイントによって家づくりで後悔しないためのコツはいくつか存在しています。
持ち込みたい要素によっては生活が不便になる可能性もあるので、設計段階でコーディネーターなどに相談しながら決めることをおすすめします。
どれだけ念入りに相談して決めたところで、実際に住み始めてから気付くこともあります。
家づくりの準備をする際は、理想と生活動線を比較して考えて行くようにしましょう。
まとめ
家づくりで後悔しないために注意しておきたい7つのポイントを紹介してきました。
今回紹介したのはあくまでの1つの例に過ぎません。
家づくりで気を付けてほしい部分はまだまだたくさんありますが、後悔しやすいポイントを知っているのと知らないとでは大きく差が生まれます。
本記事を参考に、ステキで快適な家づくりをしていきましょう。
すまい給付金と住宅ローン控除の併用は可能か?気になっている方も多いのではないでしょうか?
夢のマイホームを購入後、新しい家具や家電などで新居を自分好みに彩りたいもの。
ですがかけられるお金には限度があり、ある程度制限しなければならないという問題に直面してしまうことが多いかと思います。
そんな時に役に立つのが「すまい給付金」という制度。
今回は、すまい給付金について詳しく解説していきます。
すまい給付金と住宅ローン控除は併用できる?
結論からいうと、この2つの制度は併用が可能です。
後ほどすまい給付金と住宅ローン控除について詳しく触れていきますが、どちらも住宅購入者が抱える負担を少しでも軽くするための制度です。
消費税という法が生まれた1989年から現在の2021年まで、増税が行われて住宅購入者の負担も大きくなりました。
住宅を購入する人が少なくなったため、もっと気軽に購入できるようこの制度が生まれました。
負担軽減を目的にした制度ですので、併用目的で利用する人は多い傾向にあります。
すまい給付金と住宅ローン控除を併用するときの2つの注意点は?
2つの制度を併用して利用は可能ですが、いくつか注意点があります。
1.制度毎に申請方法や条件が異なる
2.用意する書類も異なる
それぞれ確認して行きましょう。
制度毎に申請方法や条件が異なる
併用できる制度ではありますが、それぞれ申請方法や条件が異なります。
まず「すまい給付金」の申請方法や条件は以下の通り。
・床面積が50m2以上であること
・年収775万円以下(家族構成によって異なります)
・住宅ローンを利用すること(50歳以上かつ年収650万円以下であれば利用しなくても可)
・第三者機関からの検査が行われた住宅であること
・専門窓口に直接申請、もしくは郵送
次に「住宅ローン控除」の申請方法や条件は以下の通り。
・購入物件に自分が住むこと
・10年以上のローン返済期間を設ける
・住宅取得の日から6ヶ月以内に購入物件に引っ越しをし、なおかつ各年の12月31日まで継続して住み続けること
・床面積が50平方メートル(15.13坪)以上で、なおかつ居住用面積が1/2以上であること
・合計所得金額が3,000万円以下であること
・住宅ローン控除を利用する場合は、必ず確定申告を行わなければならない
すまい給付金や住宅ローン控除に関する情報は、国土交通省の専用ホームページにてより詳しく紹介しています。
現時点で各制度を検討している人は1度チェックしておくことをおすすめします。
用意する書類も異なる
申請方法が異なるということは、用意しなければならない書類も異なるもの。
一般的には以下3点が必要になることがほとんどです。
・収入証明証
・住宅性能証明証
・住宅ローンの利用状況が分かる書類など
事前にそれぞれの書類がどこで入手できるかも把握しておくと、後々スムーズに物事が運びやすくなります。
住宅ローン控除とすまい給付金の給付金の違い
前提として、どちらも条件を満たしてさえいれば併用して利用できる給付金制度です。
違いを把握し、少しでも購入した物件にお金をかけられるようにと作られた制度なので上手に利用していきましょう。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅を10年以上のローンを組んで購入した人、もしくはリフォームをする人のどちらかに該当した人を対象としたのが、この住宅ローン控除という制度です。
条件は先ほど挙げた通りなのですが、リフォームに関しては工事費用が100万円以上することが前提になります。
1%相当額の住宅ローン残高を所得税から控除し、そこから控除しきれなかった差分(税金)は翌年の住民税から控除されるのです。
優先的に住民税や所得税から控除されるので、年収が多くなればなるほど還付金の受取額が多くなるというメリットを持っています。
すまい給付金とは
すまい給付金とは、住宅購入者の所得に応じて現金で給付される制度のこと。
住宅ローン控除では所得が多い人が比例して、還付金が多くなるというものでした。
すまい給付金の場合だと、所得が少ない人であればあるほど多く給付金が受け取れるというものです。
住宅ローン控除とすまい給付金の申し込み方法
住宅ローン控除の場合は初年度のみ確定申告を行わなければなりません。
・住民票(写し可)
・住宅ローンの残高証明書
・源泉徴収票
・登記事項証明書、または売買契約書
上記4点は新築物件になりますが、中古物件だと以下3点の中からいずれか1点必要になるので注意してください。
・既存住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
・耐震基準適合証明書
すまい給付金の場合は以下5点を用意してすまい給付金のホームページから申請書をダウンロード、もしくは窓口に行って申請してください。
・住民票(写し可)
・課税証明書(住民税)
・登記事項証明書(謄本でも可)
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書
・不動産売買契約書(工事請負契約書でも可)
まとめ
すまい給付金と住宅ローン控除の併用は可能かどうかを解説していきました。
2つとも申請手続きが必要なのでやや手間だと感じますが、建物にかけられるお金が増えるので申請を選択肢として入れておきたいですね。
さらに、併用可能な制度でもあるので、検討している人は条件などを確認の上上手に利用してくださいね。
住宅ローンにはさまざまな制度が存在しており、その中の1つに「つなぎ融資」というのが挙げられます。
住宅ローンを組む際に利用する制度なのですが、言葉は聞いたことあるけれどどういったものなのか分からないでいるという人はかなり多いもの。
今回は、つなぎ融資について詳しく解説していきます。
つなぎ融資とは?
そもそもつなぎ融資とは、新しく建てようとしている住宅が完成するまでの資金を一時的に融資するという制度です。
新規に住宅を購入したり建築をしたりする際に住宅ローンを組むわけですが、着工金や上棟金など完成までにかなりの資金が必要になります。
融資を受けるまでにいくつか制限はあるものの、住宅ローンの審査が通って金融機関から融資の内諾を得ていればつなぎ融資は可能です。
住宅ローンを組んでつなぎ融資を利用するには?
上記でも触れましたが、住宅を新しく建てるためには資金の準備が必要です。
住宅ローンの融資金は、売主から買主に完成した住宅が引き渡される時に買主の口座に振り込まれます。
後ほど詳しく解説していきますが、工事費用などといった注文住宅に必要な資金が準備できないという人は多いもの。
融資を受けるには、住宅ローンの審査が通って金融機関から融資の内諾を得ていて、なおかつ土地取得資金や建物建築資金に限られます。
つなぎ融資が必要になるのはいつ?
多くの人たちがつなぎ融資を利用しているものの、全ての条件下で融資が必要になるとは限りません。
基本的につなぎ融資を受ける人の多くが、注文住宅を検討している人が多い傾向にあります。
・土地代金
・着工金
・上棟金など
これらに利用されている方がほとんど。
ハウスメーカーや工務店にもよりますが、一般的に上記の支払いはそれぞれ3回に分けて支払うと定められていることが多い傾向にあります。
どれも住宅ローンが実行される前に支払うため、ある程度の資金が必要です。
つなぎ融資の仕組み
条件やケースはさまざまですが、今回は土地探しをして注文住宅を購入するまでの流れで紹介していきます。
まずは土地を探すため、ハウスメーカーや工務店に依頼をして注文住宅の契約を行います。
この時住宅ローンだと工事費用などの支払いに間に合わないことが多いため、契約段階でつなぎ融資を検討している人が多い利用するのです。
返済方法を提示されるので、以下2つのパターンから自分に合った返済方法を選択してください。
1.毎月利息のみを返済し、元金分は住宅ローン支払い時に返済
2.住宅ローンの支払い時に、利息と元金を一括で返済
つなぎ融資による借入れは、住宅ローンの融資金でどちらも住宅が引き渡された段階で清算します。
先ほども触れた通り、あくまでも土地探しから注文住宅を購入するまでの仕組みです。
ケースによってつなぎ融資の仕組みは異なるので、詳しくはハウスメーカーや工務店と相談してみてください。
つなぎ融資を利用する流れ
手順
内容
1.住宅ローン申込及び審査
・申し込み後、各金融機関の融資担当者へつなぎ融資を希望する旨を伝えてください。
・その際に希望者の年収や、建築予定の土地及び建物などについて住宅ローンの審査が行われます。
2.つなぎ融資の申込書提出
・審査通過後、各金融機関からつなぎ融資の申込書が郵送されますので、記入後速やかに返送しましょう。
※審査が通らなかった場合はこの限りではありません。
3.つなぎ融資の審査及び契約手続き
・審査承認となったら、融資実行日などの契約条件を各金融機関の融資担当者と打ち合わせに入ります。
・説明内容に納得したら、契約の手続きへ移行します。
4.つなぎ融資実行
・土地に対して融資をした金融機関が第一順位となる抵当権を設定します。
・つなぎ融資実行後は、建物が完成して住宅ローンが融資実行されるまで毎月利息のみ返済していきます。
5.つなぎ融資返済
・住宅完成後、住宅ローンの契約及び融資実行の手続きをします。
・完済段階で建物にも第一順位となる抵当権を設定します。
・つなぎ融資完済後は、決められた額の住宅ローンを返済していきます。
つなぎ融資を利用するまでの流れは、ざっと上記の通り。
第一順位の抵当権とは、債務者(融資を受ける人)が債務不履行の場合に目的物から優先弁済を受けられる権利のことです。
第一順位ですから、その名の通り融資をする金融機関が1番目の抵当権を握っています。
金融機関側は融資をする上で優先的に抵当権が付けられるので、住宅関連で融資を受ける人は必ず条件として提示されます。
つなぎ融資の利用する際のポイント
つなぎ融資利用のポイントは、大きく分けて以下の7つ。
1.住宅ローンの金利と比べてつなぎ融資は割高
2.つなぎ融資には諸々諸費用が発生する
3.つなぎ融資には限度額がある
4.住宅ローン実行時には完済していなければならない
5.つなぎ融資のみの利用は基本できない
6.基本的に住宅ローン控除がつなぎ融資には適用されない
7.予定していた住宅の完成日が遅れると利息が増える
それぞれ確認していきましょう。
1.住宅ローンの金利と比べてつなぎ融資は割高
着工金
金利
着工~引渡
借入期間
金額
1,000万円
2.6%
365日
90日
64,110円
上棟金
金利
上棟~引渡
借入期間
金額
1,000万円
2.6%
365日
60日
42,740円
この表では1つの例として利息金額を算出したものです。
特に重要なのは金利と借入期間で、事前にこの2つを把握しておけばどのくらいの利息額になるから目安として計算が可能です。
表で紹介した着工金と上棟金を合わせると106,850円となるので、住宅ローンに比べてつなぎ融資の金利が高くなることは覚えておいてください。
2.つなぎ融資には諸々諸費用が発生するつなぎ融資には、利用するにあたって諸々の諸費用が必要になります。
1.印紙税
2.住宅融資保険料
3.団体信用生命保険
4.事務手数料
主に上記4つは一般的にかかるといわれているのですが、金融機関によっては印紙税以外の3つが異なる場合があるのでよく相談しておきましょう。
3.つなぎ融資には限度額がある
上限がなく、希望金額を申告すればその額を融資してくれるということはありません。
最大何万円と提示しているところや、借入額は住宅ローンと同じ金額でなければならないなど金融機関によって異なるのでつなぎ融資を利用する際に確認はしておきましょう。
また、つなぎ融資を数回に分けて利用を考えている人は、分割回数や1回あたりの融資金限度額を設けている場合があります。
事前に融資担当者から説明をされることが多いですが、念のため確認はしておいた方が安心です。
4.住宅ローン実行時には完済していなければならない
つなぎ融資を利用するまでの流れでも紹介しましたが、住宅ローンは住宅が完成して引き渡された段階で融資が実行されます。
そのため、住宅ローンの融資金でつなぎ融資を一括で完済しなければならないのです。
完済する段階で事務手数料や印紙税などといった諸々の諸費用も一緒に精算していきます。
5.つなぎ融資のみの利用は基本できない
つなぎ融資だけの利用はできないので、住宅が完成するまでの資金を一時的に立て替えてほしいと考えている人は、住宅ローンの融資の承認を得ている必要があるのです。
そのため、つなぎ融資の利用を検討している場合は必然的に住宅ローンの融資をするのが前提となります。
ですが、銀行ではなくノンバンクならつなぎ融資のみの利用も可能だったりします。
ノンバンクは融資に特化した金融機関なので、借り入れだけにスポットを充てると大して差はありません。
知名度はまだまだ銀行に比べて劣ってはいるものの、1つの選択肢として検討してみてくださいね。
6.基本的に住宅ローン控除がつなぎ融資には適用されない
住宅ローンありきのつなぎ融資ですから、基本的につなぎ融資は住宅ローン控除の対象としては認められません。
なぜなら住宅が完成するまでの「つなぎ」であり、返済は必須となるからです。
ただし、住宅ローンの一定条件を満たしていれば住宅ローン控除は可能です。
条件などに関しては、融資を受ける金融機関に相談してみましょう。
7.予定していた住宅の完成日が遅れると利息が増える
つなぎ融資は基本的に注文住宅を検討している人が利用することが多い融資制度なのですが、住宅の引き渡し完了までの期間に相当する利息が発生します。
ですが、万が一何かしらのトラブルで予定していた完成日を過ぎてしまう場合は、支払利息が増える可能性も。
スケジュール通りに工事を進めて行くのは前提ではありますが、借入可能な期限が事前に設定されていることも考えられますので注意が必要です。
まとめ
つなぎ融資の仕組みや、利用する際の注意点などを紹介してきました。
つなぎ融資だけでなく住宅ローンもですが、無理のない計画的な資金計画を立ててから利用することをおすすめします。
融資額は返済していかければならないものではありますが、無計画で進めると後々トラブルに繋がる可能性も。
借入金額の条件などを制限されているケースも多いため、どうしても利息が高かったり諸費用が発生したりしてしまうもの。
住宅完成後、無理のない返済が可能か。
自身の収入やこれまでの貯金などを考えた上で、つなぎ融資を検討してみましょう。
住宅購入を検討しているが、無理なく住宅ローンを返済していくにはどうしたらいいのか。
マイホームを持つことは大きな夢であり、憧れを持つ人も少なくありません。
今回は、年収400万でも現実的な計画性のあるローンの組み方をいくつか紹介していきます。
ローンの金額によって返済計画は違ってきますから、一般的によく計画されている返済プランを挙げて行きます。
年収400万円で住宅ローンは組めるのか?頭金なしは可能?年収400万円で住宅ローンは組めるのは不安に感じている人は多いですが、決して組めないことはありません。
むしろ年収400万円でも住宅ローンを組んでいる人は大勢存在していますし、ほとんどの人たちが無理のない返済プランを計画しています。
年収400万円の手取りは月に約26万円月々の手取り額は会社によって異なりますが、年収400万円の手取りは平均26万円となっています。
ただし、ボーナスなしで社会保険料やその他税金などが引かれての金額です。
その為、年間での手取り額はざっと312万円程。
月の手取り額からさらに生活費に充てる分がありますので、自由に使える金額はおよそ10万円程度だといわれています。
年収400万円住宅ローンを組むことは可能か?結論からいうと、年収400万円でも住宅ローンを組むことは可能です。
先ほども触れた通り、自由に使える金額はおよそ10万円ですからそこからローンに充てられる金額を割り出して行けば良いだけのこと。
現実的に考えるなら、年収400万円だと10万円以下に抑えることが大切です。
住宅ローンは1年や2年では返済しきれないため、一般的に数十年かけて返済していきます。
仮に1ヶ月に10万円のローンを組んだとして、年間120万円の返済額が発生します。
返済比率としては、だいたい年収の25%までに留めておくことが重要です。
・年収の25%÷12ヶ月
上記の数式で出た金額が、返済可能な上限額ということを覚えておいてください。
年収400万円の人なら、約83,000円までが無理のない返済可能額ということです。
頭金の支払いは絶対に必要?一般的には頭金の支払いは必要になることはほとんどです。
まれに頭金なしでも可能な物件は存在していますが、頭金がそのまま物件価格に乗るため全額がローンの対象となります。
そのため、審査の難易度が跳ね上がって通りにくくなる可能性があります。
逆に支払う頭金の上限額はありませんから金額を増やすことで、住宅ローンの借入金額を減少させることは可能です。
物件も購入しやすくなりますので、融資額が足りないという人は頭金を増やすことで解決できる可能性もあります。
年収400万円の方に観てほしい住宅ローン借りる際のお金について住宅ローンには、購入物件以外にもさまざまなお金がかかります。
今回は、諸費用と自己資金について触れて行きます。
物件購入時に発生する「諸費用」は何があるの?建物だけでなく土地を購入する際には、必ず「登録免許税」や「不動産取得税」といった諸々の申請が必要です。
物件購入したら、火災や地震保険などに加入して保険料を支払います。
住宅ローン関連の手数料も発生するので、これらを総称して「諸費用」と呼びます。
新築物件を購入する場合だと、住宅価格の3~5%。
中古物件だと、5~10%が諸費用に充てられるのです。
物件購入の「自己資金」はどれくらい必要?物件購入費や諸費用のことをも考えると、ある程度自己資金は持っておいて損はありません。
ひと昔前までは住宅ローンの契約基準で、物件価格の2~3割ほどが必要でした。
2021年現在では頭金が不要のところもありますが、その分月々の返済額も上がるので可能なら頭金分の自己資金は用意しておくことをおすすめします。
その他諸々の自己資金の目安としては、物件の約20%以上は持っておくと良いでしょう。
※住宅種別によっては自己資金率が20%以上のところもあるようですので、あくまでも参考にして頂ければと思います。
いくらまで組める?年収400万円の借り入れ可能額をシミュレーションここでは、実際に年収400万円の人が借り入れできる可能額を紹介していきます。
今回の条件としては以下の通り。
年収
400万円
返済可能な金額
83,000円
自己資金
100~500万円
返済金利
2%
年齢
30歳
返済期間
35年
頭金
無
100万円
200万円
300万円
400万円
500万円
借り入れ限度額
2,506万円
購入可能額目安(新築物件)
2,405万円
2,505万円
2,605万円
2,705万円
2,805万円
2,905万円
購入可能額目安(中古物件)
2,280万円
2,380万円
2,480万円
2,580万円
2,680万円
2,780万円
諸費用は、新築物件4%で中古物件9%として計算しています。
上記のシミュレーションでの結果はあくまでも目安ですので、詳しく知りたい人はお近くの金融機関に相談してみてください。
3000万円の住宅ローンを組んだ場合の返済シミュレーション3000万円の住宅ローンを組むにあたって、今回の条件としては以下の通り。
物件価格
3000万円
返済期間
35年
返済金利
2%
頭金
100~500万円
ボーナス
無
月々の支払額シミュレーションは以下の通り。
頭金
100万円
200万円
300万円
400万円
500万円
月々の支払額
9.6万円
9.3万円
8.9万円
8.6万円
8.3万円
年収400万円の人が無理なく返せる金額-金額別に解説-
一般的に年収の5~6倍程が、無理なく住宅ローンの返済を継続できる借入額といわれています。
ここでは年収400万円の人が、各種住宅ローンを組んだ場合に返済できる金額を解説していきます。
年収400万で住宅ローン3000万の場合年収400万円円で3000万円の住宅を購入する場合、ほぼ必ずといっていいほど頭金の用意は必須です。
本記事で何度も触れている頭金なしのプランもありますが、審査と今後のことを考えると頭金はあった方が良いです。
なので、だいたい頭金を500~600万円用意しておいて、借入額を2,400万円まで引き下げれば毎月8万9,000円~7万1,000円で返済が可能です
年収400万で住宅ローン3500万の場合年収400万円だと3000万円の住宅ローンが限界だったりするので、この辺の金額になると審査上頭金は必須です。
返済比率が高すぎると審査に落ちる可能性が高いため、3,500万円で組むなら年収600万円が理想とされています。
35年ローンで組んだとしても、無理なく返済という点ではやや難しいといえます。
年収400万で住宅ローン4000万の場合そもそも年収400万円の場合、借入限度額は約3400万円までしか借り入れができません。
年収500万円の人でも返済が厳しい状況に陥りやすいので、金銭的な負担が大きいといえます。
年収400万で住宅ローン5000万の場合年収400万円で5000万の住宅ローンは不可能です。
まず審査が通らないという問題が発生するため、5000万の住宅ローンを組む場合年収700万円は合った方が良いです。
600万円の人でも不可能ではありませんが、ギリギリのラインだといえます。
年収400万円の住宅ローンを借りる際の注意点最後に年収400万円で住宅ローンを借りる際の注意点を3つ紹介していきます。
1.借りる際の年齢住宅ローンを組む際は、自身の年齢を考慮する必要があります。
返済期間は最長35年で、その間に何歳までなら家計が圧迫されないかなどを慎重に考えなければなりません。
60代や70代になるにつれて毎月の支出が厳しいと感じることもあるため、借りる際の年齢は考慮しましょう。
2.支払いを終える年齢各金融機関にもよりますが、一般的に80歳の誕生日までが住宅ローン完済時の上限年齢とされています。
ですが一般的な会社勤めであれば定年退職をする年齢(65歳まで)までには、完済していることが理想です。
購入する住宅の形態にもよりますが、だいたい30代後半~40代前半にローンを組み始めて30年弱くらいで完済している人が多い傾向にあります。
3.月々で無理のない返済額は?年収400万円なら、月々約83,000円が無理のない返済額だといわれています。
400万円なら年収の25%までが返済比率といわれていますから、今後のライフイベントなどを考慮して無理のない返済をしていきましょう。
まとめ年収400万円の人が3000万円の住宅を検討する場合、可能であればやや多めの頭金を用意しておくことをおすすめします。
頭金が多ければ多いほど返済額も少なく済みますし、余裕を持った暮らしが実現可能です。
理想の暮らしを送るために、今一度自身の収入面などを考慮してみましょう。
新生活を始める上で、お部屋探しは重要なポイントです。
優良物件の条件は人それぞれですが、お部屋探しの流れや、探し方のコツを知ることで、より自分に合ったお部屋が見つかる可能性が高まります。
お部屋探しの失敗談も紹介していますので、初めてのお部屋探しでお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも優良物件の探し方のコツを知っておく理由は?
優良物件の探し方のコツを知っておくべき理由は、本当に自分に合った物件を見つけるためです。
希望条件にもよりますが、数あるお部屋の中から優良物件を選ぶことは簡単ではありません。
やみくもに探すのではなく、部屋探しのコツを掴むことが理想の部屋への近道といえます。
優良物件の探し方のコツ7選
お部屋探しをする上で、知っておくべき探し方のコツを7つ紹介します。
不動産情報サイトはこまめにチェックしておく 不動産会社とのコミュニケーションを密にしておく 少しでも良いなと感じた物件は内見に行く 理想の条件について優先順位を決めておく 条件に該当する物件は複数ピックアップしておく 入居前の仮押さえは原則不可 少しでも疑問や不明点があれば随時質問
順番に解説します。
不動産情報サイトはこまめにチェックしておく
不動産情報サイトはこまめにチェックしておくことが大切です。
ただし、こまめにといっても1時間毎にチェックする必要はありません。
1日1回、時間ができた時に不動産情報サイトを覗いてみましょう。
掲載物件は毎日更新されますので、定期的にチェックすることで理想の物件に出会いやすくなります。
不動産会社とのコミュニケーションを密にしておく
優良な物件と出会うためには、不動産会社とのコミュニケーションを密にしておくことも重要です。
不動産情報サイトをチェックしているからといって、必ずしも良い物件に出会えるとは限りません。
中には非公開物件といって、実際に不動産に行かなければ見つからない物件も存在しています。
まずは不動産に足を運んで、不動産会社の担当者に条件に見合う物件が出たら連絡するようお願いしましょう。
少しでも良いなと感じた物件は内見に行く
内見に回数制限はありませんから、少しでも良いなと感じた物件は内見に行くことをおすすめします。
気になった物件は他の人も狙っている可能性がありますから、なるべく早い内見予約をしましょう。
理想の条件について優先順位を決めておく
理想の条件が頭の中にある場合、優先順位を決めておきましょう。
物件の条件は人それぞれですが、100点満点の物件は存在していません。
例えば、家賃が安い物件を見つけたとしても、お風呂とトイレが一体型のユニットバスだったということもあり得ます。
さらに極端な話、家賃3万円ほどでなおかつオートロックの高層マンションは見つかりません。
理想が高過ぎると見つからないので、完璧すぎる条件は避けましょう。
条件に該当する物件は複数ピックアップしておく
条件に該当する物件は1件に絞る必要はなく、2〜3件ほどピックアップしておくことをおすすめします。
その中で第一志望を決定し、埋まってしまった時のことを考えて第二・第三候補の物件を見積もっておきましょう。
入居前の仮押さえは原則不可
内見は何回でも可能ですが、1件気に入った物件があったけれど入居前の仮押さえは原則不可となっております。
物件は常に早い者勝ちですので、引っ越しシーズンである1月〜3月は決断力が勝負の分かれ道です。
少しでも疑問や不明点があれば随時質問
実際に住む可能性がある物件の疑問や不明点は、些細なことでも良いので担当者に質問しましょう。
「気にはなるけれど大した問題ではない」と決めつけて入居してしまうと、後々後悔する可能性があります。
遠慮する必要はないので、随時質問しましょう。
優良物件の探し方でおすすめの流れ
優良物件を見つけるためにも、お部屋探しの流れを把握しておきましょう。
おすすめの流れは、以下の通りです。
家賃を明確にする 最低限の間取りを決める 最低条件を設けておく 不動産情報サイトを利用する 不動産に行って内見依頼をする 賃貸契約をする
順番に解説します。
家賃を明確にする
住みたいエリアを決めるのと同時に、家賃を明確にしておくのも大切です。
家賃は住むエリアによって大きく差が出ますので、希望のエリアの家賃相場と予定している家賃を比較してみましょう。
ちなみに、観光客が訪れやすい繁華街や駅近に大型ショッピングモールなど施設が整っている市街地などは家賃が高めに設定されています。
さらに、一般的に家賃は収入の1/3程度に留めておくことが最適だといわれています。
生活費を多少節約すればもう少し家賃に充てられますが、急な出費などが発生することを考えると現実的ではありません。
最低限の間取りを決める
住む人数によって間取りも異なるため、最低限の間取りは決めておきましょう。
1人暮らしなら1R〜1DKほどで、同居人がいるなら1DKほどがおすすめです。
家賃を少しでも抑えたい人は、少ない間取りを選びましょう。
間取りを選ぶ人の中には、趣味の部屋などを設けるために生活空間を分ける人も少なくありません。
料理はするけれど、寝室に料理の匂いを移したくないという人も1DK以上の間取りを選んでいます。
最低条件を設けておく
ここで細かな最低条件を設けましょう。
細かな条件というのは、最寄り駅までの距離やユニットバスなどのことです。
ユニットバスではなく、お風呂とトイレは別であってほしい コンロはIHがいい 築年数は10年以下 駅から徒歩5分圏内
上記のように、条件は挙げたらキリがないので多くても3〜5個までにしておくと物件が探しやすいといえます。
不動産情報サイトを利用する
SUUMOやホームズなど、不動産情報サイトを利用して物件を探しましょう。
ここまでにいくつかの物件条件が決まっていますから、自分が求める条件に合った物件を複数比較してください。
同じ条件の物件が複数存在することもありますが、その場合は外壁やレイアウトの配置などをチェックしてみることをおすすめします。
不動産に行って内見依頼をする
気になる物件にある程度目星が付いたら、直接不動産に行って内見依頼をしましょう。
内見は当日に行える時もありますが、不動産のスケジュールに空きがなければ後日になります。
事前に不動産会社に連絡を取ってから足を運ぶことをおすすめします。
賃貸契約をする
内見が完了し、実際に自分の目で見て納得できたら賃貸契約をします。
賃貸契約には審査が入り、見事通過できれば本契約に進みます。
審査の基準は一般公開されることはなく、審査落ちした場合でもなぜ落とされたのかの理由は教えてもらえません。
ですが、契約者に家賃の支払い能力はあるかどうかの確認や、保証人や保証機関の可否などがチェックされているといわれています。
一般的に入居審査に要する期間は3~5日程度ですが、提出した書類に不備があるとその分期間が長引くので注意が必要です。
優良物件探しの失敗談7つ
優良物件探しの失敗例をピックアップしていますので、自分たちの部屋探しをイメージしながら見ていきましょう。
失敗談1:家賃が払えなくなった 失敗談2:収納が狭かった 失敗談3:日当たりが悪かった 失敗談4:追加駐車場が確保できなかった 失敗談5:景観が悪くなった 失敗談6:インターネット速度が遅かった 失敗談7:家族構成を考えずに部屋を決めてしまった
順番に解説します。
失敗談1:家賃が払えなくなった
失敗談の一つに、家賃が払えなくなったというものがあります。
どんなに良い条件の部屋でも、家賃の支払いに追われる状況では、快適な暮らしとはいえません。
手取り収入の3割程度を家賃の目安とし、家計に無理のない計画が必要です。
失敗談2:収納が狭かった
収納が狭かったという声も失敗談としてよく耳にします。
内見をせずに部屋を決める際は、特に注意が必要です。
新築や遠隔地など内見ができないケースでは、図面などを用いて収納量をチェックしておきましょう。
失敗談3:日当たりが悪かった
日当たりの悪さも失敗談の一つです。日当たりは実際に住んでみなければ分かりづらく、一度の内見だけでは判断できません。
外からでも良いので、時間をずらして複数回、確認することをおすすめします。
失敗談4:追加で駐車場が確保できなかった
敷地内駐車場の台数が少ない場合、追加駐車場が借りられないことも失敗談として挙げられます。
近隣でも見つからない場合、引越しを検討しなければならない可能性も。
駐車場台数を事前に確認することをおすすめします。
失敗談5:景観が悪くなった
景観が悪くなったという失敗談にも注意が必要です。
隣に新しい建物が建つことで、ベランダからの眺めが悪くなるケースがあります。
建物の周りに空地がある場合、事前に建築の予定がないかどうかを確認しておきましょう。
失敗談6:インターネットの速度が遅かった
備え付けのインターネット速度が遅く使えなかったという失敗談もあります。
インターネット無料の物件が増えていますが、一本の回線を分けて使うケースでは、時間帯により回線が混雑することも。
結果、自身で回線を引き直すことで、余計な出費が発生する可能性があります。
失敗談7:家族構成を考えずに部屋を決めてしまった
家族構成を考えずに部屋を決めることも失敗談の一つ。
具体的には、広い部屋が良いからと、単身でファミリー物件を選ぶケースが挙げられます。
ライフスタイルや価値観の違いにより、周りの音が気になったり、他の住民と馴染めなかったりといったリスクを考慮する必要があります。
優良物件の探し方の注意点
優良物件を探すために、覚えておきたい注意点を紹介します。
審査前に初期費用の交渉もなるべく行う 審査書類は丁寧かつ正直に記載 重要事項の説明は聞き流さない キャンセル可能は契約書を書くまで 鍵の受け取り後は室内を必ずチェック
順番に解説します。
審査前に初期費用の交渉もなるべく行う
一つ目の注意点は、審査前に初期費用の交渉も行うことです。
入居審査までに交渉内容をまとめておきましょう。
交渉のタイミングもテクニックの一つです。
審査書類は丁寧かつ正直に記載
審査書類は丁寧かつ正直に記載するように注意して下さい。
審査書類に不備があれば、審査期間が長引きますし、内容の虚偽は契約解除の要件となります。
お互いの手間を減らすためにも、審査書類は正確に記載しましょう。
重要事項の説明は聞き流さない
重要事項の説明を聞き流さないことも注意点の一つ。
契約内容を合意する上で、重要な内容となりますので、不明な点はその場で確認して下さい。
契約書ひな形で事前に内容を確認しておけば、安心して臨めるでしょう。
キャンセル可能は契約書を書くまで
入居申込のキャンセルは契約書を書くまでと覚えておきましょう。
契約書を取り交わした後は、キャンセルではなく解約となりますので、解約にかかる費用が発生することに注意が必要です。
鍵の受け取り後は室内を必ずチェック
鍵の受け取り後は室内を必ずチェックすることも注意点の一つです。
退去時のトラブルを防ぐためにも、入居時に室内の破損・汚損の状況を確認しておきましょう。
写真で記録を残しておく方法もおすすめです。
マイホーム購入という選択肢もある
ライフステージの変化に伴う引越しをお考えの方は、マイホーム購入も選択肢の一つです。
賃貸に比べ、より自分たちに合った暮らし方を実現できることが理由として挙げられます。
住宅ローンの支払いが家賃と同程度あれば、土地を含め資産として残るマイホームにお金をかけたいと感じる方が多いのではないでしょうか。
優良物件の探し方に関するよくある質問
優良物件の探し方に関するよくある質問をピックアップしてまとめています。
物件を探し始めるのは引越しの何ヶ月前が理想? 未公開物件の探し方はある? 「即入居可」と記載がある物件は即日入居できる? 選ばないほうがいい賃貸物件はある?
順番に解説します。
物件を探し始めるのは引越しの何ヶ月前が理想?
一般的に、物件を探し始めるのは1ヶ月前が理想とされています。
理由として、申込から入居開始までの期間が1ヶ月以内とされるケースが多いためです。
部屋の取り置きはできないので、無駄な家賃を抑えるためにも、引越しの1ヶ月前が目安といえます。
未公開物件の探し方はある?
不動産会社に直接問い合わせることで、未公開の新築情報や空き予定の情報が手に入ることがあります。
ポータルサイトには情報のタイムラグがあることが理由です。
「即入居可」と記載がある物件は即日入居できる?
入居審査や契約手続きが必要であるため、即日入居は現実的ではありません。
早く入居したい場合、営業日換算で最短入居日を不動産会社へ確認することをおすすめします。
選ばないほうがいい賃貸物件はある?
希望の条件は人それぞれ異なるため、一概にはいえません。
立地・間取り・家賃を総合的に判断して、自分の条件に合った物件を選ぶことが重要です。
まとめ:優良物件の探し方のコツを知って理想の暮らしを
ここまで優良物件の探し方のコツと流れについて解説してまいりました。
自分たちの理想の暮らしをイメージすることが優良物件に出会う近道です。
しかしながら、賃貸物件では理想の暮らしを実現できないケースもあります。
そんな時は、マイホームの建築も選択肢に入れてみるとよいでしょう。
建匠は家族の思いを込めたオンリーワンのお家づくりを提案しています。
賃貸住宅に満足できない方は、お気軽にモデルハウスへお越し下さいませ。
親世代と子世代が同じ家に住む二世帯住宅。
二世帯住宅といってもその中で種類があり、親世帯と子世帯の関係によって住みやすい二世帯住宅というものは変わってきます。
そのため、家族によっては二世帯住宅で良かったというケースもあれば、後悔をすることになってしまったというケースも存在します。
二世帯住宅で後悔をしないためには、二世帯住宅がどのようなものなのか、どんなメリット・デメリットがあるかを知った上で検討することが大切です。
今回は二世帯住宅にはどんなものがあるのか、メリットやデメリット、二世帯住宅を建てる際に利用できる補助金制度について紹介します。
二世帯住宅の種類
一口に二世帯住宅といってもその中でいくつかの種類が存在します。
ここでは「完全分離型」「部分共有型」「共有型」の3種類を見ていきましょう。
二世帯住宅の種類:完全分離型
文字通り親世帯・子世帯で生活を完全に分離するタイプの二世帯住宅です。
住宅を左右に仕切る、1階と2階で分けるといったように、親世帯・子世帯で生活が交わらないような住宅です。
生活が交わらないということからライフスタイルの違いでトラブルになるということを避けやすい上に、いざというときはすぐに駆けつけられるといった点が大きなメリットです。
しかし、各世帯それぞれで設備を用意する必要がありますので費用がもっともかかるのがデメリットといえます。
二世帯住宅の種類:共有型
2つの家族が家のすべてを共有するタイプの二世帯住宅です。
風呂やトイレ、キッチン・リビングなど、個人の居室以外のすべてを一緒に使用して生活します。
設備を共用する分、家を建てる際にかかる施工費用や生活費を低く抑えられることや、親世帯と子世帯の距離が最も近く、家族での交流が多いほうが良いという方にとっては非常に大きなメリットと言えるでしょう。
反面、ライフスタイルにずれがある場合はそれぞれの世帯が気を使う必要も多くなり、ストレスを感じやすくなることもあるのがデメリットといえます。
二世帯住宅の種類:部分共有型
玄関やお風呂などの一部の設備を親世帯・子世帯で共用するタイプの二世帯住宅です。
完全分離型と共有型の中間のようなタイプでお互いのライフスタイルをある程度維持しながら一緒に生活しやすいということがメリットといえます。
デメリットとしては完全分離型ほど気にしなくてもよいというわけでもなく、共有型よりも施工費用や生活費は高くなるということが挙げられます。
親世代・子世代それぞれから見る二世帯住宅のメリット 親世帯のメリット・デメリット
◯メリット
・子世帯と好きなときにコミュニケーションを取れる
・病気やケガをした場合はお互いの世帯を頼ることができる
・子世帯の子育てに協力できる
・将来の介護についても子世帯を頼れる
「病気や怪我の場合」と「将来の介護」は親世帯からすると大きなメリットといえます。
二世帯住宅なら、遠距離別居と違って、将来介護をしてもらう際にも移動などの手間をかけずに済みますし、急な病気やケガの際にも子世帯に頼りやすい環境です。
◯デメリット
二世帯住宅は、距離が近い分、お互いのいやなところや生活リズムの違いも目につきやすいものです。
完全分離型のような場合であればライフスタイルの違いなどによるストレスの軽減はできますが、その場合でもお互いの世帯が顔を合わせる機会が多いことには変わりません。
二世帯住宅を建てる場合は、親世帯と子世帯が本当にストレスなく同居していけるか、よく考える必要があります。
子世帯のメリット・デメリット
◯メリット
・親にお金を出してもらえば広い家を建てられる
・家に親がいてくれるため子どもの世話を任せられる
・生活費を二世帯で負担すれば月々の電気代やガス代の節約になる
子世帯側から見ると、二世帯住宅は「節約」と「子育てサポート」が主な魅力だといえます。
生活費の軽減や子育て世代の場合は子供の面倒を見てもらうということも行いやすいのが魅力になるでしょう。
◯デメリット
子世帯にとっても、「距離の近さ」は無視できないデメリットです。
特に、義理の両親と暮らすとなった場合、気になるところがあったとしてもなかなか言い出しづらいといったようなこともあり得るでしょう。
世代によって考え方や常識などは異なるものですので、ライフスタイルに口出しをされ、ストレスをためてしまうこともあり得ます。
二世帯住宅における補助金
ここまでで二世帯住宅は建築コストが上がるということがデメリットとしてありましたが、二世帯住宅でも使用できるおすすめの補助金を紹介します。
・すまい給付金
・地域型住宅グリーン化事業
・長期優良住宅化リフォーム推進事業
「すまい給付金」を利用すると、収入や住宅の仕様に応じて最大50万円もらえます。
元々は2021年12月末までの入居が条件となっていましたが、2022年12月末までに期間が延長されました。
また、「地域型住宅グリーン化事業」は、長期優良住宅などのエコ性能が高い仕様にした場合、最大140万円資金を補助してもらえる制度です。
最後の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、リフォーム専用の補助金制度です。
リフォーム後の住宅性能によって、最大250万円の補助金を受給可能です。
ただし、地域型住宅グリーン化事業と、長期優良住宅化リフォーム推進事業は、併用することができませんので注意が必要です。
まとめ
今回は二世帯住宅の種類やメリットやデメリットを、お得な補助金制度をご紹介しました。
二世帯住宅と一口にいっても様々な種類があり、ご家族によって向き不向きがあります。
ライフスタイルや家へのこだわり、性格的な相性等によって、おすすめの住まいは変わりますので、ライフプランや将来を見据えた設計を心がけることが大切です。
新築注文住宅をお考えの方は、二世帯住宅や建て替えもお気軽にご相談ください(^^)/
▽▼ご予約はこちらから▼▽
https://xn--mjrr9y.com/contact/
対応エリア:
高知県(高知市・南国市・土佐市・いの町・香南市・香美市・佐川町・日高村・安芸市周辺)
その他エリアでお考えの方もお気軽にご相談ください!
住宅ローンを組むにあたって、気になるのは「金利」。
住宅ローンでは金利にもいくつかの種類があり、全期間固定型、変動金利型、固定期間選択型といった金利タイプがあります。
今回は、それぞれの金利でどのように違ってくるのか、特徴を解説していきます。
借り入れ先や借り入れ方法についてもさまざまな種類がありますから、どれを選ぶべきか悩んだときに参考にしてください。
住宅ローンの金利タイプにはどんなタイプがあるのか?
住宅ローンの金利は、たった0.1%違うだけでも、実際に支払う金額が大きく変わります。
住宅ローンの金利は、具体的には「全期間固定型」、「変動金利型」、「固定期間選択型」といったタイプがありますので、それぞれの特徴を見ていきましょう。
全期間固定型の特徴やメリット・デメリット
借り入れる全期間中の金利が変わらないが、その分金利が高くなりやすいのが、全期間固定型です。
◯全期間固定型のメリット
・借り入れ期間中は常に金利が固定されるため、返済額が確定している
・低金利の時に契約すれば、その恩恵を完済時まで受けることができる
・毎月の返済額が変わらないので、安心感がありライフプランを考えやすい
先が見えない社会において、現在の金利だけを参考にしていると金利が上がったときに支払いが厳しいと感じられるようになるかもしれません。
また、固定給ではなく収入の変動が大きい人の場合には、現在から一年後、二年後、十年後、三十年後の経済状況を予想するのは簡単なことではないでしょう。
そうした不安のある人にとって、常に一定の支払いで問題ない全期間固定金利型は非常に魅力的です。
たとえ収入が減ってしまったとしても、返済額は変わらないため収支計画も立てやすくなります。
◯全期間固定型のデメリット
・市場の金利がいくら下がっても、返済する金利は高いまま変わらない
・借入後、金利タイプの変更が自由にできない
デメリットとしては、他の金利タイプに比べて、金利がやや高くなる傾向があるということや借り入れた段階から更にお得にはならないということでしょう。
将来的に市場の金利が上がっていく動きがあれば他のタイプと比べてお得とはなりますが、金利が下がっていった場合にも安くなるということは有りませんので損をしたと感じられるかもしれません。
後述しますが、全期間固定型の代表的なものに「フラット35」があります。
変動金利型の特徴やメリット・デメリット
現状金利が最も安くなるが、今後金利が上がったり下がったりするのが、変動金利型です。
変動金利型という名前の通り、常に金利が変動する可能性があることが特徴です。
金利の変動は、半年に一回見直されます。そのときに改められた金利をもとにして、実際の返済額が5年ごとに変わっていきます。
◯変動金利型のメリット
・固定金利より金利が低い
・金利が下がると、返済額が減る
メリットとしては、他の金利タイプに比べて金利が安くなりやすいことが挙げられます。
しかし、これから先、金利がどうなっていくかはわかりません。
◯変動金利型のデメリット
・急激に金利が上昇した際に、「未払い利息」が発生する可能性がある
・将来の返済額や総返済額が読みづらいため、ライフプランが立てにくい
デメリットとしては「とにかく今、金利が安ければいい!」という考えでいると、将来的に金利が上昇したとき支払額が増えてしまうこともあるでしょう。
メリットとデメリットが表裏一体であることが、変動金利型の特徴でもあります。
ただし変動金利には、「125%ルール」と呼ばれるルールがあります。
125%ルールとは「仮に金利が大きく上昇したとしても、新たな返済額はそれまでの125%以上にはならない」というルールです。
これまでの返済額が月々10万円であれば、そのあと金利が上昇したとしても返済額が月々12万5000円以上にはならないというものです。
収入が不安定というわけではない人や、125%ほどの変動をしていくと仮定して計算してもそこまでの痛手にならないと考えられるのならば、変動金利型を選んでみるのもいいかもしれません。
固定期間選択型の特徴やメリット・デメリット
こちらは先ほどご紹介した「変動金利型」と「固定金利型」のどちらの要素も兼ね備えたタイプです。
固定期間選択型では、まず金利を固定する期間を決定します。
10年や20年など任意の期間においては、固定型と同様に金利が一定になります。
そして固定期間が終わったら、そのあと改めて「固定金利型」と「変動金利型」のどちらを選択するか決定します。
状況に合わせて金利を固定にしながら、必要なプランを見直せる点が大きな魅力と言えるでしょう。
先にご紹介した「固定金利型」と「変動金利型」のいいとこ取りができる一方、デメリットもあります。
固定期間選択型では前述した変動金利型の125%ルールは適用されません。
急激に金利が上昇した場合、125%以上の支払いとなってしまう可能性があります。
また、固定期間が終わってからは金利の優遇幅が小さくなり、返済額が増える可能性もあります。
こちらは固定期間が終わってしまうまでに繰り上げ返済ができれば、比較的スムーズに返済できますので、余裕のある返済計画が立てられそうであれば、固定期間選択型を選ぶのもよいでしょう。
住宅ローンの借入先の選択肢
住宅ローンの金利については、借入先も大切なポイントです。
民間ローン、フラット35、財形住宅融資といったパターンがありますので、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説していきます。
民間ローンの特徴やメリット・デメリット
民間ローンは「メガバンクや地方銀行をはじめとしたいわゆる民間の金融機関から借りる」というもの。
民間ローンを展開してる金融機関には、メガバンク、ネット銀行、地方銀行、生命保険会社、農協などが挙げられます。
住宅ローンの内容は、それぞれの金融機関によって異なり、金融機関がそれぞれキャンペーンなども実施しています。金利タイプやサービスについてもそれぞれに違うため、ホームページや窓口で内容をよく確認することがおすすめです。
民間の住宅ローンを借りるのであれば、金融機関や保証会社の審査を受けなければいけません。
審査に通らなければローンを借りることもできませんので、注意しましょう。
フラット35の特徴やメリット・デメリット
フラット35は、「利用者と民間の金融機関とのあいだに住宅金融支援機構が入って住宅ローンを組む」ようなものです。
フラット35では、住宅金融支援機構が民間金融機関を通してローンを組みます。
基本的に「全期間固定金利タイプ」の住宅ローンのみを扱っており、先ほどご紹介した通り、このタイプではすべての期間で金利が変わりません。
返済計画が立てやすいのが魅力でしょう。
また、保証会社を通さないことから、金融機関で発生する保証料がかからないのも特徴です。
メガバンクや地方銀行などの銀行のほかに、ネット銀行や住宅ローン専門会社の利用もできます。
こちらも民間ローンと同様に、どの金融機関を利用するかによって金利やサービスが異なります。
財形住宅融資の特徴やメリット・デメリット
財形住宅融資は「財形貯蓄を行っている会社員や公務員」を対象としています。
財形住宅融資の利用条件は、「勤務先にて財形貯蓄を1年以上行った人」のように一定の条件を満たした人のみに限られており、金利については、5年ごとに見直されるのが特徴です。
財形住宅融資は固定金利にできないため、その点には注意してください。
メリットとしては、保証料や融資手数料がかからないため、諸経費を抑えることができます。なお、財形融資はあくまで福利厚生の1つであり、勤務先に財形融資の制度がなければ使用できません。
住宅ローンの借り入れ方法の種類と注意点
ここからは住宅ローンの借り入れ方法についてご紹介します。
こちらもそれぞれの特徴やメリット・デメリットについてみていきましょう。
ペアローンの特徴やメリット・デメリット
ペアローンは「夫婦がそれぞれに異なる住宅ローンを一つずつ、世帯で二つ契約する」のが特徴です。
住宅ローンを組むときには、一般的に一世帯で1つの契約ですが、ペアローンを利用すれば、夫と妻でそれぞれの契約を結ぶことができます。
ペアローンのメリットは夫婦それぞれに住宅ローン控除を受けられる点です。
控除枠を最大限活用できるため、節税にも貢献します。
また、1人で契約をする場合よりも借入額を増やすことができますので、
これまで手が届かなかった住宅を購入するきっかけになるかもしれません。
一方でデメリットとしては、事務手数料をはじめとした諸費用についても単純に2倍になってしまうことが挙げられます。
金銭面だけでなく、契約のわずらわしさについても倍増したように感じられるかもしれません。
また、住宅ローン控除は所得税に対しての控除のため、どちらかが仕事を辞めたときには受けられなくなってしまいます。
連帯債務の特徴やメリット・デメリット
契約者が1名であるのに対し、連帯債務者としてもう1名の連名で契約するのが、連帯債務です。
連帯債務の場合、主の契約者1名、そして連帯債務者1名の連名によって住宅ローンを契約します。
例えば、夫が契約者、妻が連帯債務者というような形になります。
メリットとして、連帯債務者の収入も含めて、借入額を決定でき、ペアローンと同様に借入額を増やせるという点が挙げられます。
さらに、どちらも住宅ローン控除を適用できることが挙げられます。
しかし契約そのものは1つであることから、ペアローンと違って諸費用や契約のわずらわしさは1契約分に抑えることができます。
デメリットとしては、連帯債務を取り扱っている金融機関そのものが限られていることが挙げられます。
選択肢が少ない中で、条件の合う金融機関などを探さなければいけません。
また、主となる契約者は団体信用生命保険に加入できますが、連帯債務者はできない可能性もありますので注意しましょう。
連帯保証の特徴やメリット・デメリット
連帯保証は、夫婦のどちらかが返済義務のある債務者、もう一人が保証人となるというものです。
夫婦のうち債務者でない方はあくまで連帯保証人という立場になるのが連帯債務との違いです。
連帯保証人は、なんらかの理由によって主となる債務者が返済できなくなったとき、はじめて返済義務が発生します。
連帯保証のメリットは、あくまで契約そのものは1つに絞られることから、諸費用等が増えないこと。
それでいて連帯保証人の返済能力によって借入額を増やせる可能性があることも特徴です。
条件を満たせば収入合算もできますが、物件の名義は単独にできるため、どちらかにしておきたい世帯におすすめです。
デメリットとしては、連帯保証人は債務を負っているわけではないことから、住宅ローン減税や団体信用生命保険の恩恵を受けられないことが挙げられます。
まとめ
今回は、住宅ローンの金利タイプ、借り入れ先、借り入れ方法についてまとめてご紹介していきました。
それぞれに特徴が異なり、違った魅力があるからこそ、状況に応じて最適な金利タイプや借り入れ先、借り入れ方法を選びましょう。
たとえ同じ金額を借りたとしても、どんな契約をするかによって支払わなければならない金額が変わってきますので、最後までよく検討してください。
▽▼ご相談・お問い合わせはこちらから▼▽
https://xn--mjrr9y.com/contact/
対応エリア:
高知県(高知市・南国市・土佐市・いの町・香南市・香美市・佐川町・日高村・安芸市周辺)
その他エリアでお考えの方もお気軽にご相談ください!
夢のマイホームを手に入れる際、大きく分けて注文住宅で建てる方法と建売住宅を買う方法があります。
注文住宅とは一からすべて自由に決めて建てる戸建てのことで、建売住宅とは土地と建物をセットで買う戸建てのことです。
一見すると夢のマイホームは自由に作れる注文住宅の方が良いと思いがちですが、建売住宅にしかない魅力というのも多いです。
そこで、今回の記事では注文住宅と建売住宅それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
これから家を持とうと思っている方は、ぜひこちらの記事を参考に比較検討してみてください。
注文住宅とは?注文住宅のメリットとは?
注文住宅とは一からすべて自由に決めて建てる戸建てのことです。
まずは注文住宅のメリットを確認しましょう。
注文住宅のメリット:唯一無二かつ自由自在な家を作れる
注文住宅における最大の魅力が、唯一無二かつ自由自在な家を作れる点です。
注文住宅はフルオーダーとセミオーダーがあり、選び方次第で多種多様な家が建てられます。
フルオーダーでは文字通り間取りから外装内装、導入する機能や採用する仕様まで選べます。
セミオーダーではあらかじめ用意されているパーツごとに選ぶことが可能です。
オーナーの方ごとに要望は異なり、人によっては「窓は大きくしたい」「収納を多くしたい」「お風呂は広くしたい」など希望があるはずです。
それらに細かく対応できるのが注文住宅の魅力だといえるでしょう。
注文住宅のメリット:ライフスタイルごとに予算を調節できる
注文住宅はライフスタイルごとに予算を調節できるのも魅力です。
必要なものと不要なものを見極めて、生活する上で使うものだけを取り入れられます。
それ以外はカットできるため、その分、予算を浮かせられるのです。
あまりこだわりがない場合は、節約次第で数十万円~数百万円ほど予算を削減することも可能です。
あまり衣服を持たない方は収納を減らしても良いですし、子供を育てる予定がない方は部屋を減らしても良いです。
ライフスタイルはオーナーの方ごとに違うため、必要のないものはカットして負担を減らすという手段も選べます。
注文住宅のメリット:建築している過程を見学できる
注文住宅は土地を購入して基礎を作り、建物を引き渡すところまで自分の目で見学できます。
一生住むことになる家のことなので、作る過程を見られるというのは大きな魅力です。
当然ながら自分の家がどのように作られているのかも知れるため、より愛着が生まれるのではないでしょうか。
また、手抜き工事を未然に防ぐことにもつながります。
工務店やハウスメーカーは無数にあり、すべてが完璧な仕事をしてくれるかどうかは未知数です。
疑うことは避けたいですが、それでも建築途中で見学することで、建築業者だけではなく職人たちがどのような仕事をしているのかも確認できます。
注文住宅のデメリット
次に注文住宅のデメリットについても把握しておきましょう。
注文住宅のデメリット:予算がオーバーする可能性もある
注文住宅はこだわりを詰め込むあまり、予算がオーバーしてしまう可能性も高いです。
削れるところは削って予算を削減する方もいますが、多くの場合は予算を超えてしまいます。
そのため、どうしても割高になることは否めません。
また、数千万円単位での買い物となるので、数万円や数十万円は誤差と考えて予算に組み込みがちです。
曖昧な決め方をすると最終的には数百万円も予算をオーバーしていることがあるため、注意が必要です。
特に、住みやすい家にしようとすればするほど予算も比例して高くなります。
優秀な設備や機材を取り入れれば住み心地は良くなる一方、予算も高くなるでしょう。
希望と予算を天秤にかけて計画していくことが必要です。
注文住宅のデメリット:イメージ通りにならないこともある
注文住宅は一からすべて作るため、イメージをいかに具現化するかが重要です。
しかし、頭の中で「こうしたい」「ああしたい」と考えていても、実際に建築するとなるとイメージと違うこともあります。
近年は3DやVRなどの活用でイメージも掴みやすくなってはいるものの、それでも限界があります。
自分で絵が描けるなら良いのですが、建築業者に言われるがまま作っていくと思い描いたイメージとは違う家になるかもしれません。
こればかりは工務店やハウスメーカーなどと入念に打ち合わせを行うべきです。
注文住宅のデメリット:着工から完成まで時間がかかる
注文住宅は契約後に着工するわけですが、完成まで時間がかかります。
土地選びから建物の引き渡しまで含めると、約14~15ヵ月ほどかかるのが一般的です。
設計事務所などに相談する場合は、それだけで約3ヵ月かかります。
そこからプランを練り上げ、見積もりから設計に入る段階で約半年かかります。
いよいよ工事に入ったとしても、そこから約6ヵ月前後はかかるでしょう。
その際、特殊な工法や特集の建材を用いる場合、さらに工期は長くなります。
最低でも1年はかかると見ておくことが重要です。
建売住宅とは?建売住宅のメリットとは?
建売住宅とは土地と建物をセットで買う戸建てのことです。
ここからは建売住宅のメリットをご紹介します。
建売住宅のメリット:注文住宅と比べて安価な価格設定となっている
建売住宅は住宅ローンを使って土地と建物の代金を一括で払えるため、経済的負担を軽減できます。
そもそも良心的な価格設定となっている場合が多く、予算が限られている方でも購入可能です。
財布と相談しながら幅広く選べるのは魅力も大きいでしょう。
また、予算も土地と建物を合わせた販売価格となるため、返済計画も立てやすいのが魅力です。
近年は住宅ローンを組むだけでも人生の大きな負担となることから、どうしても躊躇してしまう方も多いです。
しかし、それでも夢のマイホームを手に入れたいということなら、予算を先に決めてから建売住宅を探すというのも良いかもしれません。
建売住宅のメリット:実物を見てから購入を決められる
建売住宅はすでに完成済みのものも多いため、実際の現場を下見してから購入できます。
つまり、自分たちが住む物件の実物を内見しつつ選べるわけです。
着工から自分の目で見たいという方も多いですが、完成した物件を購入前に確認できるというのはとても大きな魅力です。
特に、イメージ通りの家に住みたいという方には、建売住宅の方がおすすめです。
ただ、建売住宅は建築業者によって建築のスピードも異なるため、場合によっては完成するまで待たなくてはならない物件もあります。
その場合は、完成後に一度確認するなど、購入前によく吟味することが大切です。
建売住宅のメリット:入居するまで時間がかからない
建売住宅は完成済みの物件を購入できるため、入居まで時間がかかりません。
一から家を作るとなると数ヵ月~1年以上はかかるのですが、建売住宅は即入居が可能な物件もあります。
そのため、すぐに家が必要な方にとっては魅力も大きいです。
なお、即入居できるため、生活設計も立てやすいのが特徴です。
一から作る家は工期が遅れてしまうこともある一方、建売住宅は完成済みのものなら予定が崩れることもありません。
そのため、入居後の生活を構築するのも簡単です。
建売住宅のデメリット
次に建売住宅のデメリットについて解説します。
建売住宅のデメリット:こだわりを取り入れられない
建売住宅はこだわりを詰め込むことはできません。
そもそも建売住宅は間取りから外装内装、導入する機能や採用する仕様まで決まっていることがほとんどです。
そのため、基礎などからすべて自分の思い通りにしたい場合は不向きとなります。
事実、こだわりが強い人は建売住宅だと物足りないかもしれません。
ライフスタイルは人によって大きく異なるため、どのような家にしたいのかも千差万別です。
建売住宅は一部のみオーナーが選べる部分もあるのですが、やはり一から作る家に比べると自由度は下がります。
よりユニークでオリジナリティ溢れる家を作りたい場合は、建売住宅では難しい点も多くなるでしょう。
特に個性を引き出せるような家を作りたいのなら、建売住宅は不向きです。
建売住宅のデメリット:似たような見た目の家になる
建売住宅の多くは建築業者が一定の土地を開発し、そこに建てた建物を販売するというスタイルが一般的です。
そのため、どうしても似たような見た目の家になってしまいます。
景観が一定に保たれるため、町全体としては見栄えが良いものの、ほかの人と似通った家になってしまうことは否めません。
せっかく夢のマイホームを持つというのに、他人と同じような家では満足できない方も多いでしょう。
何より自分だけの家という認識が持てないのは、愛着が生まれない要因にもなってしまいます。
いくら物件を直接見て決めたとしても、いずれは「もっと違う家にしたかった」という感情も生まれるかもしれません。
建売住宅のデメリット:市街地から離れた郊外が多い
建売住宅は市街地から離れた郊外で販売されていることが多いです。
そもそも市街地には大型のマンションやアパートが経っており、大規模な開発ができない場合もあるでしょう。
建売住宅は土地を開発して建てた建物を販売する形式なので、当然ながら都心からは離れていることがほとんどです。
そのため、自家用車が必須となる物件もあります。
さらにはコンビニやスーパー、病院に学校などの公共施設が少ない場合もあります。
当然、それらは生活の基盤ともなる要素なので、生活自体が不便になることも否めません。
より便利な生活を望むのなら、都心に家を建てた方が各段に便利な暮らしができます。
それらの要素も天秤にかけて判断する必要があります。
まとめ
注文住宅も建売住宅もどちらが良くてどちらが悪いとは言えません。
むしろ、それぞれにメリット・デメリットがあります。
夢のマイホームを選ぶ際には、それらの要素を頭に入れて考えることが重要です。
今後の人生をも左右することになるため、注文住宅のメリット・デメリットと建売住宅のメリット・デメリットをそれぞれ頭に入れておきましょう。
どちらも一長一短なので、より理想のライフスタイルに近い家を選ぶことが大切です。