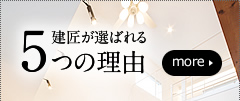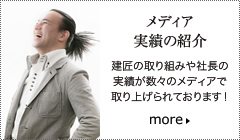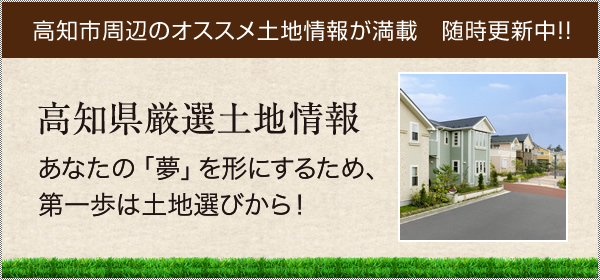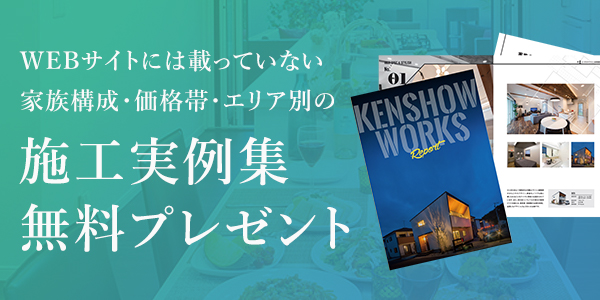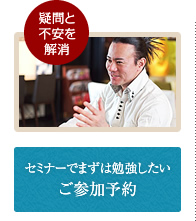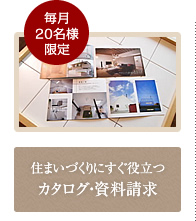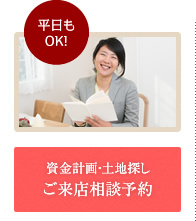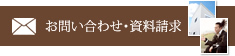この記事では、注文住宅で使われる窓の種類について解説していきます。
注文住宅は、窓の選び方によって家屋内と外観の印象が大きく変わります。
リビングやキッチン、寝室といった場所は、換気や採光などのポイントを押さえて窓を選びましょう。
この記事では、注文住宅を建てる際に押さえておきたい窓の種類と、選び方について解説します。
これから注文住宅を建てる予定がある人は、ぜひ最後までお読みください。
【この記事でわかること】
窓の種類と各間取りにおける選び方 窓を選ぶ際の注意点注文住宅で一般的に使われる窓の種類8選
この章では注文住宅で一般的に使用される窓の種類と特徴について解説します。
すべり出し窓 上げ下げ窓 掃き出し窓 FIX窓 引き違い窓 スリット窓 天窓(トップライト) 出窓
窓選びは、建てた家での日常生活に直結するため、ポイントをしっかり押さえましょう。
すべり出し窓
すべり出し窓は、住宅に多く使われる窓で、取手を押し出すか引くことで開閉できる窓です。
横に開くタイプもあれば縦に開くスクエアタイプもあるため、多くの種類の中から家に合った窓を選べます。
特に縦すべり出し窓は、窓の正面以外の風を取り込むことに適しているため、家の通気性が格段に向上します。
すき間も少ないので、気密性が高い点でも優れているといえるでしょう。
上げ下げ窓
上げ下げ窓は、窓が上下に入れ違いとなっていて、下側から上に窓を持ち上げて開ける窓です。
シンプルなデザインのため、頻繁に開閉しない窓によく使われるタイプだといえるでしょう。
掃き出し窓
掃き出し窓は、リビングなどに設置される、サイズが床から天井まである窓です。
床のホコリや汚れを庭に向けて掃き出すことから名づけられており、人の出入りや頻繁に換気する場所に設置されることが多く見られます。
FIX窓
FIX窓とは、開閉しない窓のことです。FIXとは「固定する」ことを表します。
天井窓や吹き抜けの上部にある窓に使われることが多く、採光するための窓として使われます。
引き違い窓
引き違い窓は、居室からベランダへの出入口によく使われます。
掃き出し窓と使われ方は似ていますが、主にリビング以外の居室に使われる窓が「引き違い窓」と呼ばれます。
スリット窓
スリット窓は、細長く開閉できないタイプの窓です。
防犯性とデザイン性が高いため、玄関やリビングに設置することが多いといえるでしょう。
天窓(トップライト)
天窓は、FIX窓を天井に設置した場合に呼ばれることの多い呼び名です。
ただし、採光と換気の両方をこなすために開閉タイプとするケースもあります。
出窓
出窓は、部屋側がカウンターになっており、外側に「出っ張っている」窓です。
カウンター部分が小物の置き場になるためデザイン性が高く、収納箇所が増える効果もあります。
窓自体は開閉しないタイプも開閉タイプも採用でき、自身に合ったタイプを選べます。
【間取り別】注文住宅の窓の選び方
この章では、注文住宅を建てる際に、家屋内の場所に応じた窓の選び方について解説します。
階段・廊下 リビング・ダイニング キッチン 寝室 浴室 子供部屋
窓はデザインで選ぶことも重要ですが、間取りに適した選択をすることで、より効果的に窓を使えます。
そのため、この章で解説する使用方法を押さえておきましょう。
階段・廊下
階段や廊下には、少し高い位置に設置するFIX窓やスリット窓がおすすめです。
なぜなら、階段や廊下は外部からの目線にさらされないようにしつつも、採光できる窓を選択する必要があるからです。
リビング・ダイニング
リビングとダイニングは、掃き出し窓や開閉タイプのすべり出し窓がおすすめです。
なぜなら、リビングとダイニング採光に加え換気しやすい窓を選ぶことが重要であるからです。
掃き出し窓だけではなく、開閉タイプのすべり出し窓を複数の個所に設置して、風の通り道を確保しましょう。
キッチン
キッチンには、横に長いFIX窓や天窓がおすすめです。
なぜなら、北側に設置する家が多くて暗くなりがちであるからです。
横に長いFIX窓や天窓を設置し自然光が常に入る設計にしましょう。
寝室
寝室には、引き違い窓とすべり出し窓が良いでしょう。広さに余裕があれば出窓もおすすめです。
寝室は引き違い窓とすべり出し窓採光と換気が重要となる部屋です。
そのため、引き違い窓とすべり出し窓を風が通るように設置し、広さに余裕があれば出窓を設置することで広い空間を演出できます。
浴室
浴室には、上げ下げ窓を設置しましょう。
浴室は、一般的に一箇所しか設置できないうえに、とにかく早く換気できる窓と防犯性に優れた窓を設置することが重要です。
そのため、換気しやすさと防犯性の両方に優れている上げ下げ窓が良いでしょう。
子供部屋
子供部屋には、開閉しない天窓と引き違い窓が良いでしょう。
子供部屋にはなるべく自然光が多く入り、換気しやすい間取りを設計したいという人は多くいます。
天窓と引き違い窓はその両方を兼ね備えています。
また、寝室と同じく出窓を設置すると、収納スペースが増え、部屋を広くすることが可能です。
注文住宅の窓で失敗しないコツ
注文住宅を建てる際には窓の選択が重要なため、選択するうえでの注意点を押さえておかなければなりません。
そこで、この章では注文住宅の窓で失敗しないコツについて解説します。
外観とのバランスを意識する 間取り図では見えない採光や通風も考慮する 隣地の窓や換気扇の位置も把握しておく 家具や電化製品などの配置を考慮する 防犯面を考慮する
順番に確認していきます。
外観とのバランスを意識する
家の採光と換気に重点を置くことは重要です。
ただし、導入した結果イメージした外観にならなかったという失敗事例もあります。
特に、出窓やスリット窓は外観に大きな影響を与えるため注意が必要です。
間取り図では見えない採光や通風も考慮する
間取り図には、光や風の通り道が反映されていません。
実際の自然光の入り方や風通しは、設計士に確認する必要があります。
そのため、自分が気に入った窓だけを選定するのではなく、導入後の採光と風の通り道も考慮して検討しましょう。
隣地の窓や換気扇の位置も把握しておく
図面上では全てイメージ通りだとしても、建築予定地の周辺状況によっては計算通りの採光と換気にならないこともあります。
特に、隣地の窓や換気扇、室外機などが干渉する場合、折角設置した窓が開けられないという事態にもなりかねません。
そのような事態を防止するためにも、建築予定地の周辺環境は必ずチェックしましょう。
家具や電化製品などの配置を考慮する
窓を選ぶ前に、家具や電化製品などの配置を決定しておくのがポイントです。
なぜなら、家具の位置によって採光や換気に大きく影響が出るからです。
イメージ通りの空間にするためにも、家具や電化製品の配置に注意する必要があります。
防犯面を考慮する
窓の数が増えるほど、光は入りやすくなり換気しやすくなりますが、防犯性を下げてしまいます。
そのため、全ての窓を開閉するのではなくFIX窓を選択したり、高所に天窓を設置したりなどの工夫が必要です。
注文住宅における窓の開け方をシミュレーション
この章では、注文住宅における窓の開け方について、7月〜9月の7時〜23時の間で検証したシミュレーション結果を解説します。
どのタイミングで窓を開けるべきかをポイント解説するため、住んだあとの参考にしてください。
なお、開けないと決めた時期は窓を閉め、エアコンの使用をおすすめします。
7時~11時
11時~19時
19時~23時
7月
下旬以外は開ける
上旬のみ開ける
下旬以外は開ける
8月
下旬のみ開ける
開けない
上~下旬全て開ける
9月
上~下旬全て開ける
※参考: 窓の開け方提案シート|DFG×LIXIL
上記の表からもわかる通り、猛暑となる7月下旬〜8月はなるべくエアコンを使い、気温が低い時間帯に窓を開けると効果的です。
ただし、昨今は早朝でも30度を超えることもあるため、気温を確認しながら窓を開閉しましょう。
注文住宅の窓は種類ごとの特徴を把握しよう
注文住宅は、窓の選択で採光性や風通しが決まります。
そのため、この記事で解説した窓の特徴や使用方法の把握が重要です。
建匠では、エリアに合わせた窓を提案しており、住んだあとに快適な住環境となる家を提供しています。
「採光や換気で後悔したくない」という方は、ぜひ建匠までお問い合わせください。
来店予約お申込み|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
この記事では、育休中に住宅ローンを組めるのかを解説していきます。
家づくりを検討している最中に育児休暇を取るケースは増えています。
世帯主となる男性が育児休暇を取得することも珍しいことではなくなりました。
厚生労働省が公開しているデータによると、男性の育児休暇の取得率は2012年頃から年々増加しています。
このことからも、育休中に住宅ローンを組めるかは、ライフプランの観点からも非常に重要だといえるでしょう。
そこで、この記事では育休中に住宅ローンを組むためのポイントについても解説します。
※参考: 図表1-8-1 育児休業取得率の推移|厚生労働省
【この記事でわかること】
育休中に住宅ローンを組めるかどうか 育休中に住宅ローンを組む際の評価方法 育休中に住宅ローンを組む際のポイントと注意点育休中でも住宅ローンは組める?
結論からいうと、育休中でも住宅ローンを組めます。
なぜなら、育児休暇は復職することが多いと金融機関側に考えられるからです。
一方、育休と同じように会社から給料をもらいながら休職する形態として「病気休暇(傷病休暇)」があります。
しかし、病気休暇中に住宅ローンを組むのは難しいとされています。
なぜなら、病気休暇(傷病休暇)の場合は復職しないケースが多く、高リスクの融資だと金融機関に判断されるからです。
育児休暇の場合は復職する可能性が高いと判断されるために住宅ローンが組めることが多いといえます。
ただし、全ての金融機関で融資可能というわけではないため、注意しましょう。
育休中における住宅ローン審査のポイント
この章では、育休中に住宅ローン審査を受ける際のポイントを解説します。
組めるかどうかは金融機関によって決まる 育休や産休が審査でプラスになることはない 団体信用生命保険(団信)の審査に落ちるケースがある
育休は通常の勤務形態とは異なるため、金融機関の審査も通常とは別の基準で行われます。
そのため、育休を取得する前にポイントを把握しましょう。
組めるかどうかは金融機関によって決まる
育休中でも住宅ローンを組めるかは、金融機関によって決まります。
そのため、育休中に住宅ローンを組むためには、対応してくれる金融機関を選択する必要があります。
不動産会社経由で育休中の住宅ローンを取り扱っている金融機関を調べてもらい、条件の良い金融機関を選定しましょう。
育休中に住宅ローン審査を受けられる代表的な金融機関は、以下の通りです。
金融機関
特徴
ろうきん
審査は厳しいが可能
三井住友銀行
復職後の年収によっては可能
フラット35
復職前提であれば可能
みずほ銀行
ペアローンであれば可能
住信SBIネット
ペアローンであれば可能
上記の表から、住宅ローンを組むためには復職が前提の金融機関もあれば、配偶者がいることが条件の金融機関もあることがわかります。
自分の状況を踏まえたうえで、どの金融機関で住宅ローンを組むのが良いか判断しましょう。
育休や産休が審査でプラスになることはない
住宅ローンの審査において、育休や産休がプラスになることはありません。
なぜなら、育休中や産休中は年収が下がるからです。
育休中の住宅ローンを取り扱っている金融機関は、休職前と復職後の年収をベースに審査しますが、通常よりも厳しく審査することが多いといわれています。
したがって、復職後も同じように働ける場合であっても審査は厳しくなることを理解しましょう。
団体信用生命保険(団信)の審査に落ちるケースがある
育休前は健康であっても育休中に体調を崩し、団信が通らないというケースは多く見られます。
団信は、住宅ローンの債務者が死亡もしくは重度障害状態になった際に、住宅ローン残債の支払いが免除される保険契約です。
ほとんどの金融機関が団信に加入することを融資条件としています。
ただし、団信に加入するためには健康であることが前提です。
そのため、育休中に何らかの病気や体調不良になった場合は住宅ローン本審査が通らなくなり、住宅ローンが借りられなくなることもあるでしょう。
このように、育休中の体調変化は団信の審査や住宅ローンの借入に大きく影響することがあります。
育休中の年収額はどのように評価されるのか
この章では、育休中の年収額がどのように評価されるのかを解説します。
金融機関は、「継続した安定収入」と「職場復帰できるかどうか」という2点を重点的に評価して、育休中の年収額を判断します。
育休中は年収が下がりがちな時期ですが、金融機関は下がった年収で評価するわけではありません。
まず、自営業や会社員を問わず、年収がある程度安定していて、今後も収入が継続することが金融機関にとって大きなプラス評価となります。
また、そういった労働環境に復帰できるかどうかも重要視されます。
そのため、育休中に住宅ローンを検討して有利な条件で融資を受けるためには、「継続して安定した収入がある」ことと「職場復帰する」ことを担当者に伝えましょう。
育休中に夫婦で住宅ローンを組む方法
この章では育休中に夫婦で住宅ローンを組む方法について解説します。
共働き世帯であれば、育休中で下がった年収を補填したあとの世帯年収を金融機関に審査してもらうことも可能です。
そのため、共働き世帯の人はこの章で解説する3つの方法を把握して、最適な選択をしましょう。
ペアローン 連帯債務(収入合算) 連帯保証
順番に解説していきます。
ペアローン
ペアローンを活用すれば、育休中でも住宅ローンを組めるでしょう。
ペアローンは1つの不動産に対して2人で融資を受ける契約形態ですが、それぞれが審査されて契約を締結します。
お互いの契約に連帯保証で参加することになるため、厳しい審査基準となります。
しかし、育休中であっても返済を肩代わりできる点が特徴です。
連帯債務(収入合算)
連帯債務を活用しても、育休中に住宅ローンを組めるでしょう。
連帯債務もペアローンと同じように2人とも審査対象となる形態です。
ペアローンと異なる点は、契約者はどちらか1人だけである点です。
ペアローンほど審査は厳しくなく、安定収入があれば審査が通りやすい借入方式だといえるでしょう。
連帯保証
連帯保証人を立てると、育休中に住宅ローンを組みやすくなるでしょう。
連帯保証契約では契約者が1人で、どちらか一方が連帯保証人になります。
しかし、主債務者が問題なく支払いをしている間は、単体契約と変わりありません。
そのため、育休取得者が連帯保証人になることで審査を通すケースが多くあります。
育休中に優遇を受けられる住宅ローンもある
育休中の住宅ローン審査は厳しくなる傾向がある一方で、優遇を受けられる金融機関もあります。
優遇の例としては、主に3つが挙げられます。
1つ目は、申請すれば産後1年間、適用金利を0.2%下げてくれるものです。
契約者本人の育休だけではなく、契約者の妻が育休に入った場合にも適応される金融機関があります。
2つ目の優遇は、産休・育休中は返済元金を最長2年間据え置くものです。
3つ目の優遇は、子育て中は手数料を無料にしてくれるものです。
このように、育休中の住宅ローン利用に手厚い金融機関もあるため、不動産会社から紹介してもらいましょう。
育休中の住宅ローンに関するよくある質問
この章では育休中の住宅ローンに関するよくある質問を解説します。
育休中であることを隠すと住宅ローン審査でバレる? 育休中の場合に住宅ローン審査時の必要書類は変わる? 育休中に住宅ローン審査に落ちたらどうすればいい?
順番に回答していきます。
育休中であることを隠すと住宅ローン審査でバレる?
育休中であることを隠し切ることは、不可能に近いといえます。
なぜなら、本審査の時点で提出する住民票に産まれたばかりの子供が明記されていると、金融機関が育休を疑うからです。
その場合、金融機関は会社に在籍と勤怠状況を確認するため、育休中であることが発覚するでしょう。
このように、育休中であることを隠すことは不可能に近いため、おすすめできません。
育休中の場合に住宅ローン審査時の必要書類は変わる?
育休中は、通常の書類に追加で「見込年収証明書」や「育休証明書」といった書類を用意しなければなりません。
後で「用意していなかった」とならないためにも、事前にしっかり準備しておきましょう。
育休中に住宅ローン審査に落ちたらどうすればいい?
育休中に住宅ローン審査に落ちた場合は、ほかの金融機関に相談しましょう。
育休中であることが理由で、住宅ローン審査に落ちることは珍しくありません。
ほかの金融機関に相談しても審査に落ちてしまうケースもありますが、審査に通る可能性を全て検証することが重要です。
育休中の住宅ローン審査は復職後を考慮しよう
育休中に住宅ローンを組めるかどうかは、復職後に安定収入を確保できるかがポイントです。
そのため、まずは家づくりにおけるライフプランを設計しましょう。
どのタイミングで復職して年収がどのように推移するのかを十分に想定することが重要です。
建匠ではお客様に合ったライフプランを提案して金融機関を紹介しています。
育休中の住宅ローンでお悩みの方は、ぜひ建匠までお問い合わせください。
来店予約お申込み|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
この記事では、注文住宅において起こりうるトラブルの事例を解説していきます。
注文住宅は、土地を買って家を契約し、建築が完了してはじめてマイホームとして暮らすことが可能です。
入居までには多くのステップがあるため、注文住宅にはトラブルが起きやすいといえます。
そのため、事前にトラブルの内容と回避の方法を知ることは非常に重要です。
この記事では、起こりうるトラブルだけではなく回避方法、相談先などもあわせて解説します。
これから注文住宅の建築を検討される人は、ぜひ最後までお付き合いください。
【この記事でわかること】
注文住宅のトラブル事例 注文住宅のトラブルを回避する方法 注文住宅のトラブル相談先注文住宅で多いトラブル事例
この章では注文住宅でよくあるトラブル事例を解説します。
工期に遅れが生じた 施工ミスや設備の不具合が生じた 仕上がりがイメージと異なっていた 着工後に近隣トラブルが発生した
事前にトラブルの内容を確認し、対策すれば未然に防止できる可能性が高くなるため、この章で解説するポイントを押さえておきましょう。
工期に遅れが生じた
海外からの資材搬入遅れや、新型コロナウイルス蔓延による職人不足といった影響を受け、工期遅延が発生する例があります。
注文住宅は、設計完了してから建材発注するため、計画通り進められるかは社会情勢次第です。
政治的な理由により建材が高騰する、「ウッドショック」や「アイアンショック」といった予測不可能なトラブルが発生し、工期が大幅に遅れることもあります。
施工ミスや設備の不具合が生じた
建築を進める際に、施工ミスや設備の初期不良といったトラブルもゼロではありません。
したがって、こうしたトラブルを回避するためにも、完成後に物件をチェックし、気になる点は細かく担当者に伝えましょう。
仕上がりがイメージと異なっていた
設計時に決めたデザインが発注の段階でうまく伝達されず、仕上がりがイメージと異なってしまうトラブルがあります。
このトラブルは担当者のミスだけではなく、オーナーがそもそも認識を誤っているケースもあります。
イメージと異なる仕上がりになっていた場合は、設計打合せの資料を確認し、当時を振り返りながら確認することが重要です。
着工後に近隣トラブルが発生した
建物の着工後に、近隣トラブルが発生してしまうこともよく見られます。
近隣住民から騒音や振動、臭気に関するクレームを受けるケースです。
多くの場合で建築会社に連絡がいきますが、大きなトラブルになった場合には、建築後に住民からオーナーにクレームが届くこともあります。
このような事態を避けるためにも、着工前には近隣住民に挨拶しましょう。
注文住宅はお金によるトラブル事例も多い
注文住宅のトラブルは建築時だけでなく、お金に関するトラブルも多くあります。
値引き交渉でトラブルが生じた 現金払いの諸費用を把握していなかった 追加工事によって見積がより高額になった
不動産は家が完成し、確定申告した時点でようやく「総費用」が判明します。
そのため、あとから想定外のお金がかかったり、価格を抑えたばかりに思わぬトラブルが発生したりするケースがあるため注意が必要です。
値引き交渉でトラブルが生じた
むやみに値引き交渉すると、トラブルが生じる場合もあります。
値引き交渉は、初期費用を抑える上でも重要なポイントです。
ただし、値引きによってリスクが生じるケースもゼロではありません。
土地の価格交渉の場合、ほかの購入客から満額の申し込みが提示され、自分の契約直前に白紙となるリスクもあります。
このように、値引き交渉はリスクも把握しておきましょう。
最も重要なことは、値引き交渉を前提に家づくりを進めるのではなく、資金計画をしっかりと立てて余裕を持つことです。
現金払いの諸費用を把握していなかった
現金払いの諸費用を把握していないことも、トラブルにつながるでしょう。
注文住宅を建てる際に、現金で支払う諸費用はいくつかあります。
代表的な項目として「手付金」と「印紙代」が挙げられます。
手付金は、不動産売買契約時に売主もしくは建築会社に支払うもので、50万円〜100万円が一般的です。
また、印紙代は売買代金と請負金額によって変わります。
多くの金融機関は、ATMの引き落としが1日上限50万円となっているため、引き落としのトラブルを起こさないよう事前に確認しましょう。
なお、印紙代の目安は、以下の一覧を参考にしてください。
不動産売買契約金額、請負金額
印紙代
100万円を超え 200万円以下
200円
200万円を超え 300万円以下
500円
300万円を超え 500万円以下
1,000円
500万円を超え1千万円以下
5,000円
1千万円を超え 5千万円以下
1万円
5千万円を超え 1億円以下
3万円
1億円を超え 5億円以下
6万円
5億円を超え 10億円以下
16万円
10億円を超え 50億円以下
32万円
50億円を超える
48万円
※参考: 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置|国税庁
追加工事によって見積がより高額になった
注文住宅は1箇所だけ変更したい場合でも、ほかの施工箇所も変更しなければならないケースがあります。
したがって、追加項目だけの金額だけを考えていると大きな増額が発生するおそれもあるので注意しましょう。
注文住宅のトラブルを回避する方法
ここまで、注文住宅でよく起きるトラブル事例を紹介しました。
トラブルを回避する方法を知っておくと、事前に対策ができます。
この章では、注文住宅のトラブルを回避する方法について解説します。
住宅に関する最低限の知識を事前に身に付ける 信頼できる施工会社に依頼する 担当者とのコミュニケーションを怠らない 内覧時に細かくチェックする 着工前に近隣住民へ挨拶しておく
順番に見ていきましょう。
住宅に関する最低限の知識を事前に身に付ける
家づくりを検討する際は、建築会社や不動産会社に任せきりにするのではなく、住宅に関する最低限の知識は事前に身に付けておきましょう。
YouTubeやインターネット、SNSなどで住宅に関する多くの情報を入手できます。
そのため、建築会社や不動産会社のアドバイスに加え、自身で知識を習得しておくのも重要です。
信頼できる施工会社に依頼する
満足度の高い家を建てるためには、信頼できる施工会社と出会うことが重要です。
具体的には、営業の様子やスタッフの対応など、チェックするポイントはさまざまです。
したがって、実績だけに左右されるのではなく、入念にチェックしましょう。
担当者とのコミュニケーションを怠らない
要望を盛り込んだ設計図面を作るためには、担当者とコミュニケーションを取り、要望を確実に伝える必要があります。
また、発注や職人への伝達ミスの防止などにもつながるため、担当者とのコミュニケーションは非常に重要だといえます。
内覧時に細かくチェックする
完成後の内覧時は、細かくチェックしましょう。
施工イメージの相違や施工ミス、設備の初期不良は完成時に見つけることが重要です。
仮に、あとから見つけた場合は保証対象外となるケースもあり、大きなトラブルにもなりかねません。
着工前に近隣住民へ挨拶しておく
建物の着工前には近隣住民に挨拶し、工事期間などをあらかじめ伝えましょう。
前述したように、着工時に近隣住民からクレームを言われるトラブルがあります。
トラブルを未然に防ぐためには、事前に情報を伝えておくことが重要です。
注文住宅のトラブルが起きた際の相談先
事前に対策しても、トラブルが発生してしまうケースもゼロではありません。
そのため、どうしても解決できない場合には以下に挙げる相談先から、解決のアドバイスをもらうことをおすすめします。
法テラス 首都圏不動産公正取引協議会 国民生活センター(ホットライン) 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)
相談先を知っておくと安心にもつながるため、チェックしていきましょう。
法テラス
連絡先
0570-078374
最寄りの事務所
事務所所在地・連絡先|法テラス
受付相談内容
・情報提供業務
・民事法律扶助業務
・犯罪被害者支援業務
・国選弁護等関連業務
・司法過疎対策業務
法テラスは、法務省が管轄する法人となり、正式名称は「日本司法支援センター」となります。
争乱が起きた場合に「相談先」と「解決方法」が分からない事態に対して、窓口として機能することが目的です。
そのため、トラブルが起きた際には、まず法テラスに相談することをおすすめします。
首都圏不動産公正取引協議会
連絡先
03-3261-3811
最寄りの事務所
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
受付相談内容
公正競争規約の普及及び執行に関する事業
首都圏不動産公正取引協議会は、不当景品類および不当表示防止法に基づき不動産広告を監視する団体です。
不動産広告に関する苦情に対応することが目的となっており、不動産会社に直接改善を求めたり、相談者に対処可能な行政機関を紹介したりといった活動を行っています。
国民生活センター(ホットライン)
連絡先
188
最寄りの事務所
全国の消費生活センター等
受付相談内容
消費者のトラブル全般
国民生活センターは、消費者庁が運営している相談窓口で、土日・祝日でも対応可能な点が特徴です。
また、HPには多くのトラブル事例が記載されているため、連絡しなくても自己解決できる糸口を見つけられます。
このように、トラブルに巻き込まれた際の対処方法をすぐ知りたい人におすすめの相談窓口だといえるでしょう。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)
連絡先
0570-016-100
最寄りの事務所
財団紹介|(公財) 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
受付相談内容
・請負や売買等により取得した住宅
(中古を含む)に関する相談
・住宅のリフォームに関する相談
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、リフォームやマンション売却、建て替えなどの紛争を専門に取り扱っている機関です。
専門機関には、直接問い合わせできる点が大きな特徴です。
また、相談だけではなく「住宅紛争審査会」を利用することで、第三者の力を借りて紛争処理を実行することもできます。
したがって、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターは不動産トラブルの早期解決に役立つ機関といえるでしょう。
注文住宅のトラブルは周囲にも相談しよう
注文住宅の建築は人生の一大イベントのため、トラブルのない暮らしを実現させることは大前提といえます。
したがって、まずはトラブルが起きないよう事前に対策しながら進めましょう。
それでも発生したトラブルについては周囲のプロに相談することが重要です。
建匠では、注文住宅で発生するトラブルを事前に解説し、スムーズに建築できるようアドバイスしています。
また、住み始めたあとに気になる点が見つかった場合でも、納得いただけるようお客様に寄り添って相談を承ります。
注文住宅のトラブルが不安な方は、ぜひ建匠にご相談ください。
来店予約お申込み|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
不動産の購入では、物件価格以外にも費用が発生し、いくつかは取得費用として支払いが生じます。
そのため、不動産を購入する際には住宅ローンの諸費用がいくらかかるかを把握しておくことが重要です。
そこで、この記事では住宅ローンの諸費用について節約する方法も踏まえて解説します。
これから住宅ローンを組む予定の人は、ぜひ最後までお読みください。
【この記事でわかること】
住宅ローン諸費用の内訳と目安 住宅ローン諸費用の節約方法住宅ローンの諸費用とは
住宅ローンを組む際には、金融機関が手続きをする工数や登記のために司法書士へ依頼する必要があり、それらにかかる費用を諸費用と呼びます。
諸費用は不動産を購入するために必ずかかるため、物件購入価格と諸費用を資金計画に加えて考慮することがおすすめです。
この章では、物件購入価格と諸費用の目安と、支払うタイミングについて解説します。
物件の購入価格と諸費用の目安 諸費用はいつ支払う?
順番に見ていきましょう。
物件の購入価格と諸費用の目安
新築戸建てを購入する場合、一般的には物件価格の10%が諸費用です。
ただし、購入物件によってはこの割合を大きく超えるケースもあるため、注意が必要です。
したがって、購入する物件ごとに諸費用を確認し、総額を把握しましょう。
諸費用はいつ支払う?
諸費用は不動産の引き渡し時に支払います。
諸費用を含めて住宅ローンを組む場合、借入額から引き落としによって支払うため、あらかじめ資金を用意する必要はありません。
ただし、住宅ローンに組み込めない諸費用がある場合は、別途で資金を用意する必要があるため注意しましょう。
住宅ローンにかかる諸費用の内訳
この章では住宅ローンにかかる諸費用の内訳と費用の目安を解説します。
保証料 事務手数料 団体生命信用保険料 火災保険料・地震保険料 登記に関連する手数料 印紙代 仲介手数料 繰上げ返済手数料 適合証明書(フラット35の場合) 登録免許税 融資代行手数料 長期優良住宅申請費用
順番に解説します。
保証料
保証料とは、保証会社との契約によって支払う諸費用です。
費用の目安
物件購入価格×2.2%
債務者が返済できなくなった際に保証会社が支払いを肩代わりするため、多くの銀行が保証料の支払いを融資条件に取り入れています。
ただし、金融機関によっては保証料が不要となるケースもあり、金額が変わる場合もあります。
したがって、検討している金融機関に確認しましょう。
事務手数料
事務手数料は、住宅ローン借入する際に銀行がかかる工数に対して支払う手数料です。
費用の目安
1万円~3万円
保証料と同様、金融機関によって費用が変わり、0円のところもあります。
団体生命信用保険料
団体生命信用保険は、債務者に万が一のことがあった際にローン残債が免除される保険で、諸費用として発生するものの借入額に含まれるケースがほとんどです。
費用の目安
借入額に含まれ、0.1~0.3%金利を上乗せで追加可能
また、金利を上乗せすると死亡以外にも三大疾病や十二大疾病などへの保障をつけられます。
したがって、健康上の不安がある人は条件や上乗せ金利幅などを確認し、オプション追加を検討しましょう。
火災保険料・地震保険料
火災保険料と地震保険料は、初年度に諸費用として支払います。
費用の目安
30万円~50万円(3,000万円の新築を購入した初年度の場合)
上記のとおり、30万円〜50万円が相場であるものの、火災保険はどのようなプランを選択するのかで大きく費用が変わります。
したがって、代理店から提示された見積をしっかり確認し、余計なオプションがついていないかチェックしましょう。
登記に関連する手数料
所有権の移転、もしくは保存のための費用は登録免許税に該当し、司法書士へ手続きを委任する必要があります。
これらが登記に関連する手数料です。
費用の目安
1万円~5万円
費用の目安は1〜5万円程度です。
ただし、地域によっては10万円近くかかるケースがあるため注意が必要です。
印紙代
売買契約書や請負契約書の提出時に印紙税が必要となり、その際にかかる諸費用が印紙代です。
費用の目安
売買代金によって変動する(※)
※参考:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
印紙代は、売買代金によって大きく変動するため、物件価格ごとに確認する必要があります。
仲介手数料
仲介手数料は不動産会社に支払う報酬です。
ほとんどのケースでは、引渡し時に以下の金額を支払います。
費用の目安
【物件価格によって以下のように変動】
・売買代金200万円以下:5%+税
・売買代金200万円を超え400万円以下の場合:4%+2万円+税
・売買代金400万円を超える場合:3%+6万円+税
ただし、契約内容によっては不動産売買契約時の支払いとなるケースもあり、契約解除となっても支払いが発生する可能性もあります。
そのため、不動産会社に仲介手数料はいつ支払う必要があるのかを確認しましょう。
繰上げ返済手数料
繰上げ返済にかかる手数料は、各金融機関によって大きな差があります。
費用の目安
5,000円~50,000円
例えば、三菱UFJ銀行の場合、手数料はインターネットでの繰上げ返済であれば0円となり、テレビ窓口を利用する場合は5,500円、窓口であれば16,500円かかります。
また、完済する場合はテレビ窓口で22,000円、窓口で33,000円必要です。
※参考:一部繰上返済・期限前完済のお手続き(住宅ローン) | 三菱UFJ銀行
このように、繰上げ返済の依頼方法と金額によっては手数料がかかります。
適合証明書(フラット35の場合)
適合証明書とは、技術基準を満たしているかどうかを示した書類のことで、フラット35を利用する場合に必須です。
費用の目安
3万円~5万円
取得するためには建築会社へ依頼する必要があり、そのための証明取得費として上記金額がかかります。
また、適合証明書は住宅ローン減税を受ける際の必要書類であるため、フラット35を利用する人はおのずと支払いが必要になるでしょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産を売買し所有権を移転、もしくは保存する際にかかる税金です。
費用の目安(※)
【土地】評価額×2%
【建物】評価額×0.4%
【中古戸建】評価額×2%
※令和5年3月31日取得までに取得した場合
前述した司法書士への報酬に合わせて支払うのが一般的で、不動産の固定資産税評価額に応じて金額は変わります。
売主から評価書を取得すれば計算が可能なため、事前に不動産会社に費用を確認しましょう。
融資代行手数料
融資代行手数料とは、買主が銀行と行う手続きを不動産会社が代行する際に生じる手数料です。
そのため、直接金融機関と手続きをする場合は不要です。
費用の目安
3万円~5万円
長期優良住宅申請費用
長期優良住宅申請費用は、その名のとおり長期優良住宅の認定を受けるためにかかる申請費用です。
費用の目安
5万円~10万円
長期優良住宅はさまざまな優遇を受けられるため、認定を取得できる建物であれば取得しておくことをおすすめします。
住宅ローンの諸費用を節約する方法
この章では、住宅ローンの諸費用を節約する方法について解説します。
頭金を多めに用意する 保険の保障内容を見直す 複数の借入先を比較検討する 住宅ローンを電子契約にする
順番に見ていきましょう。
頭金を多めに用意する
不動産の購入費用は「借入額+頭金」で成り立っているため、頭金を多く出せば借入額を下げられます。
そして、借入額が下がれば、保証料も下がるでしょう。
保険の保障内容を見直す
団体生命信用保険や火災保険の保障内容は、リスクとのバランスが取れているかが重要です。
子どもがいない世帯であれば、保育園でのトラブル保障などは不要です。
また、生命保険などで保障している部分との重複も、チェックする必要があります。
このように、保険は保障内容の精査が必須だといえます。
複数の借入先を比較検討する
諸費用は借入先によって大きく変わるため、諸費用を節約するためには多くの金融機関をチェックしておくことが重要です。
ただし、自分で金融機関を回ると多大な労力が必要なため、不動産会社を通じた一括比較をおすすめします。
住宅ローンを電子契約にする
電子契約は印紙代がかからず工数も減るため、事務手数料も安くなります。
近年では、オンライン完結する不動産契約が増えてきたため、電子契約を利用できるかを事前に確認しましょう。
住宅ローンの諸費用に関するよくある質問
この章では、住宅ローンの諸費用に関するよくある質問について解説します。
住宅ローンの諸費用が払えないときはどうする? 住宅ローンに諸費用の組み込みは可能? 住宅ローンの手数料は値引きできる?
順番に見ていきましょう。
住宅ローンの諸費用が払えないときはどうする?
住宅ローンの諸費用を支払うための資金が準備できない場合、住宅ローンを組む金融機関に相談し、フリーローンを組みましょう。
諸費用分だけのフリーローンであれば、それほど大きな債務にならず負担も少なく済みます。
ただし、住宅ローンを組む金融機関で借りなければ、住宅ローン自体の審査が厳しくなるため注意しましょう。
住宅ローンに諸費用の組み込みは可能?
多くの住宅ローン利用者は、諸費用を住宅ローンに組み込んで利用しています。
ただし、リフォームや家財購入費用などは不可とする金融機関もあるため、借りたい金額と項目を金融機関に伝え、あらかじめ可否を把握することが重要です。
住宅ローンの手数料は値引きできる?
基本的に住宅ローンの手数料は値引きできません。
ただし、連帯保証人を立てて保証料を不要とする方法はあります。
住宅ローンの諸費用は種類を把握して安く抑えよう
住宅ローンの諸費用は種類が多く、それぞれ節約する方法があります。
したがって、最適な金額にするためにも内容を十分確認しましょう。
建匠では、お客様に合った住宅ローンの組み方を無料でアドバイスしています。
諸費用についても最適になるように、お客様に寄り添って金融機関を紹介しています。
住宅ローンの諸費用などで失敗したくない人は、ぜひ建匠までお問い合わせください。
来店予約お申込み|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
不動産を購入する際に、住宅ローンを利用する人は多くいますが、どこに相談すべきか悩んでいる人も少なくありません。
この記事では、住宅ローンの相談先や事前準備、相談する際のポイントなどについて解説します。
住宅ローンで失敗しないためにも、ぜひ最後までお読みください。
【この記事でわかること】
住宅ローンの相談先 住宅ローンを相談する際の事前準備 住宅ローンを相談する際の注意点そもそも住宅ローンを相談するタイミングは?
住宅ローンを相談するタイミングは、主に不動産購入を検討し始めたタイミングです。
不動産は、価格が高いほど設備や立地を良くできるものの、予算は有限です。
特に、住宅ローンを組む場合は、毎月の返済額がどのくらいになるのかを把握する必要があります。
したがって、不動産の購入を検討し始めたタイミングで住宅ローンを相談し、借入額と毎月の返済額のバランスを把握しましょう。
住宅ローンはどこに相談するべきか?
住宅ローンの相談先は複数あり、それぞれ特徴があります。
この章では、住宅ローンの相談先を3つ紹介します。
各金融機関の相談窓口 ファイナンシャルプランナー 不動産会社 住宅会社
順番に見ていきましょう。
各金融機関の相談窓口
金融機関の相談窓口は、大手銀行から地方銀行、労働金庫、住宅金融支援機構など数多くあります。
したがって、まずはインターネットで各金融機関の特徴を把握し、自分に合いそうな金融機関を選んで相談しましょう。
また、感染症対策の観点から実店舗に行きたくない人向けに、オンライン相談窓口を設置している金融機関もあります。
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは、ライフプランの作成だけではなく住宅にかける予算も提案してくれます。
さらに、金融機関についても詳しい情報を持っています。
また、目先の金利だけではなく将来的に得する借入れ方法もアドバイスしてくれるため、より安全に住宅ローンを借入できるでしょう。
このような理由から、ファイナンシャルプランナーから金融機関を紹介してもらう方法もおすすめです。
不動産会社
不動産を購入する多くの人が住宅ローンを利用するため、不動産会社と金融機関は提携しているケースが多くあります。
また、不動産会社からの紹介で借入れ条件が良くなる金融機関も多く存在します。
したがって、家の購入や建築を相談している不動産会社があれば、おすすめ金融機関を複数選定してもらいましょう。
住宅会社
住宅会社も金融機関との提携が多いため、住宅ローンの相談先としておすすめです。
注文住宅は建物予算と土地予算、関連する全ての諸費用をまとめた資金計画をしなければなりません。
そのため、全ての費用を把握できる住宅会社に相談することで漏れがなくなり、より安心できる計画になるでしょう。
また、建匠では住宅ローンアドバイザーの有資格者が多く、お客様に合った資金計画を提案しています。
金利や金融機関の商品以外にも具体的な返済計画について無料アドバイスを実施していますので、住宅ローンの相談は建匠がおすすめです。
お問い合わせ・資料請求|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
住宅ローンを相談する前の事前準備
住宅ローンを相談する前には、事前準備が必要です。購入物件が決まっている場合と決まっていない場合では事前準備の内容が変わります。
そこで、この章では以下の2つの場合について事前準備の内容を解説します。
購入物件が決まっている場合 購入物件が決まっていない場合
順番に見ていきましょう。
購入物件が決まっている場合
購入物件が決まっている場合、購入する前提で住宅ローンについて相談しましょう。
住宅ローンの審査は「この人にいくら融資できるか」ではなく、「この資金計画に対していくら融資できるのか」を見られるというのが正しい解釈です。
また、住宅ローンは以下のステップを踏みます。
事前審査 本審査 銀行との契約 融資実行
事前審査では、購入する物件の資料や資金計画表、源泉徴収票、身分証明証などが必要です。
したがって、購入物件が決まっている場合は事前審査の段階で購入物件の資金計画表を提出し、借入れ条件の回答を得ましょう。
購入物件が決まっていない場合
購入物件が決まっていない場合、事前審査用の物件を用意して審査を受けましょう。
購入物件が決まっていない段階であっても、事前審査しておけば借入の可否と金利、融資条件を事前に確認できます。
したがって、具体的な資金計画をベースとした不動産探しが実現できるでしょう。ただし、購入物件が決まった段階で、再び事前審査が必要なため注意が必要です。
住宅ローンを相談するポイント
住宅ローンを相談する際のポイントは、申請する情報が後出しにならないように事前準備することです。
金融機関が住宅ローンの相談を受ける場合、主に以下を注視します。
借入予定額 年収 勤続年数 年齢 他に借入があるかどうかなど
住宅ローンを相談する場合は、上記のような情報が後出しにならないように事前準備が必要です。
また、住宅ローン審査以外の相談をする際には、尋ねたい内容を整理しましょう。
そうすることで、金融機関からも明確な回答を得られ、有意義な相談になるといえます。
相談せずに自分で住宅ローンを組むことはできるのか
金融機関に直接出向き、相談していなくても住宅ローンは組めます。ただし、損をするケースは多いため注意が必要です。
前述の通り、不動産会社は金融機関と提携しているケースが多く、不動産会社を経由して相談すると融資条件が良くなる場合もあります。
そのため、気になる金融機関があれば不動産会社に相談し、不動産会社経由での審査をおすすめします。
住宅ローンの相談に関するよくある質問
この章では住宅ローンの相談に関するよくある質問を紹介します。
住宅ローンの相談窓口は無料? 住宅ローンの相談窓口は土日も可能? 住宅ローンは相談から契約まで来店不要でも問題ない?
順番に回答していきます。
住宅ローンの相談窓口は無料?
住宅ローンの相談窓口は、どの金融機関であっても無料です。
そのため、なるべく多くの金融機関に相談し比較検討しましょう。
住宅ローンの相談窓口は土日も可能?
金融機関によっては土日でも相談窓口を受け付けているところもあり、21時以降の対応が可能なところもあります。
また、事前審査や本審査を自宅で行える金融機関もあるため、予定が合うタイミングで相談しましょう。
住宅ローンは相談から契約まで来店不要でも問題ない?
住宅ローンの相談をオンラインで実施している金融機関も多く、来店せずに必要な情報を得られます。
また、ネット銀行であれば相談から融資実行まで、全てオンラインと郵送で完結可能です。
したがって、忙しくて来店できない人や感染症対策として来店したくない人にとっても、住宅ローンを組みやすい環境が整っているといえるでしょう。
住宅ローンを相談する際は内容を明確にしよう
住宅ローンは、相談する内容を明確にして事前準備しておけば、知りたい情報をスムーズに得られるでしょう。
また、不動産会社を経由すれば住宅ローンの借入先を一度に検討でき、有利な条件の融資を受けられます。
したがって、住宅ローンの相談は事前準備と検討する数が重要といえるでしょう。
建匠は、高知県と兵庫県で注文住宅に関する最適なプランなどを提案しており、多くの銀行とも提携しています。
したがって、業務提携により実現された「建匠だけのお得な金利プラン」をご提案可能です。
お客様のライフプランに合った資金計画も提案しているため、住宅ローンの相談はぜひ建匠までお問い合わせください。
来店予約お申込み|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店