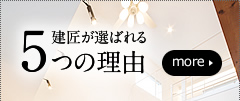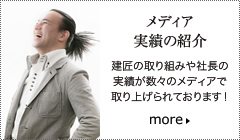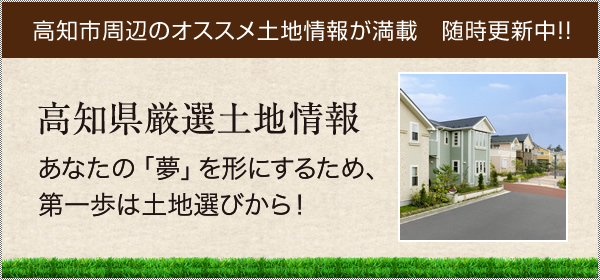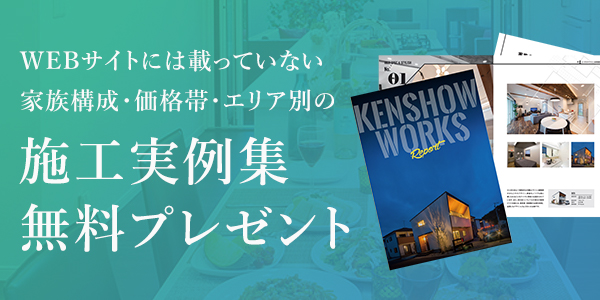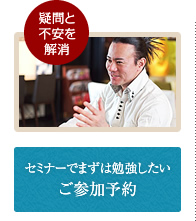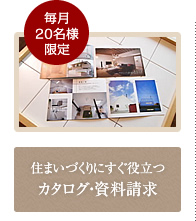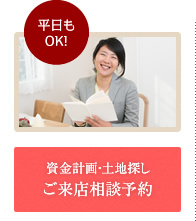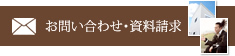この記事では、高性能住宅の基礎知識などを解説します。
高性能住宅は、気密性・断熱性が高く1年を通して快適に暮らせる家です。
耐震性や耐久性にも優れているので、長期間にわたって安心・安全に住み続けられます。
実際にマイホームを建築する前に高性能住宅について知っておけば、より快適で住みやすい家を実現できます。
また、高性能住宅は補助金をもらえる場合があるため、マイホームの選択肢の1つとして捉えることもおすすめです。
本記事では、高性能住宅のメリット・デメリットや補助金制度を解説します。これから家づくりを検討している人は、ぜひ本記事を最後までお読みください。
【この記事でわかること】
高性能住宅とは? 高性能住宅に住むメリット 高性能住宅に住むデメリット 高性能住宅の補助金・減税制度高性能住宅とは?
高性能住宅とは、気密性や断熱性、耐久性や耐震性などの快適に暮らすための性能に優れた家を指します。
気密性 断熱性 耐久性 耐震性
ここでは、高性能住宅を実現する上で大切な4つのポイントを解説します。
気密性
気密性とは、家の内部と外部の空気移動に伴う熱の移動を少なくする性能のことです。
住宅における気密性が高い家は隙間風などが入らない状態を指し、気密性が高いほど室温を維持しやすいといえます。
夏の熱い空気や冬の冷気が入りにくく快適に暮らせます。
花粉やPM2.5などの汚染物質が家の内部に侵入するのを防ぎ、健康面に良い点もメリットです。
断熱性
断熱性とは、外部の暑い空気や冷気を家の中に入れないよう、遮断する性能のことです。
断熱性が高い住宅ならば、夏は涼しく冬は暖かく過ごせます。
壁の内部に性能が高い断熱材を入れたり、断熱性能が高い窓を設置したりすると、家の内部と外部で移動する熱の量が少なくなり、室温を一定に維持できます。
耐久性
耐久性の高い住宅ならば長く住み続けられるため、長い目で見るとお得だといえます。
一般的な木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、質の良い建材でしっかりした工法で建てられた住宅では、30年以上経っても暮らせます。
長期にわたって良好な状態で使用できる『長期優良住宅』ならば長く快適に暮らせるだけでなく、補助金を受け取れるため税金面でもメリットがあるのが特長です。
耐震性
大きな地震が発生するおそれがある日本では、耐震性の高さも重要なポイントです。
住宅の耐震性の高さを表す"耐震等級"には、以下の3段階があります。
耐震等級1:建築基準法の基準を満たす 耐震等級2:建築基準法の1.25倍の耐震性能を持つ 耐震等級3:建築基準法の1.5倍の耐震性能を持つ
数字が大きいほど耐震性能が高く、耐震等級は3が1番高いレベルです。
※参考:新築住宅の住宅性能表示制度 住宅性能表示制度ガイド|国土交通省
高性能住宅に住むメリット
マイホームを性能が高い住宅にすることで、以下のようなメリットを実感できます。
光熱費が抑えられる ヒートショックのリスクが低い 1年を通して快適に暮らせる 災害に対する強度が高い 家が長持ちする
それぞれのメリットを解説します。
光熱費が抑えられる
高性能住宅は気密性や断熱性が高いため、家を一定の室温で維持できます。
エアコンなどを効率良く使用できるので、光熱費を抑えられる点がメリットです。
熱を逃がさない性能が高いと、少ないエネルギーで冷暖房の効果を感じられます。
なお、断熱性だけ高めても気密性が低いと、隙間から熱が外部に逃げてしまいます。
また、気密性が高くても断熱性能が低いと、壁や窓から外の気温をダイレクトに受けるため、一定の温度を保てません。
そのため、気密性・断熱性の両方を高めることを意識しましょう。
ヒートショックのリスクが低い
気密性や断熱性に優れている住宅はヒートショックのリスクが低く、小さな子供や高齢のご家族が安心して過ごせます。
冬場における入浴やトイレでも、ヒートショックの心配がありません。
ヒートショックとは、暖かい部屋と寒い部屋との温度差による急激な血圧変動が原因で、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす健康リスクのことです。
高性能住宅の室内は外の気温に左右されないため、家族全員が1年中快適に暮らせます。
高性能住宅ならば老後も安心して暮らせます。
1年を通して快適に暮らせる
高性能住宅は気密性・断熱性が高いため、家の内部を最適な室温のまま維持できます。
1年を通して快適に暮らせる点が大きなメリットです。
夏は涼しく、冬は暖かく過ごせるので、心身ともに健康的な生活を実現できます。
災害に対する強度が高い
地震が多い日本では耐震性の強さも欠かせません。高性能住宅は耐震性が高く、万が一大きな地震が発生しても、倒壊するリスクが低いといえます。
長期優良住宅として認定されている高性能住宅は耐震等級2の基準を満たしているため、安心して暮らせます。
家が長持ちする
高性能住宅は耐久性が高いため、家が長持ちする点が大きな魅力です。
品質の良い建材や耐久性の高い部材を使用しているため、家の劣化スピードが通常に比べて早くありません。
メンテナンスの手間や費用を減らせるので、コスト面でも優秀です。
高性能住宅に住むデメリット
高性能住宅には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
初期費用が高くなりがちである 熱がこもりやすい
上記2点をそれぞれ確認しましょう。
初期費用が高くなりがちである
高性能住宅は質が高い断熱材や設備、建材などを使用しているため、初期費用が高くなりやすい点がデメリットです。
一般的な住宅と比較すると、建物価格がやや高いといえます。
しかし、性能が高いため劣化が遅く、メンテナンス費用やリフォーム代を最小限に抑えられます。
長期的な視点で見ると、コスパが良くお得でしょう。
冷暖房の効率も良く電気代も抑えられるので、家計と環境に優しい住宅です。
熱がこもりやすい
高性能住宅は気密性・断熱性に優れている一方で、熱がこもりやすい点がデメリットです。
ただし、エアコンが効きやすいため、夏でも涼しく過ごせます。
風通しを良くして日差しが入らないように工夫すると快適に暮らせるので、それほど心配ありません。
高性能住宅の補助金・減税制度
政府は長期優良住宅などの省エネ住宅の普及を促進しており、高性能住宅を建てる際に利用できるさまざまな補助金・減税制度を用意しています。
主な補助金・減税制度は以下の4つです。
ZEH補助金 エネファーム設置補助金 贈与税が非課税になる限度額拡大 長期優良住宅の税金の優遇
それぞれの制度を解説します。
ZEH補助金
ZEH補助金制度は、経済産業省および環境省が実施している補助金です。
対象となる設備を導入して省エネ性能を備えた住宅を対象にしています。公募の期間は以下の通りです。
一次公募期間:2023年4月28日(金)10:00 ~ 2023年11月10日(金) 17:00締切 二次公募期間:2023年11月20日(月)10:00 ~ 2024年1月9日(火) 17:00締切
※参考:ZEH支援事業 公募情報|一般社団法人 環境共創イニシアチブ
※2023年10月現在
ZEH住宅を購入する場合は、ZEH補助金を忘れずに受け取りましょう。
エネファーム設置補助金
エネファーム設置補助金は国と地方自治体が主体となって実施しているため、大きく2つに分けられます。
国が実施しているエネファーム補助金制度は、経済産業省が行っている、『給湯省エネ事業(高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金)』です。家庭用燃料電池では、1台につき15万円が補助されます。
自治体が行っている補助金は、自治体によって補助額に違いがあります。
※参考1:令和4年度補正「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」について|経済産業省 資源エネルギー庁
※参考2:令和5年度蓄電池・燃料電池(エネファーム)補助金|つくば市
※参考3:【令和5年度】家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金|埼玉県
贈与税が非課税になる限度額拡大
親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が、2023年12月31日まで延長されました。
一般住宅の非課税枠は500万円ですが、省エネ住宅の場合は1,000万円まで限度額が拡大します。
※参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
長期優良住宅の税金の優遇
新築した戸建て住宅が長期優良住宅の場合は、以下のように税金が優遇されます。
税金の種類
優遇内容
所得税
令和4〜5年までに入居:借入限度額5,000万円
※通常の住宅は3,000万円
令和6〜7年までに入居:借入限度額4,500万円
※通常の住宅は2,000万円
登録免許税(令和6年3月31日までの取得が対象)
所有権保存登記:税率0.1%※一般住宅特例の場合は0.15%
所有権移転登記:税率0.2%※一般住宅特例の場合は0.3%
不動産取得税
控除額1,300万円※一般住宅の場合は1,200万円
固定資産税(令和6年3月31日までの新築が対象)
減額措置として5年間1/2※一般住宅特例の場合は3年間1/2
※2023年10月現在
※参考:認定長期優良住宅に対する税の特例(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)|国土交通省
適用を受けるための要件や必要書類も確認しましょう。
高性能住宅を建てるなら建匠の『極断熱の家』がおすすめ
1年中過ごしやすく経済的・健康的に暮らせる家を建てたい人には、建匠の『極断熱の家』がおすすめです。
『極断熱の家』の断熱性能は北海道基準で、冬でも暖かく過ごせます。
断熱性能が非常に高いため、"夏は涼しく冬は暖かい"家を実現できます。ヒートショックの心配がないため、老後になっても安心して暮らせる住宅です。
冷暖房コストを抑えられるので、家計に優しい点もメリットです。
『極断熱の家』については、以下のページで詳しく説明しています。気になる人はぜひこちらもご覧ください。
極断熱の家|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
高性能住宅に関するよくある質問
ここでは、高性能住宅に関するよくある質問に回答します。
高性能住宅が向いている人の特徴は? 補助金制度は併用できる?
上記2つの質問を順に見ていきましょう。
高性能住宅が向いている人の特徴は?
初期費用や一定の期間を要してでも快適な住宅に住みたい人には、高性能住宅が向いています。
一般的な住宅より多少費用がかかりますが、住宅が長持ちして安全に生活できるため、長期的な視野で見るとお得だといえます。電気代を抑えられる点もメリットです。
補助金制度は併用できる?
国土交通省・経済産業省などの国が実施している制度は、原則併用できません。
金額が大きいなど、条件の良いほうを選ぶことをおすすめします。
地方公共団体の補助制度については、国費が充てられている制度以外が併用できます。
※参考:住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業【経済産業省】及び断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省 CO2加速化支援事業【環境省】の内容について|経済産業省
高性能住宅はメリット・デメリットを比較して検討しよう
高性能住宅には、暖かく快適に過ごせる、耐久性や耐震性が高いなどのメリットがあります。
一方で、夏は熱がこもりやすい、初期費用が高いなどのデメリットがある点も事実です。
高性能住宅を選ぶときは、メリット・デメリットを比較し自分に合っているかを判断しましょう。
また、高性能住宅を建てる際に活用できる補助金も確認することをおすすめします。
補助金を上手に活用できれば、長く快適に暮らせる家がお得に実現できるでしょう。
建匠では、高性能住宅をはじめ、家づくりに関する多くの相談を受け付けています。
建匠では1年中快適に過ごせる『極断熱の家』も提供しているため、高性能住宅を検討している人は、ぜひ一度建匠にお問い合わせください。
お問い合わせ・資料請求|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
この記事では、住宅ローン控除の減税を年末調整で実施する方法を解説します。
住宅ローン控除は、その年におけるローン残高の0.7%の金額が還付される制度です。住宅ローンで家を購入した人の金銭的な負担を軽減します。
しかし、住宅ローン控除をどのような方法で受けるのか知らない場合、必要な書類や記入方法がわからず不安に感じてしまうでしょう。
そこで本記事では、住宅ローン控除(減税)を年末調整で行う方法を、必要書類や記入例と併せて解説します。
住宅ローンの利用を検討している人は、ぜひ本記事を最後までお読みください。
【この記事でわかること】
住宅ローン控除(減税)とは? 確定申告で住宅ローン控除(減税)を受ける方法 年末調整で住宅ローン控除(減税)を受ける方法 住宅借入金等特別控除申告書の書き方・記入例 年末調整で住宅ローン控除(減税)を受ける場合の注意点そもそも住宅ローン控除(減税)とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅の新築・購入・増改築などをした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除する制度です。
所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税からも税金が控除されます。
この制度の目的は、金銭的な負担を軽減して住宅確保を促進することです。
住宅ローン控除(減税)を受ける条件【新築の場合】 1年目と2年目以降での違い 2024年から住宅ローン控除(減税)が変わる
ここでは、住宅ローン控除について上記の3点から解説します。
※参考:住宅:住宅ローン減税|国土交通省
住宅ローン控除(減税)を受ける条件
新築の場合に住宅ローン控除(減税)を受けるには、以下の条件を満たしていることが必要です。
減税を受ける人がマイホームとして使用する住宅である 床面積が50㎡以上で合計所得金額が2,000万円以下 床面積が40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額が1,000万円以下
(2023年末までに建築確認を受けた新築住宅の場合)
住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住する 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用である 借入金の返済期間が10年以上※参考:住宅ローン減税制度について|国土交通省
上記の条件を満たしている場合は、住宅ローン控除の申請を検討しましょう。
最長13年間も控除を受けられるため、住宅ローンを組む際にはメリットが大きな制度といえます。
1年目と2年目以降での違い
住宅ローン控除を申請する際、1年目と2年目以降では手続き方法に違いがあります。
1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きすれば申請可能です。
1年目と2年目以降の手続き方法や必要書類は、後述します。
2024年から住宅ローン控除(減税)が変わる
2024年・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準に適合しないと原則住宅ローン減税を受けられません。
省エネ基準を満たさない新築住宅は、住宅ローン減税の対象外となります。
なお、2024年以降は、どの新築住宅でも住宅ローン減税の最大控除額(軽減される所得税・住民税の最大額)が引き下げられます。
2023年度と2024年度以降のローン残高上限額を比較した表は以下の通りです。
借入限度額とは、住宅ローン減税の対象となるローンの年末残高の上限を指しています。
【新築住宅・買取再販住宅】(控除率0.7%)※控除期間 13年間
住宅の環境性能
借入限度額
2022・2023年入居
2024・2025年入居
長期優良住宅・低炭素住宅
5,000万円
4,500万円
ZEH水準省エネ住宅
4,500万円
3,500万円
省エネ基準適合住宅
4,000万円
3,000万円
その他の住宅
3,000万円
0円
※2023年10月現在
※参考1:住宅ローン減税制度について|国土交通省
※参考2:住宅:住宅ローン減税|国土交通省
2023年までに入居する場合は、省エネ住宅でなくても借入限度額3,000万円までは控除の対象になります。
しかし、2024年以降は省エネ基準を満たした住宅でないと、控除を受けられません。
省エネ基準を満たした住宅でも借入限度額が低くなっているため、2024年以降に住宅ローンを利用する場合は減税される金額が少なくなります。
確定申告で住宅ローン控除(減税)を受ける方法
1年目に住宅ローン控除の手続きをするときには確定申告を行います。
確定申告の手順と必要書類を解説します。
確定申告の手順
確定申告は例年、2月16日から3月15日の期間内に手続きをします。
ただし、還付申告は1月から実施可能です。申告の手順は以下の流れです。
必要書類を準備する 申告書を作成する 申告書を提出する 税金を納付する・還付を受ける
最初に、『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』や『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』など、必要な書類を用意しましょう。
次に、確定申告書を作成して住所地などの所轄税務署や業務センターに郵送します。税務署窓口への持参やe-Taxを利用したパソコンからの送信も可能です。
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な際に郵便などで送付する場合は、コピーと返信用封筒を(切手貼り付け)同封して返送してもらいます。
納税には金融機関の窓口で納付するほかに、"振替納税"や"クレジットカード納付"などさまざまな方法があります。
還付金は、確定申告から1ヶ月程度経った際に、申告書に記入した金融機関の預貯金口座へ振り込まれることを把握しておきましょう。
※参考:令和 4 年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き|国税庁
確定申告での必要書類
確定申告で必要な書類は以下の通りです。
確定申告書 源泉徴収票(勤務先から入手) 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁サイト・税務署から入手) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(住宅ローンを契約した金融機関から送付) 家屋の「登記事項証明書」(法務局から入手) 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写し(購入したハウスメーカーなどから入手) 認定通知書の写し(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、ハウスメーカーなどから入手)
このように、住宅ローン控除を受けるにはさまざまな書類が必要であるため、早めに準備しておきましょう。
※参考1:No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
※参考2:会社員が住宅ローン控除を受けるための「はじめての確定申告」|フラット35
年末調整で住宅ローン控除(減税)を受ける方法
給与所得以外に収入のない会社員が2年目以降も住宅ローン控除を受ける場合は、年末調整で手続きを行います。この手続きは、年末調整の書類を勤務先に提出して行います。
ただし、個人事業主や年収2,000万円以上の会社員など、年末調整をしない人は2年目以降も確定申告が必要です。
ここからは、年末調整の手順や必要書類を解説します。
年末調整の手順
住宅ローン控除を受けた1年目の確定申告後に、税務署から『住宅借入金等特別控除申告書』が送られてきます。
この書類と金融機関から送付される『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』を、勤務先に提出します。
年末調整での必要書類
年末調整で必要な書類は、主に以下の通りです。
住宅借入金等特別控除申告書 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅借入金等特別控除申告書は、税務署から控除を受ける年の用紙がまとめて送付されます。
控除期間が13年の場合は12枚分です。紛失しないようにしっかりと保管しましょう。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、金融機関が発行する12月末時点の住宅ローン残高の証明書です。毎年10月中旬頃に送られてきます。
※参考:給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)|国税庁
住宅借入金等特別控除申告書の書き方・記入例
住宅借入金等特別控除申告書の書き方を解説します。下表は、国税庁の公式HPにある『住宅借入金等特別控除申告書』の見本です。
※出典:給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の記載例|国税庁
申告書は、以下の手順で記載していきましょう。
手順
記載する項目
詳細
1
給与の支払者の名称・申請者の氏名、住所
勤務先の名称・所在地、自分の氏名・住所などを記入 法人番号や税務署長欄は空白でも可2
①新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高
年末のローン残高を転記3
②住宅借入金等の年末残高
単独でローンを借入している場合は、①の金額を転記 連帯債務者がいる場合は、自分の負担金額と負担割合をかけた金額を記入4
③ ②と証明事項の取得対価の額又は増改築等の費用の額のいずれか少ない方の金額
②とロの欄、②とホの欄を比較して金額が少ない方を記入5
③×『居住用割合』
住宅のすべてを居住用として使用している場合は『ヘ欄』に100%と記入 ③の金額を転記6
住宅借入金等の年末残高等
④の合計金額を転記7
住宅借入金等特別控除額
⑤の金額に0.7%をかけて記入8
年間所得の見積額
源泉徴収後の金額(所得)を記入 年収ではない点に注意※2023年10月現在
※参考:給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の記載例|国税庁
控除期間13年の場合は12年分の書類があるため、必ず申告する年度の年号が記載されている用紙を使用してください。
年末調整で住宅ローン控除(減税)を受ける場合の注意点
ここでは、年末調整で住宅ローン控除(減税)を受ける場合の注意点を解説します。
年末調整し忘れたら確定申告で対応する 必要書類の取り扱いに注意する 状況によっては書類の再発行が必要になる
上記3点をそれぞれ見ていきましょう。
年末調整し忘れたら確定申告で対応する
年末調整を忘れた場合、自分自身で税務署に確定申告をしなければなりません。
年収2,000万円以下の会社員ならば会社が年末調整をしてくれるので、手間をかけずに確定申告を受けられます。
住宅ローン控除には時効があり、過去5年間までは所得税の還付を受けられます。しかし、5年を過ぎると無効になるため、注意しましょう。
必要書類の取り扱いに注意する
住宅ローンの控除を受ける際は、さまざまな書類が必要です。
住宅借入金等特別控除申告書は、初年度の確定申告後の10月頃に、管轄の税務署から残りの年数分が一括で送られます。
申告書は、紛失しないようにしっかりと保管しておきましょう。
状況によっては書類の再発行が必要になる
10月以降に繰り上げ返済や借り換えなどを行った場合は残高が変わるため、年末残高証明書の再発行が必要です。
金融機関に繰り上げ返済したことを伝えて、再発行を依頼しましょう。
住宅ローン控除(減税)の年末調整に関するよくある質問
ここでは、住宅ローン控除(減税)の年末調整に関するよくある質問に回答します。
住宅ローン控除(減税)を受けないとどうなる? 住宅ローン控除(減税)の還付金は年末調整後のいつもらえる? 住宅ローン控除の1年目に年末調整してしまったらどうすればいい?
上記3つの質問を順番に見ていきましょう。
住宅ローン控除(減税)を受けないとどうなる?
年末調整までに必要書類を提出できなかった場合、2年目以降に確定申告を行うことで控除を受けられます。
申告しなければ、自動的に税金が軽減されることはありません。5年を過ぎると時効となり、申告できずに還付を受けられないので注意が必要です。
住宅ローン控除(減税)の還付金は年末調整後のいつもらえる?
住宅ローン控除の還付金がもらえる時期は会社によって異なります。
一般的に、12月か1月の給与に還付金額分が反映されます。
住宅ローン控除の1年目に年末調整してしまったらどうすればいい?
住宅ローン控除を受けるには、1年目に自分で確定申告することが必要です。
5年以内に申告すれば控除が受けられるので、1年目の確定申告を忘れた場合はなるべく早く確定申告しましょう。
住宅ローン控除(減税)は2年目以降なら年末調整で対応できる
住宅ローン控除は、1年目は自分で確定申告が必要ですが、会社員の場合は2年目以降なら年末調整で対応できます。
必要書類を揃えて会社に提出するだけで申請できるため、便利な制度といえます。
住宅ローン控除で受け取る還付金は、年末の住宅ローン残高の0.7%程度と非常に大きい金額です。
しっかりと手続きして、漏れがないように受け取ることをおすすめします。
住宅ローン控除をはじめ、家づくりに関して不安な点がある場合は、建築を依頼するハウスメーカーや工務店などに相談すると効果的です。
多くの施工事例を持っていれば、家づくりのさまざまな相談に応じてくれるでしょう。
高知県や兵庫県で注文住宅を提供する建匠では、家づくりに関する相談を承っています。
該当の地域でマイホームの購入を検討している人は、ぜひ一度建匠にご相談ください。
お問い合わせ・資料請求|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
冬は1年で最もエアコンの使用率が高く、全国的に電気代が高くなる季節です。
2022年は、ウクライナ侵攻を機にロシア産資源の禁輸措置などがされ、燃料輸入価格が2倍前後高騰し、電気代も高騰しました。
大手電力各社は調達燃料費の高騰に抗しきれず、2023年4月頃から一斉に3〜5割程度の電気料金値上げを申請しました。
こうした状況を踏まえて、政府は2023年2月より『電気・ガス価格激変緩和対策事業』を展開し、電気・ガス料金の家計負担を抑える施策を展開してきました。
しかし、2023年9月(10月請求分)以降は補助額が半減されるおそれがあり、電気代が高くなる冬場を前に家計の負担はさらに増大するおそれが高まっています。
本記事では、冬の電気代で困っている人に向けて、電気代の上手な節約方法を紹介します。ぜひ最後までお読みください。
【この記事でわかること】
冬の月別・地域別・世帯別の電気代 冬の電気代が高くなる理由 冬の電気代を上手に節約する方法冬の電気代の相場はいくら?
ここでは、冬の電気代の相場をチェックしましょう。以下の3つのカテゴリーから冬の電気代を分析します。
なお、冬の時季は12〜2月(請求月1〜3月)とします。
月別の平均電気代 地域別の平均電気代 世帯別の平均電気代
順に見ていきましょう。
月別の平均電気代
まず、2022年度の月別電気代(全国平均)を総務省統計局のデータから見てみましょう。
<2022年度月別平均月額電気代(全国平均)>(単位:万円)
2022年
2023年
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
1.39
1.18
0.99
0.98
1.19
1.32
1.28
1.15
1.25
1.71
1.86
1.76
※2023年9月時点
※参考:家計調査|総務省統計局
上記の表から、2023年に入って電気代が1.5倍近く跳ね上がっていることがわかります。
また、2022年の同時期(1〜3月)とも比較してみましょう。
<2021年度月別平均月額電気代(全国平均)>(単位:万円)
2022年
1月
2月
3月
1.29
1.53
1.62
※2023年9月時点
※参考:家計調査|総務省統計局
1年前の冬場と比較しても、1.2倍程度高くなっていることがわかります。
燃料費が高騰したことに加えて、冬場はエアコンや電気ストーブ、ファンヒーターなどの使用頻度が高いため、ほかの季節に比べて電気代がかなり高くなっています。
地域別の平均電気代
ここでは、冬場の電気代を地域別に比較してみましょう。
<2023年1〜3月地域別電気代>
全国平均
高知県
高知市
東京都
23区
大阪府
大阪市
北海道
札幌市
愛知県
名古屋市
福岡県
福岡市
1〜3月
合計
53,168円
50,378円
44,890円
45,543円
60,280円
48,729円
37,911円
1〜3月別
平均
17,722円
16,792円
14,963円
15,181円
20,093円
16,243円
12,637円
電力会社
-
四国電力
東京電力
関西電力
北海道電力
中部電力
九州電力
6月以降値上げ幅
-
23.0%
15.3%
-
20.1%
-
-
8月以降値下げ幅
-
▲239円
▲327円
-
▲327円
▲242円
-
※2023年9月時点
※参考:家計調査|総務省統計局
地域別に2023年冬場の電気代を比較すると、調査した6エリアのなかでは札幌市が最も高く、ついで高知市、名古屋市が高くなりました。
その一方で、福岡市が最も低い結果となりました。
札幌市における冬場の電気代が高い要因は気候ですが、他の地域では各エリアの大手電力会社が設定する電気料金に左右される部分が大きくなっています。
また、高知市と札幌市においては、元々電気代が高いうえに6月以降の電気代の上げ幅も大きいので、今後もさらなる注意が必要です。
世帯別の平均電気代
ここでは、2023年1〜3月における平均電気代を世帯別に見ていきましょう。
<2023年1〜3月世帯別平均月額電気代(全国平均)>
総世帯
2人以上世帯
単身世帯
1〜3月計
43,939円
53,168円
28,019円
1〜3月別平均
14,646円
17,722円
9,339円
※2023年9月時点
※参考:家計調査|総務省統計局
2人以上の世帯における平均月額電気代は、単身世帯の2倍近くになっていることがわかります。
また、1年前の同時期(1〜3月)の世帯別平均月額電気代も見ておきましょう。
<2022年1〜3月世帯別平均月額電気代(全国平均)>
総世帯
2人以上世帯
単身世帯
1〜3月計
36,903円
44,542円
23,246円
1〜3月別平均
12,301円
14,847円
7,748円
※2023年9月時点
※参考:家計調査|総務省統計局
2023年の世帯別平均月額電気代は、前年同時期と比べて単身世帯、2人以上世帯いずれも1.2倍程度高くなっていることがわかります。
2023年9月以降(電気料金反映は10月)、電気料金値上げの緩和措置は延期される見通しですが、2024年度の冬場はさらなる値上げになるおそれが高いといえます。
冬の電気代が高くなる理由
冬の電気代が高くなる理由を解説する前に、夏と冬の電気料金を比較すると、以下の通りになります。
<夏と冬の電気料金比較(総世帯)>
3ヶ月総額電気料金
3ヶ月平均月額電気料金
冬場の電気代(2023年1〜3月)
43,939円
14,646円
夏場の電気代(2022年7〜9月)
29,291円
9,753円
※2023年9月時点
※参考:家計調査|総務省統計局
総務省統計局の調査によれば、夏場の平均月額電気料金(2023年1〜3月)は9,753円です。
一方、冬場(2023年1〜3月)は1万4,646円で、夏場の1.5倍程度になっています。
ここからは、冬場の電気代が高くなる理由を解説します。
暖房の消費電力が大きい 照明を長時間使用する
それぞれ見ていきましょう。
暖房の消費電力が大きい
冬場は室内の温度を上げるために、暖房機器の使用頻度が1年で1番多くなります。
電気機器を複数同時に利用すれば、電気代が高くなるのも無理はありません。
また、冬場にエアコンなどの消費電力が大きくなる1番の原因は、室内と外気温度の差が1年で最も大きくなるからです。
エアコンなどの暖房器具は、設定温度に達するまでの時間に最も電力を消費するので、外気温で冷やされた低い室内温度が低いほど消費電力は大きくなります。
ここで、国内各所の冬場と夏場の最高気温と最低気温を見てみましょう。
高知市
東京23区
大阪市
札幌市
名古屋市
福岡市
夏場
2023.8.1
最高気温
33.5℃
33.2℃
37.0℃
30.9℃
36.6℃
35.1℃
最低気温
26.1℃
22.2℃
28.4℃
23.7℃
27.8℃
25.9℃
気温差
7.4℃
11.0℃
8.6℃
7.2℃
8.8℃
9.2℃
冬場
2022.2.1
最高気温
13.2℃
13.1℃
10.3℃
0.7℃
8.5℃
18.8℃
最低気温
0.8℃
-0.7℃
0.6℃
-6.6℃
-1.9℃
4.3℃
気温差
12.4℃
13.8℃
10.9℃
7.3℃
10.4℃
14.5℃
※2023年9月時点
※参考:気象庁|国土交通省
上記の表からも、夏場に比べて冬場の気温差のほうが、どのエリアにおいても大きくなっていることがわかります。
札幌は気温差が1番小さくなっていますが、冬場の気温が1日を通して1℃を下回っています。
そのため、常時暖房機器を利用する必要があり、電気代は高くならざるを得ません。
その他のエリアにおいては、冬場における最高気温と最低気温の気温差が軒並み10℃を超えているので、冬場の電気使用量が夏場に比べて多くなりがちです。
照明を長時間使用する
冬場は夏に比べて日照時間が短く気温も低いため、在宅時間が長めになる傾向があります。
そのため、他の季節に比べて照明を使用する時間が長くなり、電気代が高くなる原因になります。
また、冬場は身につける肌着や衣服も多めになり、その分洗濯機や乾燥機を回す時間が多くなることも、電気代がアップする要因の1つです。
冬の電気代を上手に節約する方法
ここでは、冬の電気代を上手に節約する方法を解説します。
暖房器具の使い方を改善する 古い家電を買い替える 暖かい服装で過ごす 加湿器を使用する 断熱対策を行う
工夫次第で電気代を1〜2割程度ダウンできるため、ぜひ参考にしてください。
暖房器具の使い方を改善する
冬場の電気代のなかで、最も負担が大きい暖房器具はエアコンです。
寒冷地の北海道などでは、常時つけっぱなしにしている人は少なくありません。
エアコンの暖房費を節約したい場合には、サーキュレーターやシーリングファンの利用を検討しましょう。
エアコンによって暖められた空気は、上昇して室内上部に溜まる傾向があるため、サーキュレーターやシーリングファンで空気を循環させると部屋全体が暖かくなります。
シーリングファンは、インテリアとして部屋のアクセントにも使用できるのでおすすめです。
また、エアコンは自動運転を利用し、適温に温まったらなるべく20℃を目安に温度調節してみましょう。
古い家電を買い替える
冬場に限らず、電気代が高いと感じられる場合は古い家電を見直してみましょう。
特に、冷蔵庫やエアコン、テレビや照明器具などの大型家電は、最新の品物に買い替えると電気代を大幅に節約できる可能性があります。
10年前の家電を最新の家電に買い替えると、以下の表のような省エネ効果があります。
<10年前の家電を最新の家電に買い替えた場合の省エネ割合>
買い替えた家電アイテム
省エネ割合
冷蔵庫
約40〜47%
LED電気照明
約86%
テレビ
約42%
エアコン
約17%
※2023年9月時点
※参考:機器の買換で省エネ節約|資源エネルギー庁
初期費用は必要ですが買い替えのタイミングがマッチするのであれば、ぜひ検討してみましょう。
暖かい服装で過ごす
コストがかからずお手軽にできる節約方法の1つとして、暖かい肌着の使用や厚着で過ごす方法があります。
各種暖房機器の設定温度を下げられるので、室内でも着衣による防寒対策はおすすめです。
暖かい服装で過ごすことで室内の温度を20℃程度にキープできれば、かなりの節約効果が見込めます。
加湿器を使用する
人間の身体は、加湿されると体感温度が高くなります。
冬場はこの特質を利用して、エアコンと加湿器を効果的に併用しましょう。
加湿器を利用することで体感温度が上昇し、結果としてエアコンの温度を低く設定できます。
断熱対策を行う
自宅そのものの断熱性を新築やリフォームで上げられれば、最も効果的な省エネ対策が実行できます。
それ以外にも、すぐにできる断熱対策として以下の2つの方法があります。
断熱シート 断熱カーテン
断熱シートは、冬場の冷たい床の冷気をシャットアウトしてくれる優れものです。
アルミ蒸着フィルムと発泡ポリエチレン層で構成されており、フローリングとカーペットの間に敷くと、冬場の床の冷たさを感じることなく生活できるでしょう。
ホットカーペットと床の間に敷くとさらに効果的で、低い温度設定でも十分快適な暖かさを保てます。
また、断熱カーテンは、寒さの厳しい冬場でも室内を暖かく保ち、電気代も抑えてくれる優れものです。
熱の出入りが最も大きいのは窓周辺であり、暖まった室内の暖気が窓から放出されると、室温を一定に保てません。
断熱カーテンは、室内の暖かい空気が窓から逃げることを防ぎ、室内の保温効果を高めてエアコンや電気ストーブによる電力消費を抑えられます。
断熱カーテンを選ぶときは、なるべくカーテンレールから床までをカバーできる高さの物を選びましょう。
冷気は下に溜まりやすく、下部が空いているとそこから冷気が室内に入り込んでくるので、断熱カーテンの高さには注意してください。
冬の電気代を抑えた家づくりなら建匠
建物そのものが断熱性に優れていれば"冬は暖かく夏は涼しい"快適な住空間を手に入れられます。
冬場にエアコンの温度設定を20℃に設定した場合、断熱性に優れた住宅になると断熱性能の低い住宅に比べて、体感温度が4℃も高くなるほどの違いが生じます。
高知県でこれからマイホームを検討する人は、断熱性能に優れた極断熱の家を商品展開している建匠に相談してみてください。
建匠の『極断熱の家』は、高知県における断熱性能基準であるUA=0.87を大幅にクリアし、北海道レベルの断熱性能UA値0.46が標準仕様です。
その名の通り極めて断熱性能に優れており、冬場を暖かく過ごせるだけでなく、経済的にも光熱費を大幅に抑えられます。
断熱性能に優れた極断熱の家は、冬ばかりでなく夏も涼しいので、季節を通して快適な住空間を満喫できます。
冬の電気代を抑えられる断熱性能の高い住宅を検討している人は、ぜひお近くのモデルルームに足を運んでみてください。
極断熱の家|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
冬の電気代に関するよくある質問
ここでは、冬の電気代に関するよくある質問に回答していきます。
冬の電気代はオール電化とガス併用のどちらが高くなりやすい? 1日の電気代に占める各家電の割合はどれくらい?
それぞれ見ていきましょう。
冬の電気代はオール電化とガス併用のどちらが高くなりやすい?
オール電化とガス併用については、生活の時間帯や電気・ガスの使い方によって異なるため、一概にはどちらが高いといえません。
しかし、基本料金については、電気料金で一本化されているオール電化のほうが安くなる可能性が高いといえます。
在宅時間が夜に集中する家庭(夫婦とも会社勤めをしている家庭など)にとっては、夜間の料金を抑えられるオール電化のほうが安くなる傾向にあることを覚えておきましょう。
また、省エネによる光熱費の節約として最も効果が高い方法は、断熱性を高めエアコンの稼働台数を減らすことです。
建匠が実現する『極断熱の家』では、断熱性が非常に高く換気の効率に優れている点などから、可能な限り省エネが可能です。
あわせて、太陽光発電や蓄電池を取り入れれば、電力会社から電気を買わずに済み節約にもなります(※)。
このように、建匠では買電による負担を減らせるようなプランもご提案しておりますので、電気代の負担に不安が残る方は、高気密・高断熱を実現した建匠の家づくりをご検討ください。
※ガスの使用量と基本料金は削減不可
極断熱の家|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
1日の電気代に占める各家電の割合はどれくらい?
1日の電気代に占める各家電の割合について、以下の表を用いて紹介します。
<冬季:平成30年家庭における家電製品の1日での電力消費割合>
順位
家電製品
電力消費割合
1
エアコン等
32.7%
2
冷蔵庫
14.9%
3
給湯器
12.5%
4
照明器具
9.3%
5
炊事関係
7.9%
6
待機電力
5.5%
7
テレビ
4.2%
8
洗濯機・乾燥機
2.2%
9
パソコン
0.9%
10
温水便座
0.6%
その他
9.4%
※2023年9月時点
※参考:平成30年度電力需給対策広報調査事業|一般財団法人日本エネルギー経済研究所
上の表からも、エアコンの占める割合が群を抜いて高いことがわかります。
また、コンセントをつけっぱなしにするなどの待機電力による電力消費も少なくないので、できる限りこまめにコンセントを切りましょう。
冬の電気代を抑えながら快適な生活を送ろう
今後、世界的なエネルギー資源の減衰や国内の電気料金値上げ緩和策の打ち切りなどによって、電気料金はますます高くなるおそれがあります。
そうしたなかでも、暖房器具の使い方や生活の仕方を変え、日常的にできる断熱対策で工夫しながら冬場の電気代を抑えていきましょう。
これからマイホームを検討する人には、ぜひ断熱性能に着目した家づくりをおすすめします。
断熱性能が高い家に住むことは、「健康的に過ごせるだけでなく、光熱費も抑えられる生活を手に入れられる」ことに繋がります。
ぜひ、建匠で高断熱住宅の住まいを検討してみてください。
お問い合わせ・資料請求|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
この記事では、四季を通して外気温に左右されない快適な温熱環境を提供してくれる、全館空調システムの電気代について解説します。
日本の気候は四季があって温暖だといわれていますが、実際は夏と冬の温度差が大きく、季節によって生活環境が大きく変化します。
このことは室内においても同様です。夏と冬の室温差が10度を超える地域も多く、特に冬場の室温の低さは、健康を害する原因にもなりかねません。
ここ数年、コロナを反映して健康に対する意識が高まるなか、「四季を問わず自宅の室温を快適な室温に保ちたい」と考える人も増えています。
この記事では、全館空調の電気代をエアコンと比較しながら解説するので、全館空調の導入を検討している人はぜひ最後までお読みください。
【この記事でわかること】
全館空調システムとは? 全館空調システムの電気代が高いとされる理由 全館空調システムとエアコンの電気代比較 全館空調のメリット・デメリット 全館空調システムの電気代を抑えるコツそもそも全館空調システムとは?
全館空調システムとは、一言でいうと住まい全体の空調を一括して管理できるシステムのことです。
全館空調システムは、小屋裏や床下に設置した大型の空調設備から配管ダクトを通して、一定の快適な温度に保たれた空気を家中に循環させます。
各部屋にエアコンを設置する通常のシステムと異なり、キッチンや浴室も快適な温度に保たれるため、冬場のヒートショックによるトラブルなどを避けられます。
全館空調システムの電気代が高いと言われる理由
全館空調システムの電気代が高いと思われがちな主な理由は、以下の2つです。
家全体を温度管理するため、空調を効かせる範囲が大きくなるから 24時間365日稼働であるため、家に人がいないときの電気代が無駄に思えるから
こうした理由から、広い範囲においてつけっぱなしにする全館空調システムを、電気代の観点で非効率だと捉える人は少なくありません。
それにもかかわらず、多くの電機メーカーやハウスメーカーが全館空調システムを推奨しています。
その理由は、エアコン特有の電力消費における特徴を理解して使用すれば、全館空調システムにしても電気代を低く抑えられるからです。
エアコンはスイッチ始動時において、平常時の10倍程度の電力を消費します。
そのため、各部屋に設置したエアコンのオン・オフを繰り返すと、一定温度を24時間保ち続ける全館空調システムよりも電力を消費してしまう場合があります。
エアコンの電力消費量は、全館空調システム以上に使い方で大きな違いが生じることを理解しておきましょう。
全館空調システムにかかる電気代をエアコンと比較
ここでは、全館空調システムにかかる電気代をエアコンと比較します。
まず、総務省統計局による2023年家計調査から、1〜7月までの電気代(2人以上の世帯平均)を見ていきます。
<2023年:2人以上世帯における電気代の全国平均>
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
1万7,190円
1万8,750円
1万7,228円
1万3,617円
1万1,174円
9,270円
8,627円
※2023年9月時点
※参考:家計調査|総務省統計局
また、全館空調システムの場合の電気代について、ハウスメーカーや電機メーカーの公表値などを総括すると、以下の値になります。
月別平均
1万5,000円程度
冬場(真冬)・夏場(真夏)
1万5,000〜1万8,000円程度
春・秋
1万円程度
全館空調システムの公的機関のデータがないため正確な比較はできませんが、上表2つの結果を見る限り、全館空調システムの電気代が極端に高いとはいえません。
全館空調システムの場合、使用時間や延床面積によっても変動しますが、住宅の断熱性能や気密性能によって電気代が大きく変動する可能性があります。
24時間365日つけっぱなしで使用することもあるため、根本的な断熱性や気密性が低いと、夏は設定温度を下げて冬は上げなければなりません。
こうした場合、電気代が3〜4万円に高騰する可能性があります。
全館空調システムのメリット
ここでは、全館空調システムのメリットを解説します。
家全体を年中快適な温度に保てる 清潔な空気環境を維持できる 間取りの自由度が上がる
それぞれ見ていきましょう。
家全体を年中快適な温度に保てる
四季を問わず家中の室温を快適な温度に保てることが、全館空調システムの最も大きなメリットです。
全館空調システムでは、浴室や洗面所からトイレや廊下まで、家全体が適温で維持されます。
そのため、冬場のヒートロスによる健康障害や夏場のトイレ・キッチンでの不快な暑さを気にせず、快適に過ごせるでしょう。
清潔な空気環境を維持できる
機種にもよりますが、現在は空気清浄機能を備えた全館空調システムが主流になっています。
空気清浄機能がついている全館空調システムは、花粉やウイルス、有機化合物などを清浄してくれるうえ、悪臭もカットしてくれます。
温度だけでなく、クリーンな空気で満たされた住環境を提供してくれるでしょう。
間取りの自由度が上がる
通常のエアコンは、壁に仕切られた部屋面積を前提に商品ラインナップを決定します。
一方、全館空調システムであれば、空調によって部屋を仕切る必要がないので、間取りやレイアウトの自由度が高くなります。
通常、吹き抜けや小屋裏、大空間リビングなどは空調環境を整えるのが困難です。しかし、全館空調システムであれば、こうした心配は全くありません。
全館空調システムのデメリット
ここでは、全館空調システムのデメリットを解説します。
初期費用やメンテナンス費用がかかる 換気フィルターの交換が必要になる 部屋が乾燥しやすくなる
順に見ていきましょう。
初期費用やメンテナンス費用がかかる
全館空調システムの初期費用は、通常のエアコン設置にかかる費用に比べて高額になります。
一般的に多く普及している35〜40坪程度の4LDKで、初期費用を比較してみましょう。
全館空調システム
壁掛け式エアコン4台
100〜250万円
50〜55万円
このように、全館空調の初期費用は商品によっては、エアコンの2〜5倍程度の費用がかかるケースがあります。
故障したときのことも考慮すると、初期費用がかかる点はデメリットです。
また、故障を未然に防ぐための定期点検及びメンテナンス費用として、年間1〜3万円程度の出費を見込んでおく必要があります。
換気フィルターの交換が必要になる
全館空調システムの性能を維持するためには、各種フィルターの掃除・交換が欠かせません。
各種フィルターの掃除・交換の頻度は以下のとおりです。
種類
掃除
交換
粗塵防虫フィルター
3ヶ月に1回
2年に1回
給気清浄フィルター
年に1〜2回
2年に1回
交換はメンテナンス時に実施し、フィルター代として1ヶ所あたり3,000〜6,000円程度が必要になります。
機種によっては上記以外のフィルターが設置されている場合があるため、その場合は設置した住宅メーカーに相談してください。
部屋が乾燥しやすくなる
全館空調システムには、室内が乾燥しやすくなるデメリットがあります。
全館空調システムに限らず、エアコンは乾燥した外の外気を取り入れるため、室内が乾燥しやすくなります。
外気が冷たく乾燥しやすい冬場に、室内の乾燥した空気で喉がカラカラになったり肌がカサついたりした経験がある人は少なくありません。
また、冬場の送風式暖房は、設定温度より高い温度の空気を室内に供給します。高い温度の空気は湿度を下げる特質があるため、さらに室内が乾燥してしまいます。
全館空調システムの電気代を抑えるコツ4選
ここでは、全館空調システムの電気代を抑えるコツを4つ紹介します。
風量を自動運転に設定する 天井吹出し方式を取り入れる 予約機能が付いた全館空調を選ぶ 断熱性と気密性が高い家にする
1つずつ見ていきましょう。
風量を自動運転に設定する
風量をシステムに任せると、最もコストパフォーマンスに優れた温度に調節してくれます。
弱風設定にすれば電力消費量は下がりますが、最適温度に達するまでの時間が延び、総電力量が大きくなる場合があります。
自動運転システムを効果的に利用して、電気代を節約しましょう。
天井吹出し方式を取り入れる
全館空調システムには、天井吹出し方式・壁掛けエアコン式・床下冷暖房式の3つの種類があります。
天井吹出し方式は、小屋裏に設置した空調設備から繋いだダクトを通して室内全域に冷暖房の空気を送り、各部の天井に吹出し口を設けて空調します。
最も効率的かつ確実に全部屋を空調できる点が特徴で、コストが抑えられている商品が多くあるため、全館空調を導入する際は天井吹出し方式のものがおすすめです。
予約機能が付いた全館空調を選ぶ
温度予約機能の付いた全館空調システムを選べば時間単位で温度を調節でき、電気代を抑えられます。
外出時は必要最低限の温度設定や換気機能のみの設定にし、帰宅1時間前から設定温度になるように予約しておくことで、電気代を節約できるでしょう。
電気代を抑制するコツは、帰宅1時間前に起動させ、徐々に目標温度に到達するような温度設定にすることです。
エアコンは一気に温度を上げようとすると電力消費量が大きくなるので、徐々に上がるような温度設定がおすすめです。
断熱性と気密性が高い家にする
全館空調を効果的に利用するために最も大切なことは、住宅そのものが高断熱・高気密であることです。
全館空調システムを高品質なものにしても、家そのものの断熱性や気密性が低ければ、室内の暖まった空気は外部に逃げてしまい、外部空気は簡単に室内に侵入します。
空調システムを検討する前に、住宅そのものが高断熱・高気密であることが大前提だと理解しておきましょう。
高知県でこれからマイホームを検討される人には、建匠の『極断熱の家』がおすすめです。
極断熱の家は、断熱性能において標準仕様で北海道基準のUA値0.46をクリアしており、空調システムを検討するには非常に適した性能を持っています。
断熱性、気密性だけでなく、耐震性・耐候性も非常に高い水準にあるので、これから新築を検討する人はぜひお近くのモデルルームに足を運んでみてください。
極断熱の家|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店
全館空調システムの電気代に関するよくある質問
ここでは、全館空調システムに関してよくある質問に回答していきます。
全館空調は部屋ごとに分けられる? 全館空調の電気代は家自体の日当たりが関係する? 全館空調は24時間つけっぱなしのほうがお得?
順に見ていきましょう。
全館空調は部屋ごとに分けられる?
全館空調システムの多くは、部屋ごとに温度を設定できません。
とはいえ、適正な温度環境であれば全館空調システムにおいて、暑がり・寒がりの人でも快適に過ごせるでしょう。
また、暑がりの人が多いイメージのある高知県においても「ストレスなく快適に過ごしている」といったお声をいただいております。
そのため、全館空調は部屋ごとに温度は設定できないものの、快適に過ごすことは実現可能だといえます。
全館空調の電気代には家自体の日当たりが関係する?
全館空調の電気代には家自体の日当たりが関係します。
全館空調システムを導入した家だとしても、室内の空調を調節する仕組みは通常のエアコンと変わらないので、家自体の日当たりが悪ければ電気代は高くなります。
日当たりだけでなく、建物そのものの断熱性・気密性、住んでいるエリアなどによって暖房効率は変化するので、こうした要因も電気代に影響します。
全館空調は24時間つけっぱなしのほうがお得?
全館空調システムの場合、頻繁にスイッチのオン・オフを繰り返すのであれば、つけっぱなしにして時間ごとに温度が変わる設定にするほうがお得になります。
風量設定の自動運転や予約機能を上手に利用すれば、24時間つけっぱなしでも電気代が極端に上がることはありません。
全館空調システムを導入するなら工夫しながら電気代を抑えよう
全館空調システムの導入を検討するなら、24時間365日つけっぱなしにして利用することを前提に、システムの機能自体を上手に使うことを考えましょう。
避けるべきことは、寒い真冬などに一気に温度を上げようと高めの温度設定にすることや、節約になると思って何度もシステムのオン・オフを繰り返すことです。
帰宅1時間前から設定温度に向かって徐々に室温が上がるように自動予約するなど、最適なコストパフォーマンスが得られる風量の自動設定を上手に利用してみてください。
全館空調システムを上手に利用し定期的なメンテナンスを実行することで、1年を通じて健康的でクリーンな空気に満たされた住環境を手に入れられるでしょう。
また、全館空調システムだけでなく通常のエアコンにおいても、高断熱・高気密性能の住宅であることが前提です。
建匠では、高断熱・高気密住宅の提案に合わせて、コストパフォーマンスに優れた空調システムも提案します。
断熱性や気密性に優れた住宅であれば、エアコンの台数を抑えた空調環境を作れるため、興味のある方はお近くのモデルルームで実際に体験してみてください。
お問い合わせ・資料請求|高知で新築注文住宅なら【建匠】家族の笑顔を生み出す工務店