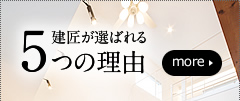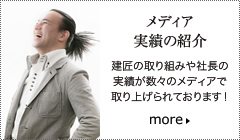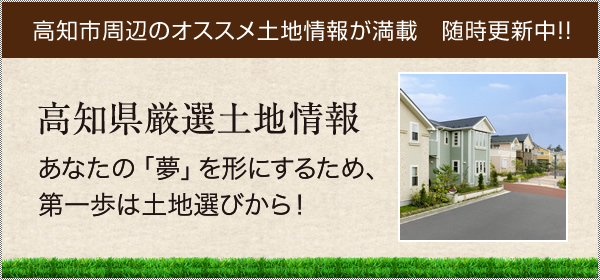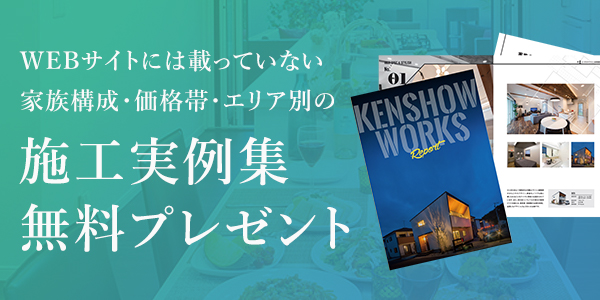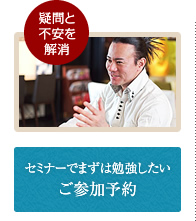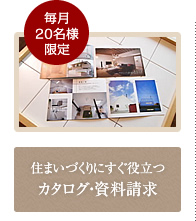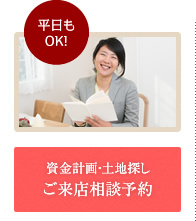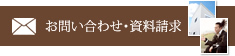新築の住宅を買うなどして、不動産を取得すると固定資産税の支払いが毎年必要になります。
「固定資産税は高いっていうけど、具体的にいくら?」「いつどうやって払うの?」と疑問を感じる人もいるでしょう。
そこで今回は、新築にかかる固定資産税について解説します。
固定資産税の決定方法や新築の固定資産税の平均額を確認し、安く抑える方法も把握しておきましょう。
新築の固定資産税とは
固定資産税は地方税のひとつで、不動産などの固定資産に課せられる税金です。
不動産には居住用の住宅や土地だけでなく、商業利用されている建物、田畑が固定資産税の対象となっています。
駐車場も不動産に含まれるため「土地」として固定資産税の対象となっていますが、屋根がある場合は「建造物」として課税されることがあります。そのため、条件次第では課税対象が変わることがあるため注意が必要です。
固定資産税の決定方法 固定資産税の納税は毎年変わる 都市計画税が必要な場合も
ここからは、固定資産税の上記3点について詳しく解説していきます。
固定資産税の決定方法
固定資産税は、建物や土地の評価額によって決定されます。
建物は新築時に調査を行なって評価額が決められ、土地は固定資産評価額によって決まります。
土地の上に建物がある場合は「家屋部分」と「土地部分」のそれぞれで計算されます。固定資産税を決定するときに使われるのは固定資産評価額で、不動産の購入費用は関係ありません。そのため、不動産の価格が高額だったとしても固定資産税が高いとは限りません。
また固定資産税額の決定は各自治体が行なうため、納税額が知りたいときには自治体から届く「固定資産通知書」で確認しましょう。
固定資産税の納税は毎年変わる
固定資産税は変動制の税金のため、税額は毎年変わります。税額が変わる理由は評価額にあり、評価額が年によって変更されるため、それにともなって固定資産税額も変わります。
評価額の変動は建物と土地で異なり、建物は基本的に築年数が経つほどマイナスとなります。
建物は大切に使っていたとしても経年劣化を防ぐことはできず、年数に応じて評価額は下がっていきます。
しかし土地の場合は、建物のように経年劣化を起こすことはなく、社会情勢や地域の価格変動によって、評価額が上下するため、固定資産税も同様に変化します。
都市計画税が必要な場合も
地域によっては固定資産税だけでなく、都市計画税も支払わなければならないことがあります。
都市計画税は地方税のひとつで、都市整備や公共事業のための費用として徴収される税金です。
固定資産税と同様に建物と土地に対して課税されて、固定資産税と一緒に支払います。
税率は地域によって異なり、最大税率は0.3%です。
固定資産税の標準税率が1.4%なので、合わせて評価額の1.7%を税金として支払うことになります。
新築の固定資産税の平均額は10万円
3,000万円の新築住宅の場合、年間の固定資産税は10万円前後と言われています。
1ヶ月あたりの金額に直すとひと月1万円ほどです。
固定資産税の金額は上記の通り地域によってことなりますが、標準税率である1.4%を採用している自治体が多いです。
ただし、人口の少ない地方の自治体は税収が少ないため税率が高い傾向にあります。
高知県内の税率は高知市・須崎市の税率は1.5%で、南国市・香美市など市区町村は標準の1.4%です。
固定資産税の計算方法
固定資産税額は以下の式で計算することができます。
「固定資産税額=固定資産評価額✕税率」
住宅の場合には以下の二つの特例が適用されます。
住宅用地で200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準額が1/6となる 住宅用地で200㎡超の部分(一般住宅用地)については課税標準額が1/3となる
上記の計算式と特例を使って固定資産税を計算することができます。
新築・中古の固定資産税を実際にシミュレーション
解説した固定資産税の計算方法を、実際に以下の4つのパターンでシミュレーションしていきます。
新築一戸建て 新築マンション 中古一戸建て 中古マンション
順番に解説していきます。
新築一戸建て
新築戸建ての場合、建物と土地の両方に課税されます。
建物の評価額を2,000万円、土地の評価額を1,000万円だとすると、以下の式になります。
「(2,000+1,000)×1.4%=42万円」
200㎡以下の特例が適用されると建物の評価額は1/6になるため以下の式になります。
「(1,200+1,000)×1.4%=30.8万円」
ただし、新築の住宅の場合にはさまざまな軽減税率が適用されるため実際の固定資産税はもう少し安くなる傾向にあります。
新築マンション
新築のマンションでの固定資産税額は土地がほぼないので、建物が課税対象の大半になります。
不動産の評価額を3,000万円だとすると以下の式のようになります。
「3,000×1.4%=42万円」
中古一戸建て
戸建て住宅で築年数が35年ほど経つと評価額は新築時に比べて10%ほどになり、土地と一緒に課税されます。
建物の評価額を200万円、土地の評価額が1,000万円だとすると以下の式になります。
「(200+1,000)×1.4%=16.8万円」
中古マンション
マンションは戸建て住宅に比べて、評価額はそれほど下がりません。
築35年のマンションの固定資産評価額は新築時の40%ほどになります。
不動産の評価額を1,200万円だとすると以下の式になります。
「1,200×1.4%=16.8万円」
新築の固定資産税を安く抑える方法
毎年支払う固定資産税は安く抑える方法があるのをご存知でしょうか。
通知された固定資産税の金額をそのまま支払っていては損をしてしまいます。
そこで、新築の固定資産税を安く抑える以下3つの方法を紹介します。
減税措置を利用する クレジットカードで支払う 家屋調査を慎重に行う
詳しく解説していきます。
軽減措置を利用する
一部の建物や土地は固定資産税の減税対象となっていることがあるため、軽減措置を活用しましょう。
固定資産税の軽減措置の種類はとても豊富で、地域によって手続きの有無は異なります。
申し込みが必要かどうかは事前に確認しておきましょう。
自治体のホームページで固定資産税の所轄部署を調べると確認することができます。
クレジットカードで支払う
固定資産税の支払いをクレジットカードで使うことで、お得に支払えます。
ポイント還元制度があるクレジットカードでは還元額分のポイントを手に入れることができます。
ただし、手数料が自治体によって違うため、「手数料よりも還元分のほうが高いか」は見極めが必要なポイントです。
家屋調査を慎重に行う
建物の新築時には家屋調査が行なわれます。
家屋調査の結果によって、評価額が変わるため、家屋調査にはなるべく立ち会いましょう。
評価額の決定は家屋調査員が行なうため、間違ってしまうことがあります。
間違った金額を支払ってしまうと本来よりも高い金額を支払うことになります。
分からないことがあれば、評価額が決まる前に申し出て、間違いが無いか確認しましょう。
新築の固定資産税の滞納に注意
固定資産税の支払いが遅れてしまうと「延滞金」が発生します。
延滞金は納付期限の次の日から発生し、最初のひと月は割合が低いですが、そのあとは一気に高額になります。
1年延滞してしまうと14.8%も上乗せされるため、なるべく早く支払いましょう。
さらに督促状や催告を無視して延滞を続けてしまうと。すぐに貯金や不動産が差し押さえられてしまいます。
新築の固定資産税に関するよくある質問
最後に、新築の固定資産税に関するよくある質問をまとめました。
・新築の固定資産税は誰が払う?
・新築の固定資産税はいつからかかる?
上記2点について、回答していきます。
新築の固定資産税は誰が払う?
固定資産税は対象となる不動産を保有している人が支払います。
支払い方法は金融機関からの振込、口座振替、クレジットカードなどがあります。
新築の固定資産税はいつからかかる?
固定資産税は家が建った日ではなく、その年の1月1日時点で不動産があるかどうかで、所有者に対して課税されます。
つまり、1月1日時点で不動産を取得していれば、その年の4月1日~3月31日までの固定資産税が課税されます。
反対に1月2日に不動産を取得したときには翌年から固定資産税が発生することになります。
新築一戸建ての固定資産税は何年で下がる?
一戸建ての場合、経年劣化があるため毎年建物の評価額は下がっていき、固定資産税もそれに伴って下がります。評価額は10年でおよそ新築時の60%の評価額となり、20年で25%になります。
まとめ:新築の固定資産税は安く抑える工夫をしよう
固定資産税は家や土地などの不動産に対して課税される税金です。税額は自治体が設定している税率によって計算されます。
ただし、土地や建物の条件によっては特例や減税措置を受けられる場合もあるため、工夫することが大切です。
減税措置の種類は非常に多く、各自治体によって異なります。確認する方法は各自治体のホームページにアクセスし、固定資産税の所轄部署を調べましょう。
また、クレジットカードで支払うとポイント還元を受けられるため活用することもおすすめです。
建匠ではお客様の要望を聞いて、ご家族の暮らし方にあったオンリーワンのお家を提案いたしております。
マイホーム作りのパートナー選びに少しでもお悩みの方は、ぜひ一度モデルハウスへお越しくださいませ。ご家族にあった暮らしのカタチをご提案いたします。
注文住宅を建てる際、まず初めに考えることは「予算」ではないでしょうか。
予算を決めないことにはどのくらいの大きさで、どのような住宅を建てるかが決められません。
今回は、フラット35の利用者情報から『注文住宅』と『土地付き注文住宅』における、あらゆる項目を抜粋し全国平均と高知県を比較して解説します。
なお、土地付き注文住宅とは、建築会社や施工期間などがあらかじめ決まっている建築条件がついた土地で建てる注文住宅のことをいいます。
土地と住宅を別々で購入する通常の注文住宅と異なり、建築条件付きのため期間の面を見るとスピーディーに家づくりを進められるのが特徴です。
※本記事で記載される金額は建匠の価格ではなく、平均的な数値です。
高知県で注文住宅を建てる費用相場
高知県で注文住宅を建てる時の建築費用について、以下の二つの項目を解説します。
注文住宅のみの場合 土地付き注文住宅の場合
実際に見ていきましょう。
注文住宅のみの場合
高知県で注文住宅のみを建てるときの建築費用はどれぐらいかかるでしょうか。
建築費用は、以下の通りです。
平均建築費用
平均建築面積
坪単価
全国
3,533.3万円
37.6坪
93.4万円
高知県
3,160.5万円
34.5坪
91.6万円
上記の表を見ると、高知県の建築費用は全国平均と大きな差はありません。
土地付き注文住宅の場合
では、高知県で土地付きの注文住宅を建てるときの建築費用はどれぐらいかかるでしょうか。
建築費用は以下の通りです。
平均建築費用
平均建築面積
坪単価
全国
2,961万円
33.6坪
88.1万円
高知県
2,883.8万円
32.6坪
88.4万円
高知県で土地付き注文住宅を建てると、全国平均に比べて少し建築費用が安いですが、坪単価で考えると大きく変わりません。
土地付き注文住宅の場合はどの項目も全国平均とほぼ同じような数字になっています。
【坪数別】高知県で注文住宅を建てる費用相場
高知県で住宅を建てるときの建築費用を以下の項目で解説します。
・注文住宅のみの場合
・土地付き注文住宅の場合
実際に見ていきましょう。
注文住宅のみの場合
土地の購入がなく注文住宅のみを建てる際、高知県の坪単価の相場は91.6万円です。
建築面積
高知県価格相場
全国価格相場
10坪
約916万円
約934万円
20坪
約1,832万円
約1,868万円
30坪
約2,748万円
約2,802万円
40坪
約3,664万円
約3,736万円
50坪
約4,580万円
約4,670万円
60坪
約5,496万円
約5,604万円
土地付き注文住宅の場合
高知県の土地付きの注文住宅の価格は坪単価で88.4万円です。
建築面積
高知県価格相場
全国価格相場
10坪
約881万円
約884万円
20坪
約1,762万円
約1,768万円
30坪
約2,643万円
約2,652万円
40坪
約3,524万円
約3,536万円
50坪
約4,405万円
約4,420万円
60坪
約5,286万円
約5,304万円
高知県の土地購入価格と建築費用の坪単価の相場
高知県の土地購入価格と建築費用の坪単価の相場は下記の表のようになります。
平均土地購入価格
平均土地面積
建築坪単価
全国
1436.1万円
219.1㎡(66.4坪)
90.7万円
高知県
962.3万円
233.1㎡(70.6坪)
90万円
高知県では全国平均よりも土地の購入価格が低いため、より広い土地を購入する傾向にあります。建築費用の坪単価は全国平均との差がありません。
全国の注文住宅・新築の平均坪単価は?
ここからは、注文住宅や新築の平均坪単価を全国の統計をもとに店舗のタイプごとに解説していきます。
ローコスト住宅メーカー 一般的なハウスメーカー 高級住宅メーカー
なお、本記事で紹介する平均坪単価は先述の通り全国平均となります。
価格は地域によっても異なりますので、自身が利用する店舗で事前に確認しましょう。
ローコスト住宅メーカー
ローコスト住宅メーカーでは、一般的な住宅よりも安く住宅を建てることができます。
坪単価は30万円ほどですが、オプションを加えると一般的な住宅と同じような価格になるため注意が必要です。
ローコスト住宅メーカーの坪単価
約30~50万円
一般的なハウスメーカー
一般的なハウスメーカーでは通常の注文住宅の他にも輸入住宅を取り扱っているメーカーがほとんどです。
坪単価は40万円以上です。
一般的なハウスメーカーの坪単価
約40~70万円
高級住宅メーカー
高級住宅メーカーとはアフターフォローやサービスが充実している大手ハウスメーカーです。
坪単価は70万円以上となります。
高級住宅メーカーの坪単価
約70~100万円
高知県で注文住宅を建てた人に関するデータ
高知県ではどのような人が注文住宅を建てているのでしょうか。
年齢・家族数・世帯年収 職業
上記2点のデータに分けて、解説していきます。
年齢・家族数・世帯年収
平均年齢
家族数
世帯年収
全国
37.6歳
3.3人
634.9万円
高知県
37.1歳
3.3人
601.4万円
家族数、世帯年収はどちらも大きく変わりませんが、高知県では全国平均に比べて少し若く注文住宅を建てています。
職業
自営業
公務員
農林
漁業主
会社員
短期社員
派遣職員
アルバイト
年金受給者
全国
4,811
1,986
17
15,845
81
332
400
267
高知県
19
33
4
98
1
0
3
0
高知県で注文住宅を建てる人は会社員が最も多く、次に公務員が多くなっています。
全国平均では自営業が会社員の次に多いので、高知県とは異なっています。
まとめ:高知県で注文住宅を建てるなら建匠へ
高知県では土地の価格が全国の平均よりも安いため、土地付きで注文住宅を建てるのであれば、比較的お得に建てられます。
また、土地の購入費用を抑えることができるため、その分の予算を建築費用に回して、家の中の設備を充実させるという使い方もできます。
建匠では、幅広い価格帯のプランから、お客様のライフスタイルにあったプランをご提案いたします。
資金計画や土地探しのお手伝いもしていますので、マイホームの購入を検討している方はぜひ一度モデルハウスへ足をお運びくださいませ。
若いうちに自分たちだけの家を持つことは難しい話ではありません。
仕事のやりがいを優先して、年収が少ない方にも同じことがいえます。家を購入するタイミングは、欲しいと思った時がベストのタイミングであり、年収は問題ではありません。
もちろん、準備できる頭金や借入可能な金額は少なくなりますので、すべての要望を叶えることはできないかもしれませんが、ご自身のライフプランにあった家づくりは可能です。
そこで今回は、所得の低い方が持ち家を持つメリットとデメリットを解説していきます。
年収が低くても家を建てることができる背景もあわせて紹介していますので、これから家を建てる計画がある方はぜひ参考にしてみてください。
低収入でも持ち家を持つのは無理じゃない
低収入でも持ち家を持つことは無理な話ではありません。
一般的に、物件価格の2割程度の頭金が必要といわれていますが、現在は住宅ローンで全額融資を受けることが可能だからです。長期的に見て返済が可能かどうかが重要となりますので、年収が審査に与える影響は少ないといえるでしょう。
もちろん、頭金が不要といっても、契約金や諸経費など一定の現金は必要ですし、借入ができる住宅ローンの金額も少なくなります。しかし、自分たちに合った資金計画を作り、無理のない範囲で土地と建物を決めることでマイホームの取得が可能となります。
・低所得者層の持ち家比率は上昇している
・持ち家比率が増えている背景
それでは、低所得者層の持ち家比率の推移と背景を詳しく見ていきましょう。
低所得者層の持ち家比率は上昇している
近年、低所得者層の持ち家比率は上昇している傾向にあります。
はじめに、低所得者層(年収300万円未満)の持ち家比率(土地付注文住宅)を見ていきましょう。
住宅金融支援機構の『フラット35利用者調査』を見ると、低所得者層(年収300万円未満)の持ち家比率(土地付注文住宅)が全国的に上昇しています。住宅取得者に占める低所得者層の割合は、2011年の8.8%から2014年には最大14.4%へ上昇し、2015年以降も10%~11%台を維持しています。
土地なしの場合も、住宅取得者に占める低所得者層の割合は、同様の推移を見せております。2011年の10.9%から2014年には最大20%へ上昇し、2015年以降も15%~17%前後を推移しています。
次に、高知県の持ち家比率を見ていきましょう。
平成30の年住宅・土地統計調査を見ると、高知県の持ち家比率は所有関係別で64.9%と全国平均に比べて3.7ポイント上回る結果となっています。持ち家比率自体は横ばいの状況が続いていますが、住宅者取得者の中で、低所得者層(年収300万円未満)の割合が増えているデータがあります。
低所得者層(年収300万円未満)の持ち家比率(土地付注文住宅)は、2011年の14.3%から2013年に最大20%へ上昇し、2015年以降ばらつきはあるものの12%~19%前後と高い水準を維持しています。
土地なしの場合は、2011年の15.1%から2017年には最大22.8%へ上昇し、2018年以降も16%~18%前後と高い水準を維持しています。
このように、年により多少のばらつきはあるものの、高知県を含め全国平均でも住宅取得者に占める低所得者層の割合が増えているのです。
持ち家比率が増えている背景
持ち家比率が増えている背景の要因はいくつかありますが、その中でも住宅ローン金利が下がり、その後も低水準で続いていることが一番の要因といえるでしょう。
住宅ローンは借入金額が大きいため、わずかな金利差が大きな利息差を生みます。また、低金利により全額融資であっても、無理のない返済計画をたてることができるようになりました。過度な金利上昇の可能性は今後も低いと考えられ、住宅購入希望者の背中を押す結果となっています。
もちろん、住宅ローンの返済は何十年と続くものなので、過度な借入はおすすめできません。将来の金利上昇を見込んだ、余裕のある返済計画をたてることが大切です。
持ち家?賃貸?低収入の人の住居に関するメリット・デメリット
持ち家と賃貸にはそれぞれに一長一短があり、どちらが正解ということはありません。自分たちの暮しにあった選択が必要であり、家を購入するタイミングは人それぞれです。
持ち家と賃貸住宅に関するメリットとデメリットを解説しますので、現在の暮らしと将来の暮らしの両方を考えながらみていきましょう。
・低収入で持ち家を買うメリット
・低収入で持ち家を買うデメリット
・低収入で賃貸に住むメリット
・低収入で賃貸に住むデメリット
それでは、順番に解説していきます。
低収入で持ち家を買うメリット
低収入で持ち家を買うメリットは、コストの最適化にあります。
毎月支払う家賃がもったいないと感じたことがある方は多いのではないでしょうか。賃貸住宅はいくら家賃を払っても、自分たちの資産とはなりません。
しかし、持ち家は住宅ローンの返済が終わってしまえば、完全に自分たちの資産となり、月々の住宅にかかる費用負担も大幅に少なくなります。コスト面からみれば、住宅の購入は早ければ早いほどメリットがあるといえるでしょう。
低収入で持ち家を買うデメリット
一方で、低収入で持ち家を買うデメリットは、住み替えが難しい点です。
転勤や離婚など思いもよらない出来事が発生することがありますし、年を重ねることで暮らし方に対する考え方が変わることもあります。
住宅ローンを抱えることにより、身動きがとりづらくなることはデメリットといえるでしょう。
低収入で賃貸に住むメリット
低収入で賃貸に住むメリットは、住み替えが容易な点とメンテナンス費用が不要な点です。
転勤や進学などライフスタイルにあわせて場所や広さを選べますし、家賃以外の突発的な出費はありません。賃料の安い物件を選ぶことで、住宅購入の頭金を貯めたりと、ライフプランにあった選択がしやすいといえます。
低収入で賃貸に住むデメリット
低収入で賃貸に住むデメリットは、一生住み続けることが難しいことです。
老朽化に伴う取り壊しなど、退去せざるを得ないケースがあげられます。住み替えには一定の費用が掛かりますし、民間賃貸住宅の場合では入居審査で入居を断られるケースもあります。
毎月の家賃を考えると、賃貸住宅は終の棲家としては不安が残る選択といえるでしょう。
まとめ
ここまで、所得の低い方が持ち家を持つメリットとデメリットを解説してきました。賃貸住宅と比較していますが、賃貸住宅で数年暮らしてから、自分たちで家を建てる方法をおすすめします。家を建てるタイミングは人それぞれですが、費用の最適化を考えると、タイミングは早いに越したことはないのです。
若い内は年収も低く、頭金の準備も簡単ではありませんが、住宅ローン金利の低水準が続く状況は、家を建てる決断を後押ししてくれます。
また、年収が低い場合、住宅ローンの借入可能金額は少なくなりますが、悪い話ばかりではありません。借入金額が少なければ、将来にわたる返済の負担が少なくなるからです。すべての要望を叶えることはできないかもしれませんが、優先順位を決めて工夫することで、理想のマイホームを作ることが可能となります。
建匠では様々な価格帯のプランから、お客様のライフスタイルにあったプランをご提案いたします。資金計画や土地探しのお手伝いもしておりますので、マイホームの購入をお考えの方はぜひ一度モデルハウスへ足をお運びくださいませ。
2階建て30坪で家を建てようとする場合、どのような間取りにするかについて、色々と思い悩む方が多いのではないでしょうか。
延床面積で30坪というと、決して狭くはないが色々と詰め込むのは難しい絶妙な広さといえます。
そこで今回は、2階建て30坪の間取りや建てる際のポイントを解説していきます。余裕のある広さとはいえませんが、間取りの配置を工夫するなど、空間を上手く使うことで快適な暮らしを実現することは可能です。
自分たちのこれまでの暮らしと、これからの理想の暮らしを考えながら優先順位を決めることが大切です。優先順位のつけ方は人それぞれですが、共感できるポイントもあると思いますので、考えていきましょう。
2階建て30坪の広さはどれくらい?
2階建て30坪の広さは、㎡換算で約100㎡となります。シングルスのテニスコートの広さが約195㎡となりますので、テニスコートの半分程度をイメージするとよいでしょう。総2階建ての場合は、それぞれのフロアがテニスコートの4分の1と考えてみてください。
2階建て30坪の延べ床面積を確保するためには、どの程度の敷地の広さが必要になるかを見ていきましょう。
2階建て30坪の家に必要な土地の広さ
2階建て30坪の家に必要な土地の広さは、建ぺい率や容積率の制限によって異なります。いくつか例を挙げますので、参考にしてみてください。
建ぺい率60%・容積率200%の場合、必要な土地の広さは30坪程度となります。建物本体以外に、ガレージなども建ぺい率の算定対象となりますので、敷地の広さには余裕を見ておく必要があります。
建ぺい率40%・容積率60%の場合、必要な土地の広さは55坪程度となります。第一種低層住居専用地域など指定されるエリアは少ないでしょうが、自分たちの住みたいエリアであれば、制限に従う必要があります。
自分たちが住みたい地域の建ぺい率と容積率は、事前に確認しておきましょう。土地探しでは重要なポイントの一つです。また、建ぺい率・容積率いずれも制限の緩和措置がありますので、土地探しの段階で専門家へ相談することも検討してみてください。
2階建て30坪住宅の特徴
2階建て30坪住宅の特徴は、コンパクトなサイズ感で3、4人家族に向いている点にあります。
先に述べた通り、何でもかんでも要望を詰め込むことは難しい広さですが、レイアウトを工夫することで快適な空間を作ることができます。
間取りは2LDK~4LDKまでを想定していますが、ライフプランにあった間取りを選ぶ必要があります。2LDKの場合、居室はもちろんのこと、水回りや収納など居室以外のスペースをゆったりと確保する余裕があります。
反対に4LDKの場合、居室を区切る必要がありますので、レイアウトによっては、室内が狭く感じたり、生活動線が悪くなったりするケースもあります。家族の人数や暮らし方により、最適な間取りは変わってきます。
ライフスタイルの変化にあわせて対応できるように、人生設計を考えながらプランニングを行いましょう。
2階建て30坪の住宅は3~4人家族で標準的なサイズ感ですが、もう少し広ければと考える人も多いため、色々な工夫が見られることも特徴といえます。マイホームの建築にあたり、自分たちで色々と調べる中で、そういった工夫を目にする機会は多いはずです。
それらの工夫が自分たちの生活にあったものであれば取り入れた方が良いのですが、その判断は簡単なものではありません。自分たちの要望をしっかりと伝えたうえで、専門家の意見を取り入れるのがよいでしょう。
2階建て30坪の家の相場価格
2階建て30坪の家の相場価格を、全国平均と比べながら見ていきます。
建築費用(万円)
住宅面積(坪)
坪単価(万円)
高知県
2,883万円
32.3坪
89万円
全国平均
2,961万円
33.5坪
88万円
※参照データ2020年度住宅金融支援機構フラット35利用者調査(土地付注文住宅)
※建築費用は主体工事に加え、付帯工事やその他必要な費用を含む合計額
高知県を見ると、平均建築費用は2,883万円であり住宅面積が32.3坪となるため、坪単価は約89万円となります。坪単価89万円×30坪=2,670万円が一つの目安となりますが、実際には建築様式やグレードにより建築費用には大きな幅があります。建築会社により力を入れている価格帯は異なりますので、自分たちにあったプランを実現できる建築会社を選びましょう。
低価格帯が得意なハウスメーカーであれば、坪単価は30万~50万円前後となります。大手ハウスメーカーの場合、坪単価は70万円~90万円前後です。工務店の場合、ハウスメーカーの8割程度が目安となりますので、坪単価は45万円~60万円前後となります。また、別途付帯工事や諸経費などが必要となりますので、本体価格の3割前後を予定しておきましょう。
このように坪単価を目安とすることで、おおよその相場価格を掴むことができます。坪単価50万円の場合、50万円×30坪=1,500万円+450万円の合計1,950万円となります。
一方で、坪単価の出し方は建築会社ごとに違いますので、坪単価だけで判断するべきではありません。モデルハウスの見学時など、気になる部分はしっかりと確認することをおすすめします。
2階建て30坪の家を建てる際のポイント
2階建て30坪の家を建てる際のポイントは、自分たちの暮らしにあった工夫を取り入れることです。
30坪は㎡数に換算すると約100㎡となりますので、間取り次第ではありますが、快適な住環境を作ることができます。家族構成や暮らし方の違いで、最適な間取りの取り方は違いますし、取り入れるべき工夫も異なります。
家を建てる際に、注意しておきたいポイントを紹介していきますので、自分たちにあったものがあれば、ぜひ取り入れてみてください。
・生活動線を考える
・吹き抜けで開放感を持たせる
・リビング階段で広さを確保する
・収納スペースを確保する
・スキップフロアを上手に活用する
それでは、順番に解説していきます。
生活動線を考える
居室の数やレイアウトに関わらず、生活動線に配慮した間取りを作ることが大切です。
間取り図のプランを見る時に、朝起きて夜寝るまでの生活を思い浮かべてみましょう。生活習慣や暮らし方は人それぞれ違いますし、家族の中でも違いが出るものです。自分たちが使いやすい動線がとれるように、家族でしっかりと話し合いをしてください。その際に家事の分担なども話しておくと、イメージが掴みやすいかもしれません。
一方で、自分たちの意見だけで進めることはおすすめできません。専門家に自分たちの要望をきちんと伝えて、フィードバックしてもらった意見を取り入れながら、プランを作っていきましょう。実際に住み始めて、使い勝手が悪かったということがないようにしなければなりません。
吹き抜けで開放感を持たせる
2階建て30坪の家では、吹き抜けを設けて開放感を持たせる方法もおすすめです。人が広さを感じるポイントは、床面積の広さだけはなく、天井の高さも大きな割合を占めています。住宅の天井高は2m40㎝が一般的となっていますが、天井高が少し高くなるだけで、受ける印象は大きく変わります。
しかし、すべての空間を一律に高くすればよいというものではなく、LDKなど天井高にメリハリをつけることが快適な住空間を作るポイントです。
スペースの都合もありますので、窓側の一部に吹き抜けを設けるだけで、開放的な空間が生まれますし、採光や通風の面でもメリットがあります。
リビング階段で広さを確保する
2階建て30坪の限られた空間であれば、リビング階段で広さを確保するのもよい方法です。
階段を別に設けるのではなく、リビングに取り込むことで敷地面積の有効活用に繋がります。移動のための空間を減らすことで居住スペースを確保することが容易となり、リビング階段自体のインテリア性能が高く、おしゃれなリビング空間を演出できることもおすすめのポイント。
また、相性のよい吹き抜けと組み合わせることで、スペースの有効活用はもちろん、デザイン性に優れたリビングの演出ができます。設置のメリットとデメリットを比べながら、ぜひ検討してみてください。
収納スペースを確保する
広さの限られた家こそ、収納スペースの確保が重要になります。せっかく居住スペースを広々と取ったとしても、備え付けの収納スペースが少なければ、結果として散らかった印象を与えることになりかねません。
収納スペースは多すぎて困るものではないので、構造体を利用した収納棚や造り付けの収納をあらかじめ設置しておくなどの対策が必要です。また、高低差を利用して収納スペースを設ける方法を試してみるものよいでしょう。
スキップフロアを上手に活用する
スペースを有効利用するためには、スキップフロアを活用することもおすすめです。空間設計は少し難しくなりますが、書斎やワークスペースなど色々な用途に使えるため、自分たちにあった使い方を考えるのも楽しいものです。
また、リビング階段と組み合わせることで、住空間を広げつつ、家族とつながりのある空間を作ることができる点もおすすめの理由です。
2階建て30坪の間取り例
2階建て30坪と同じような条件で家を建てる人は多いので、いくつかおすすめの間取り例を紹介していきます。自分たちの暮らし方に合うものがあれば、ぜひ参考にしてみてください。
・回遊性あふれるお家
・住宅密集地の完全プライベートハウス
・ハイサイドライトのお家
それでは順番に解説していきます。
回遊性あふれるお家
30坪前後のコンパクトな家では回遊性のある動線を取り入れて、伸びやかな空間を実現する間取りがおすすめです。
広さを感じるポイントは天井の高さに加え、生活動線も大きな要因となります。回遊性のある間取りは、家族全員の動線を意識したもので、家事をしている時も動線が重なりにくいのが嬉しいポイントです。
移動のためのスペースが増えると、居住スペースが減るのではないかと心配する方がいるかもしれませんが、その心配は不要です。部屋には元々移動のためのスペースがあるので、開口部など少し工夫すればスペースの無駄使いとはなりません。
また、リビング階段と吹き抜けを組み合わせることでスペースを有効活用しつつ、より空間を広く見せることも可能となります。
住宅密集地の完全プライベートハウス
住宅密集地に家を建てるケースでは、2階リビングを採用することで多くの問題を解決できます。住宅密集地の問題点は日当たりや風通しが悪く、隣家からの視線が気になりプライバシー確保の面で不安があることです。
そこで1階に寝室と居室、2階にリビングを配置する間取りがおすすめですが、メリットばかりではありません。日照の影響で夏場は暑くなりやすかったり、来客時に移動の手間があったりとデメリットも存在しますが、工夫で改善できることもあります。
夏の暑さは屋根断熱など断熱性能に配慮した家作りが必要であり、来客時の移動の手間については、設計時に動線を考えながら間取りプランを考えて対応しましょう。
ハイサイドライトのお家
居住環境において採光は重要なポイントとなりますので、ハイサイドライト(高窓)のお家もおすすめです。
敷地条件によって、十分な採光が取れない場合でも、明るく快適な空間作りに役立ちます。プライバシー性も高く、カーテンを設置しなくても周囲の視線は気になりません。また、視線が外に抜けることで部屋の広さをより感じやすく、ハイサイドライトからの眺望を楽しむこともできます。
また、上に溜まった空気が高窓から抜けることで、低い位置の窓から空気が吹いて空気の流れが生まれ、効率的な室内換気が期待できることもメリットといえるでしょう。吹き抜けやスキップフロアとの相性もよく、組み合わせることでより快適で過ごしやすい生活空間を演出してくれます。
注意点は壁と窓の配置のバランスであり、窓をたくさん付けると断熱性が低下することに注意してください。デザイン面と実用面を両立する配置設計をする必要がありますので、専門家に相談して導入を検討してみてください。
まとめ
ここまで2階建て30坪の間取りや建てる際のポイントを解説してまいりましたが、理想の住まい作りの参考になれば幸いです。30坪は決して狭くはないものの、もう少し広ければと考える人も多いのではないでしょうか。
また、理想の家を実現するための様々な工夫がありますが、自分たちにあった選択をするためにも、将来の暮らし方をしっかりと考えておく必要があります。
2階建て30坪の広さはすべての要望を詰め込むことが難しいため、思い描く理想の住まいの条件に対して、優先順位を付けなければなりません。
そこで自分たちだけで考えるのではなく、家作りの専門家の意見も取り入れることが大切です。スペースの有効活用は工夫でカバーできることもありますし、相談することで思いもよらない解決方法が見つかることもあります。
建匠ではお客様の要望を聞いて、ご家族の暮らし方にあったオンリーワンのお家を提案しています。資金計画や家の性能も重要ですが、最も大切なことは理想の暮らし像についてです。
マイホーム作りのパートナー選びに少しでもお悩みの方は、ぜひ一度モデルハウスへお越しくださいませ。ご家族にあった暮らしのカタチをご提案いたします。
本記事では、変形地の活用方法や住宅の収益化について解説していきます。
変形地は、それぞれ種類によってさまざまな利用方法があります。通常の整形地に比べて手頃な価格で購入できることもあり、検討される方もおられることでしょう。
ここでは間取り作成のポイントや、住宅以外での利用方法についてご紹介します。
変形地の種類
まずは、変形地の種類について解説します。
・三角形や五角形
・うなぎの寝床
・傾斜地
・段差がある土地
・旗竿地
上記5点を詳しく解説していきますので、変形地について理解を深めていきましょう。
三角形や五角形
三角形や五角形は、非常に大きい土地です。
主に、相続や売却の際に土地を分割していった結果残った土地や、国の事業で道路などを建設・拡張する際に土地を売却し、余った土地がこのような形になることがあります。
うなぎの寝床
うなぎの寝床は名前の通り、うなぎのように細長い土地を指します。
つまり、敷地が道路に接する長さを表す「間口」が狭く、奥行の長い土地のことです。
昔ながらの連棟長屋住宅はまさにこの形であり、それぞれを切り離して別々に売りに出される土地は、このうなぎの寝床になります。
傾斜地
傾斜地は、一般的に崖といわれる30度を超える傾斜を指します。
もしくは、高さ3mを超える高低差のある土地で、傾斜地は崖以下の傾斜と高さが目安。
盛土などをしていて、地盤が弱い場合には地盤改良工事や、造成工事により擁壁が必要になる場合があるなど、想定外の費用がかかることもある土地です。
段差がある土地
高低差のある土地ということから、段差部分の土が崩れたりしないように押さえるための擁壁工事などが必要な場合がある土地です。
傾斜地と同じく想定外の費用がかかる可能性のある土地と言えます。
旗竿地
旗竿地は、航空写真などで上から見たときに「旗」と「竿」のような形をしている土地です。
道路に接する間口部分が狭く、奥に続く路地のようになっており、その敷地を抜けた先が大きく開けている土地を指します。
変形地を生かした間取り
変形地は、間取りを生かすことで便利な暮らしを可能にします。
・余りそうな部分は庭にする
・思い切ってワンフロアにする
・高低差を利用し地下やスキップフロアにする
上記3点の間取りについて、詳しく解説していきます。
余りそうな部分は庭にする
変形地で余ってしまったスペースは、思い切って庭にしましょう。
変形地は、鋭角な部分の利用方法に困るケースがあります。緩やかな角度であれば、建物スペースとすることもできますが、急な角度の場合、建築コストの割にデッドスペースのある、無駄の多い建物となってしまいます。
このような場合は、割り切って庭スペースにすることをおすすめします。
ガーデニングはもちろんのこと、たとえば駐輪場スペースであれば、鋭角部分であっても自転車なら収まりやすくなります。
また、鋭角部分も含めてウッドデッキを組み、バーベキュースペースとすることで、鋭角部分にはバーベキューで使用する道具などを納めるスペースとすることもできます。
思い切ってワンフロアにする
変形地の間取りに困った場合、ワンフロアにしてしまうのも手段の一つです。
変形地であることから、整形の部屋を確保することが難しくなります。同じ帖数であっても整形の部屋と変形の部屋とでは、家具の配置方法も有効スペースも大きく違います。
変形地は部屋を分ければ分けるほど、デッドスペースが増える可能性があるため、思い切ってワンフロアにしてしまうことも一つの選択肢です。広い空間にすることにより、変形地特有の閉塞感を解消し、むしろ開放的に活用することができます。
たとえば、一階は玄関スペースからも壁をなるべく排除し、全体的にフラットなアプローチを取ります。このように、LDKとしてご家族または来客の際の憩いの場として、広々スペースとします。
二階以上に浴室や洗面所、ライフスタイルやご家族に合わせた居室を確保することが大切です。
高低差を利用し地下やスキップフロアにする
傾斜地や段差のある土地の特性を上手く活かして、スキップフロアを設けることで、スペースの有効活用ができます。
スキップフロアとは、1階と2階の間または2階と3階の間にフロアスペースを確保することです。つまり、「中2階」や「中3階」といったイメージです。
プランニングにはセンスが必要なため、得意な建築会社を選ぶ必要がありますが、通常の住宅にはないようなおしゃれな空間とともに、機能性も兼ね備えた間取りが実現します。
また、高低差を利用して地下階や半地下スペースを設けることもできます。
地下階は擁壁の中に造り、RC構造となるため遮音性が高くなるため、書斎などの作業スペースに適しています。
変形地を住宅以外で活用する方法
ここからは、変形地を住宅以外の目的で活用する方法を紹介します。
・駐車場
・貸倉庫
上記2点について、詳しく解説していきます。
駐車場
変形地にプランニングを検討した結果、どうしても希望とはかけ離れてしまい、住宅の建築は難しいとなった場合には、駐車場用地として再検討してみるのも良いかもしれません。
高低差のない変形地であれば、アスファルト舗装のみを施して月極駐車場として賃貸利用するのが、最も費用を掛けずに運用できる方法です。
また、アスファルト舗装もせずに稼働している月極駐車場もありますが、雨の日に水溜まりができたり、車の乗り降りの際に車内が汚れやすかったりするため、利用者が決まりにくい可能性もあります。
また、変形地であることから駐車の区画割りが上手く行かず、収益が見込めないこともあります。
月極駐車場のほか、最近ではコインパーキング事業を行う方も増えています。
変形地を手頃な価格で取得して、設備投資を行い、メンテナンスや集金などの運営もご自身で行う方法です。
コインパーキング事業については、タイムズなどの大手事業者に土地を一括借り上げしてもらい、区画ごとに定額の賃料を受け取る方法もあります。
貸倉庫
他に変形地の運用方法として、貸倉庫があります。
アパートなどを建築するよりも低コストでの建築が可能な上、変形地を安く取得できれば、高い収益を見込むことも可能となります。
また、貸倉庫には他にトランクルーム事業もあります。
主にはコンテナボックスを設置し、コンテナボックスの使用契約を結んだ方の荷物を保管するという内容です。
コンテナを置くスペースがあれば運用ができるという点では、変形地の運用には適していると言えます。
ただし注意点として、コンテナを倉庫として運用する以上は、コンテナは「建築物」と見なされるため、建築確認申請や確認済証を受ける必要があります。
これまでは、上記申請を行わずにコンテナを設置していたようですが、最近はその数が増えたことから、各自治体も問題視するようになったようで、すでに設置されているコンテナで、建築確認を受けていないコンテナについても、随時チェックが入っているようです。
まとめ
ここまで変形地について紹介しました。
本記事をまとめると、下記の通りです。
・変形地には、その種類によってそれぞれに様々な活用方法がある
・変形地の特性を活かすことにより、一般の住宅にはない間取りをプランニングできる
・変形地には住宅以外にも駐車場や貸倉庫としての運用方法もあり、変形地を理由に土地を安く購入できればメリットが高い
・トランクルーム事業を行う場合、コンテナを設置する際には建築確認申請などの行政手続きがあるため、その費用も考慮に入れる必要がある
変形地にはさまざまな種類があり、それぞれにあった間取りをプランニングすることが大切です。それでも不安が残る場合は、実績のある施工会社に相談しましょう。
桧家住宅では、変形地での住宅建築デザイン及びプランニングも得意としています。
どんなに些細なお悩みにも、お客様に寄り添って提案いたしますので、是非お気軽にご相談くださいませ。
本記事では、狭小地を売ることが困難となってしまう理由や、売却方法などを詳しく解説していきます。
インターネットなどで土地情報を見ていると、かなり価格の安い土地を見つけることがあります。安い理由は様々あるのですが、その中の一つに「狭小地」があります。
そもそも、一体どの程度の大きさを狭小地と呼ぶのでしょうか。
今回はそんな狭小地について、売ることが難しい理由やおすすめの売却方法などを詳しくご紹介します。
狭小地とは?
狭小地の大きさに明確な定義はありませんが、15坪(約50平米)以下の土地に対して、狭小地と呼ばれることが一般的な認識です。
しかし、郊外を基準にすれば20坪程度であっても狭小地と呼ばれますが、都心部での20坪は狭小地とはあまり呼ばれません。
また、同じ狭小地という括りの中でも、15坪と10坪では、実際に建てられる家の大きさも全く変化。
さらに、接している前面道路の広さによって、同じ大きさの狭小地でもその利用方法は同様に異なります。
狭小地を売るのが難しい理由
狭小地が一概に「悪い土地」というわけではないのが前提ですが、狭小地がもつ特殊性から売却が難しいとされています。
ここでは、その理由について詳しく解説します。
・住宅ローンが組みにくい
・フラット35が組みにくい
・購入方法が現金一括のみ
狭小地は、面積の関係で住宅ローンが組みづらいという点において、売るのが難しいとされています。
狭小地を購入するにあたり、住宅を建築することを前提として、住宅ローンの利用を希望される方が多いと思われます。
金融機関により様々ですが、たとえば土地が40平米以下で建物面積が60平米以下の場合は融資の承認が下りないなど、独自の条件を設定しています。
そのため、狭小地においては、所有者の職業や勤続年数に関係なく土地の面積不足というケースで住宅ローンが通らないことがあります。
フラット35が組みにくい
民間の金融機関での住宅ローンが難しい場合、次の選択肢として「フラット35」がありますが、狭小地の場合にフラット35を組むことも難しいとされます。
現在は「住宅金融支援機構」という民間の組織がその融資を取り仕切っており、元々は公庫(住宅金融公庫)と呼ばれる国の機関でした。
フラット35で住宅ローンの融資を受けるには、「フラット35適合証明」という書類を発行する必要があります。これはつまり、融資対象の不動産がフラット35の融資基準に適合していることを証明する書類です。
狭小地の場合、この適合条件が大きなハードルとなります。
複数ある要件の中に「延床面積が70平米以上」という項目があります。
建蔽率や容積率といった、土地の大きさに対して建物のサイズを制限するルールがあるため、狭小地はその土地面積から大きな建物を建築することはできず、上記の延床面積70㎡以上という要件を満たすことが難しくなります。
こちらも結果として、フラット35での住宅ローンでの融資は難しいです。
購入方法が現金一括のみ
狭小地が住宅ローンの基準に満たないとなった場合、必然的に土地購入代は現金で一括払いのみとなります。
したがって、収益物件を建てることを前提にアパートローンなどの事業性融資を利用する方法はあるものの、居住用の住宅を建築されたい方にとって現実的な話ではありません。
狭小地の購入にあたっては、現金での資金調達も視野に入れる必要があります。
むしろ、「住宅ローンは組めれば幸い」という程度に割り切り、初めから現金での購入を考えておいた方が良いかもしれません。
狭小地の売り方
それでは、売りにくいとされる狭小地はどのようにして売ればよいのでしょうか。
その方法について詳しく解説します。
・不動産仲介を利用する
・土地の買取業者を利用する
・隣の土地を所有している人に相談する
現に所有している狭小地を売却する場合には、不動産仲介会社に依頼されることが一般的です。主な業務として、一般の売り手と買い手の間を繋ぐことに特化していますので、特に狭小地のような特殊な条件の土地を、少しでも希望に近い金額で売却をしたいのであれば、不動産仲介会社は適任といえます。
昨今の不動産会社は、集客活動をインターネットで行うことが主流となっています。
そのため、全国の方に売り土地情報を公開できます。
狭小地のような、収益物件の建築としても利用できるような土地の購入者は、全国にまたがって物件情報を収集しています。
つまり、狭小地の売却をインターネットでの集客で行うことは、非常に有効な手段と言えます。
土地の買取業者を利用する
狭小地の場合は、不動産仲介会社に売却を依頼しても、思うように問い合わせが無く、長期間に渡って売れないこともあります。
このような場合には、土地の買取を専門としている会社に売却をすることも一つの方法です。
土地の買取業者に依頼をすることのメリットは、買取業者側から土地の買取りを断われる可能性は非常に低く、買い取ってもらえないということにはならないという点です。
土地の買取業者は、いわば土地買取のプロであるため、どのような土地であってもその運用方法を見出しますので、そのほとんどの土地に、何かしらの価値がつきます。
隣の土地を所有している人に相談する
これまでの方法で狭小地が売れないという場合、隣の土地を所有している人に相談するのも手段の一つです。
自身の所有する土地が地続きで大きくなれば、資産価値の向上が見込めます。
実際に、売りに出た土地を隣の方が購入するケースは非常に多くあります。
また、予想以上の高値がつくこともありますので、まずは声をかけてみるのも良いかもしれません。
狭小地はコツを掴めば上手に売れる
狭小地の売却はある程度の労力を伴いますが、上記のようにポイントを押さえていくことで、希望に近い売却を実現できる場合もあります。
狭小地は、売却にかかる諸経費を抑えることがポイントです。
例えば不動産仲介会社へ支払う仲介手数料は、売却の手取り金額を圧迫します。
最近では不動産仲介会社に依頼をせずとも、全国の土地購入希望の方へ土地情報を直接紹介できるサービスも増えてきています。同じ金額で売却しても、その売却にかかる経費を抑えるだけでも、手元に多くのお金を残すこともできます。
一つの方法に頼らずに、様々なサービスを上手く活用することで、狭小地の売却であっても希望の売却金額に近づけることができるかもしれません。
ただし注意点として、個人間売買はトラブルのもとにもなりますので、慎重に行う必要があります。
複雑な問題を抱える土地であれば、不動産仲介会社や実績のある施工会社に相談した方か良い場合もあります。
まとめ
ここまで、狭小地について紹介してきました。
本記事をまとめると下記の通りです。
・狭小地の大きさには定義はないが、一般的には15坪以下の土地を指す
・狭小地は住宅ローンを利用するのが難しく、現金での購入が必要となる場合もある
・売却の際には土地買取専門の会社に依頼をすれば、売れないということはまず無い
桧家住宅では、狭小地での住宅建築デザイン及びプランニングも得意としています。
どんなに些細なお悩みにもお客様に寄り添って提案いたします。是非お気軽にご相談くださいませ。
本記事では、狭小な土地を購入するメリットやデメリットを解説します。
マイホームを建築するにあたり、狭小な土地の購入を検討している方もいるのではないでしょうか。その際には、「狭小な土地はマイホームの建築には適しているのか。」「狭小な土地を購入すべきではないのか。」といった疑問が生じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、狭小な土地を購入するメリット・デメリットを詳しく解説していきますので、ぜひ参照ください。
狭小な土地を購入するメリット
狭小な土地には、3つのメリットがあります。
・購入価格がリーズナブル
・土地にかかる税金を抑えられる
・利便性に長けている
ここでは、狭小な土地を購入するメリットについて、順を追って詳しく解説していきます。
購入価格がリーズナブル
狭小な土地を購入するメリットとして、まず一番に挙げるべきは購入価格がリーズナブルという点です。
狭小であるがゆえ、同じ坪単価のエリアでも価格を抑えて購入できます。
主に「土地価格+建物価格+諸費用」の総額が住宅の購入総額となりますが、土地購入価格が安く済めば、購入予算総額の大きなアドバンテージとなります。
土地にかかる税金を抑えられる
狭小な土地を購入する場合、土地にかかる税金を抑えられる点も大きなメリットです。
土地を購入する際には「不動産取得税」や、「固定資産税」と「都市計画税」(都市計画税は一部かからない地域があります)などが課税されます。
不動産取得税については、要件を満たす新築住宅を建てる場合の減税措置がありますので、課税されないことも多くありますが、固定資産税及び都市計画税は毎年かかる税金です。
狭小な土地を購入することで、土地にかかる上記の税金を抑えることができます。
利便性に長けている
狭小な土地は都市部に多く集まっていることから、利便性に長けている土地がほとんどです。
たとえば、バス停や駅が近くにあったり、商業施設にすぐ行ける場所であったりと、利便性が高いからこそ人気が集まっています。
狭小な土地は、日々の生活で繰り返される出勤や通学、ショッピングなどの負担を減らしたいという人へ非常におすすめです。
狭小な土地を購入するデメリット
上記では狭小な土地を購入するメリットについて解説しましたが、次はデメリットについても解説していきます。
・住宅ローンを組めない
・隣の家と密接している
・資産価値が少ない
上記3点もメリットに加え重要となりますので、ぜひ参考ください。
住宅ローンを組めない
狭小な土地を購入する際は、住宅ローンを組めないケースがあるというのがデメリットの一つです。
狭小な土地を購入する場合でも、住宅ローンを利用される方が多いと思われますが、金融機関の多くは狭小地への融資に一定の制限を設けています。
金融機関により様々ありますが、一般的な基準として一戸建住宅の融資の場合、土地面積が40平米以下、建物面積が60平米以下の場合は住宅ローンの取り組みが難しいのが現状です。
隣の家と密接している
狭小な土地は、隣の家との距離を広く取れず、密接していることが多くあります。
敷地内の限られたスペースを最大限に活用して、可能な限り建物面積を確保する必要があるため、隣地境界線との距離を空けることが難しいのがその理由です。
資産価値が少ない
前述のように、金融機関も融資に消極的な点から、狭小な土地は資産価値が少ないというのもデメリットです。
狭い土地は隣地との距離も狭く、閉塞感のある立地条件。さらに狭小な土地であるが故、建築できる建物もコンパクトに仕上げざるを得ないため、4人家族などの一般的な人数での入居は難しいなど、なにかと制約が多くなってしまいます。
そのため、資産価値にも影響が出てしまう場合があります。
狭小な土地はプラスになることも多い
狭小な土地の購入にはメリットがある反面でデメリットも存在し、中々購入に踏み切れないという方も多いのかもしれません。
しかし狭小な土地は、ご自身が居住するためだけに購入するのではなく、少し視点を変えることでさらにプラスに考えることもできます。
それは「収益物件」としての視点です。
たとえば、「戸建の賃貸」を目的として住宅を建築する場合に、狭小な土地は適していると言えます。一般的な広さの土地に、賃貸を目的として新築住宅を建築した場合、建物面積が広く取れることから賃料設定が高くなります。そのため、賃借人にとっても家賃の負担が大きく、借り手がつきにくい可能性があります。
一方で狭小な土地に住宅を建築する場合、その建築スペースは限られ、さらに土地取得価格も比較的お手頃であることから、総額を抑えることができます。
そのため、家賃も低く設定できることから、賃貸としての需要も高くなります。
他には、コインランドリー店舗を建築する方法もあります。狭小な土地でも、約10坪ほどあれば店舗の面積を確保することができます。最近は共働き世帯も多いため、コインランドリー店舗は全国規模でその数を増やしているという現状があります。
狭小な土地であれば、投資資金としての総額も抑えることができるため、適していると言えます。
このように居住用としてだけではなく、収益用としての購入も検討できるのが狭小な土地の魅力でもあります。
では、収益物件以外ではプラスは無いのかと言うと、決してそんなことはありません。
狭小住宅を得意とする建築会社に依頼することで、通常の住宅には無いような、デザイン性の高い個性的な住宅を建築することが可能です。
狭小な土地は、通常の建築よりもコストがかかる場合もありますが、狭小住宅の建築をノウハウ化して、余分なコストを極力抑えるための、企業努力を重ねている施工会社もあります。
そのため、狭小な土地には一般の新築住宅にはないような、魅力的な住宅を建てることができる可能性があるのです。
入居人数の多いご家族にとっては、根本的に広さが不足しているという理由から、狭小な土地の購入は見送られることが多いのかもしれません。
しかし、お一人やお二人など、比較的少人数でのご入居を考えられている方は、十分に検討の余地があると思われます。
まとめ
ここまで狭小な土地を購入することのメリット・デメリットについて紹介してきました。
本記事をまとめると、下記の通りになります。
・狭小な土地は非常に手頃な価格で購入できる反面、その狭さから隣地との距離を確保することが困難なため、閉塞感のある立地条件となる可能性がある
・狭小な土地は、金融機関からの融資を受けることが難しい場合があるため、気になる土地が見つかった場合は、建物のプランニングを検討する前に、融資の条件を満たす土地であるかどうかを確認する必要がある
・狭小な土地は、ご自身の居住用としてだけではなく、戸建賃貸やコインランドリーなどの収益物件を建築する土地としても購入の検討が可能
・通常の大きさの住宅建築の発想では思いつかないような、狭小住宅の建築を得意とする魅力的なアイデアを持った建築会社に出会える可能性がある
狭小な土地は不便だと思われがちですが、視点を変えることで多くのメリットがあることが分かります。狭小な土地について少しでも疑問が残る場合は、実績のある施工会社に問い合わせるというのも手段の一つです。
建匠では、狭小な土地に関して購入を希望されるお客様のサポートを行っております。
どんなに些細なお悩みにもお客様に寄り添って提案させていただきますので、是非お気軽にご相談くださいませ。
本記事では、狭小住宅で後悔してしまう原因と、その対処法を解説します。
家が小さい分、様々なコストを抑えられる、狭小住宅。一方で、「狭小住宅って住みやすいの?」「家が小さいと機能性がないのでは?」と不安になる人もいるのではないでしょうか。
夢のマイホームを手に入れることは、多くの人によって憧れでもあります。しかし、家を購入するということは、それなりに費用が発生するもの。家を購入したいと検討している人の大半が、できる限りコストを抑えてなおかつ機能的な家に仕上げたいと考えています。
そこで今回は、小さな家を建てた際に後悔する原因と、その対処法を紹介していきます。
小さい家で後悔する人もいる-原因を紹介-小さい家を好んで狭小住宅にしたものの、中には実際に住んでから後悔する人がいらっしゃいます。
都心部に家を建てることを検討している人は、土地代の価格が高いことから面積の小さな土地を選んで、家を建てる狭小住宅を選ばれる方も少なくありません。
しかし、工務店とよく相談した上で決めた家のはずが、住み始めてから後悔したという声を目にすることがあります。
ここでは、狭小住宅にして後悔したという方の原因を3つ解説します。
・吹き抜けに憧れてオープン階段にした
・開き戸同士が近い
・収納スペースが少なすぎた
原因その1:吹き抜けに憧れてオープン階段にした開放感のある吹き抜けに憧れてオープン階段にしたものの、それが後悔の原因となることがあります。
高い天井に自然光が差し込む、温かみのある広々とした空間が実現できる吹き抜け空間。吹き抜けの住宅は圧迫感がなく、人気が高い物件として昔から注目されています。
多くの住宅で吹き抜けの空間を採用していますが、コンパクトが売りの狭小住宅では、使いづらさが懸念点となります。狭い敷地の中で、できる限り広々とした空間を求めた結果、間仕切りを減らしてしまったという人も。間仕切りを減らしてしまうと、空調効率が悪くなり、空気をせき止めてくれる壁がないので一定の温度が保てなくなります。
さらに乳幼児がいる世帯がオープン階段を採用してしまうと、誤って転倒してしまう危険性があります。空調管理と事故防止は、間取りを考える上でとても大切なことです。
原因その2:開き戸同士が近い間取りの関係上、どうしても扉の位置が固定になってしまい、開き戸同士が近いというのも原因の1つです。
一見、間取り図だけを見ると問題なさそうに感じますが、いざ住んでみると不便なケースも。
特に、
・子供が遊び半分で壁にぶつけてしまう
・稀に近くのドアを同時に開けるタイミングがある
・誤って手を挟んでしまう場合がある
などの問題が生じるので、注意が必要です。
設計段階で、ある程度工務店側から「開き戸同士が近いこと」を確認されますが、大丈夫だと認識してしまうと後々の後悔に繋がります。
些細な問題だと感じる方が多いものの、住んでから気づくというケースが見受けられます。
どうしてもその場所に扉を設けなければならない場合は、どちらかを開き戸ではなく引き戸にすることをおすすめします。
原因その3:収納スペースが少なすぎたコンパクトな家にありがちなケースが、元々荷物が少ないばかりに収納スペースを少なく見積もってしまったというもの。
「収納を後付けにして自由にした方が使い勝手が良い」という考えで、元々の収納スペースに棚を設けなかったという人もいます。
起こりうる問題として、
・収納スペースにぴったりの棚が見つからなかった
・大きなものを買いすぎて入らなかった
・結局整理が難しくなった
などが挙げられます。
狭小住宅だからといって収納面を疎かにしてしまうと、後々後悔につながります。
小さい家で後悔しないための対処法ここでは狭小住宅で後悔しないための対処法を紹介していきます。
今回紹介する対処法は、以下の3つ。
・1つの間取りにこだわらないこと
・広い空間を求めても仕切りを設けるところはしっかりと設ける
・実績のある施工会社に依頼
それぞれチェックしていきましょう。
対処法その1:1つの間取りにこだわらないこと1つの間取りにこだわらないことは、狭小住宅にする上で大切です。
家を建てると考えた人は、さまざまな物件の情報収集にあたります。その際に、情報収集の段階で間取りも考えますが、1つの間取りにこだわらない方がさまざまな視点で物事を考えることが可能です。複数の間取りを知ることで、いざ設計図を作成する時に工務店側の提案に意見が出せます。
間取りの情報収集は、ネットはもちろん雑誌なども参考にしましょう。
対処法その2:広い空間を求めても仕切りを設けるところはしっかりと設ける「限られた空間を少しでも広く活用したい」という希望があった場合でも、仕切りを設けることが大切です。
小さい家で後悔する原因でも紹介しましたが、仕切りを設けないと、空調管理がしづらくなり冷暖房の効きが悪くなります。リビングに2階へ上がる階段を設けている人は、オープン階段の設置はよく考えてください。壁を設けることで空気が逃げるのを阻止してくれます。
住まい全体の断熱性効果を高めるのは、狭小住宅でも効果的です。
対処法その3:実績のある施工会社に依頼狭小住宅は、変形した土地はもちろん、道路からやや奥まったところなどさまざまな場所に建てられます。中にはあまり条件が良くない土地も存在していますが、実績の多い施工会社なら、その土地に合わせた快適な空間をできる限り提案してくれます。
中でも、
・土地はもちろん、その地域に詳しい
・狭小住宅の家づくりの実績がある
・実用的な狭小住宅に関する知識が豊富
上記3つをできる限り網羅している施工会社を選びましょう。
まとめ狭小住宅で後悔する原因と対処法などについて紹介しました。
狭小住宅にして後悔する原因をまとめると、
・吹き抜けに憧れてオープン階段にした
・開き戸同士が近い
という点が挙げられます。
狭小住宅にした際に、これらのポイントに注意をしないと、後で後悔する原因となってしまいます。事前に知っておけば後悔することもありません。小さな家に住む際には、どのようなことに注意すれば良いのかを理解することが大切です。
家づくりは悩むことが多く、さまざまな問題に直面しまうことは多いもの。そんな時に、強い味方になるのが「建匠」です。建匠では、家づくりに関わる全ての技術と情報を駆使し、家族1人1人に合わせた快適な暮らしを提案致します。
どんなに小さな問題や悩みにもお客様に寄り添って提案をさせていただきますので、家づくりでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
本記事では、一戸建てにかかる維持費や、一戸建てを購入する間に考えるべき費用について解説いたします。
マイホームは多くの方の憧れではありますが、所有してからもそれなりに費用がかかります。経年劣化などによる修繕費用やその他税金など、維持費は常に負担しなければなりません。
大まかにマイホームを持ちたいと考えることは決して悪いことではありませんが、今後かかる費用のこともしっかりと理解を深めていくことが大切です。
今回は、一戸建ての維持費はどのくらいかかるのかについて紹介していきます。
一戸建ての維持費はどのくらい?購入後に必要となる費用一戸建てにかかる維持費と、購入後に必要となる費用について詳しく解説します。
維持費といっても、人によってはさまざまですが、一戸建ての維持費は年間で平均約40万円だといわれています。
後ほど一戸建ての維持費の内訳は紹介していきますが、30年分の住宅ローンを支払い終わる頃には、合計で1,000万円以上するケースがほとんど。住宅購入を検討した場合、物件選びや住宅ローンを組んだり引っ越しの準備をしたりなど、大忙しです。
維持費については、住み始める前から考えておく必要がありますが、やるべきことが他に多数あり、意外に見落としてしまう部分といえます。住み始めてから維持費について考える方もいらっしゃいますが、年間の支払い額を考えるとマイホームを持つ前から考えておいた方が安心です。
では、購入後に必要となる維持費とは具体的にどのようなものが挙げられるのでしょうか。
一戸建てを維持する際の費用の内訳ここでは、先述した維持費の内訳について、それぞれ紹介していきます。
・各種税金
・修繕費用
・各種保険費用
・その他光熱費など
上記4点を解説していきます。
各種税金税金には主に2種類あります。
1つ目は「固定資産税」と呼ばれるもので、毎年必ずかかる地方税。
2つ目は「都市計画税」と呼ばれるもので、エリアによっては支払う必要がある税金。
まず「固定資産税」ですが、家が建てられた場所や形状、さらには大きさに建物の材質などによって金額が異なります。一般的に、購入価格の7割が固定資産税評価額となるので覚えておきましょう。また、特例を使用すれば、固定資産税の負担が減らせる場合もあります。
次に「都市計画税」ですが、一般的に市街化区域内に存在している土地とその建物が課税対象です。都市計画や都市区画整備の費用に充てられており、毎年一括または4回の分割で支払いが可能です。必ずしも住宅を購入した全員に発生する税金ではないので、自分が課税対象者かどうかの確認は各自治体の総務部や課税課に問合せましょう。
上記、2つの税金をしっかり押さえておくことがポイントです。
修繕費用修繕費用は維持費とはいえませんが、必ず必要になる費用ですので、普段から少しずつ貯めておきましょう。
一戸建ての修繕費用は所有期間によって異なりますが、主に600〜800万円ほどかかります。
住み始めてから数年は、さほど大きな問題に直面しなければ修繕費用はほとんど発生しません。しかし、築10年を迎えたあたりで設備の劣化が予想され、家の修繕が必要になります。
主に修繕が必要になる箇所として、
・キッチンやトイレなど、水まわり設備
・外壁修理・塗装
・屋根修理・塗装
などがあります。
上記3つ以外にも挙げられる箇所は多々ありますが、中でも修繕費用が発生しやすいのが水まわりです。水回りは使用頻度が高い部分である上に、年月が建てば経つほど経年劣化で修繕する回数も多くなります。
したがって、劣化が大きく進む前に修繕することをおすすめします。
気になる修繕費用ですが、水まわりと外装部分に分けて表で解説します。
また、下記の修繕費用の内訳はあくまで一例であり、依頼する施工会社によって異なります。修繕を依頼する際に、事前に料金を確認することも大切です。
【水まわり設備】
修繕箇所
修繕費用の相場
浴室
100~120万円
キッチン
100万円以上
洗面台
30万円
トイレ
20~50万円
【外装部分】
修繕箇所
修繕費用の相場
屋根修理・塗装
40~200万円
外壁修理・塗装
60~300万円
小さな劣化なら修繕工事する必要はありませんが、費用を抑えるために長年放置してしまうと、その分で費用も変動します。
水回りと外壁の修繕は、およそ10~15年で1度メンテナンスを入れましょう。
各種保険費用火災保険や地震保険など、万が一の時を考えて備えとして保険費用も維持費の1つです。
保険に入っていなければ、火災や震災で住宅が壊れた際に、修繕費用から捻出しなければなりません。保険は、タイプや特約の有無、補償内容などによって異なりますが、10年間で10〜20万円が平均とされています。
特に火災保険は住宅ローンを組む段階で加入が必須となるので、自分たちが住む家に合わせた適切な保険を選ぶ必要があります。
たとえば、
・家を建てるエリア
・建物の構造
・補償対象(家財も含む)
・特約の種類と範囲
・保険期間
などがあります。
契約内容は保険ごとに異なるので、相場を割り出すのは難しいとされています。
一般的に、東京都の保険費用の相場は火災保険で5年の期間を設けて約30,000円、地震保険で同じく5年の期間を設けて約10万円台だといわれています。どちらかを契約する方もいらっしゃいますが、火災保険と地震保険の両方に加入する方が多い傾向にあります。
また、人によっては住宅ローンを組む際に火災保険と地震保険以外にも「団体信用生命保険」への加入を求められる方もいらっしゃいます。
団体信用生命保険の適用条件は、主に以下の通り。
・住宅ローンの契約者が、返済途中で亡くなった場合
・高度障害状態に陥った場合
上記の条件に該当した際に、残っている住宅ローンが支払われます。
各種保険費用の支払いは、10年分を1度に支払ったり分割にしたりも可能なので保険会社とよく相談しましょう。
その他光熱費など先述した費用以外には、
・駐車場代
・光熱費
・自治会費
などがあります。
家を建てたエリアや駐車場の大きさなどによって差はあるものの、平均3~5万円だといわれています。
それぞれの内訳は以下の通りです。
駐車場代
約1万円~2万円
※全国平均~東京・大阪の平均
光熱費
約2万円
自治会費
500円~2万円
※全国平均~東京・大阪の平均 上記は、建てた家の立地や周辺の状況によって大きく変動するため、自分の住宅がどれくらいかかるのか、事前にチェックすることが大切です。
一戸建てを維持するのに年間でどの程度の維持費がかかる?冒頭でも触れましたが、一戸建ての維持費は年間で平均約40万円だといわれています。
ここでは年間で支払う各種維持費と、それらを30年ローンで支払った場合の総額を表で説明します。
【年間で支払う各種維持費】
項目
維持費用の相場
各種税金
約13万円
修繕費用
約30万円
各種保険料
約2万円
その他光熱費など
約3万円
合計
約48万円
住宅ローンが最大35年で組めますが、30年ローンの場合各種維持費は以下の通り。
【30年間で支払う各種維持費】
項目
維持費用の相場
各種税金
約300万円
修繕費用
約800万円
各種保険料
約80万円
合計
約1,180万円
家を建てるエリアなどによって、上記で挙げた相場よりもやや高額になる場合も考えられます。
これらを月換算にすると、およそ3~4万円が相場です。
一戸建ての維持費を抑える方法最後に、戸建ての維持費を抑える方法について紹介していきます。
マンションに比べて管理費用や修繕積立金などが必要ないので、その分安くなります。土地代や建物本体に大きく費用を支払うため、できる限り維持費は押さえたいと考える方はいらっしゃいます。
特に、保険費用や税金に関しては固定費用となるので、押さえるべき費用は修繕費です。住み始めてから大きな出費を出さないためにも、素材選びの段階から今後のことを見据えて選択していくことが大切です。
今回は、下記3つのポイントに分けて紹介していきます。
・メンテナンスがしやすい耐久性のある素材や設備を採用する
・定期的にセルフメンテナンスをしておく
・リフォームをする場合は実績のある施工会社に依頼する
一戸建ての維持費を抑える方法その1.メンテナンスがしやすい耐久性のある素材や設備を採用する家を建てた後の修繕費用を節約するために、メンテナンスしやすい耐久性のある建材を採用しましょう。
家を建てる前に、屋根や建物の外壁などの建材を決めます。年々、新しい建材は次々と開発されているので、施工会社とよく相談して耐用年数の長い素材を選びましょう。
さらに、建材は屋根や建物の外壁だけでなく、水まわりやドアなどの内装も決める必要があります。水まわりは特に修繕回数が多いとされている箇所なので、気になる部分は慎重に選ぶことが大切です。
一戸建ての維持費を抑える方法その2.定期的にセルフメンテナンスをしておく日頃から自分たちでセルフメンテナンスしておくのも、維持費を抑える方法の1つです。
気になる箇所を手入れすることで、経年劣化による腐敗や破損を防げます。
ただし、専門的な技術を必要とする箇所は、自分でやろうとすると逆に悪化につながる可能性があるので注意しましょう。
セルフメンテナンスする範囲は、汚れを除去したり床や壁の小さなヒビ割れなどを補修したり、手入れ可能な範囲に留めることが大切です。
一戸建ての維持費を抑える方法その3.リフォームする場合は実績のある施工会社に依頼する
リフォームする際は、実績のある施工会社に依頼するのが最適です。
先述しましたが、水まわりや外装のリフォームをする際、状況に応じて修繕費用は高額になります。そのため、施工方法や素材について事前に把握しておくことが安心に繋がります。
そんな時、実績の多い施工会社ならば、修繕箇所に合わせた最適なリフォームをできる限り提案します。
一戸建ての維持費をできる限り抑えるためにも、さまざまな条件を網羅している施工会社に依頼しましょう。
まとめ一戸建ての維持費の内訳や費用を抑えるポイントについて紹介しました。
本記事をまとめると、一戸建てにかかる維持費の内訳は年間で、
・各種税金は約13万円
・修繕費用は約30万円
・各種保険料は約2万円
・その他光熱費などは約3万円
となり、合計約48万円であることが分かりました。
建物本体の費用はもちろん、土地代など様々な費用が発生することで、維持費のことを全く考えていなかったという方は少なくありません。
家を建てるエリアや面積などによって費用は異なるものの、事前にしっかりとシミュレーションしておき、資金調達することで快適な暮らしが実現できます。
家づくりは、建物を完成させるまでがゴールではありません。
住み始めてからかかる費用もあるので、事前の把握が大切といえます。
そんな時に、強い味方になるのが「建匠」です。建匠では、家づくりに関わる全ての技術と情報を駆使し、家族1人1人に合わせた快適な暮らしを提案致します。
どんなに小さな問題や悩みにも、お客様に寄り添って提案をさせていただきますので、家づくりでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
高知県での一人暮らしの家賃相場を紹介していきます。
一人暮らしをすると決めたものの、毎月滞納することなく家賃を支払って行けるのか不安に感じる人は多いもの。
誰かと一緒に暮らす場合はそこまで神経質になることも少ないですが、一人暮らしとなると不安からなかなか踏み込めないでいるという人が多い傾向にあります。
今回は、高知県で一人暮らしを考えている人向けに家賃相場や一人暮らしのコツなどを紹介していきます。
高知エリアの家賃相場
高知県は豊かな緑に囲まれた自然豊かな環境を持った県です。
四国の太平洋側に位置しており、市の西側は丘陵地があって北側は山地が広がっています。
そんな高知県の家賃相場は、平均4~5万円ほどといわれています。
ただし部屋数によっても家賃相場は変動していきますので、参考程度にマンションまたはアパートタイプで目安となる平均相場を以下に記しておきます。
建物種別
間取り
最低家賃
最高家賃
マンション
ワンルーム
3.5万円(土佐市)
5.1万円(四万十市)
1K~1DK
3.7万円(香南市/香美市)
5.1万円(四万十市)
1LDK~2DK
4.4万円(土佐市)
5.4万円(高知市)
建物種別
間取り
最低家賃
最高家賃
アパート
ワンルーム
3.3万円(土佐市)
4.9万円(四万十市)
1K~1DK
3.5万円(香南市)
4.9万円(四万十市)
1LDK~2DK
4.2万円(土佐市)
5.3万円(高知市)
高知の住まいを替える場合の費用は?高知に限らず一人暮らしにかかる費用は家賃だけでなく、引っ越し代や賃貸契約した際の仲介手数料などが発生します。
初月時に発生する費用は、ざっと以下の通り。
・不動産業者への仲介手数料
・家賃
・敷金や礼金
・引っ越し代
・(家具家電の買い替え)
引越し業者を利用しないとしても、不動産業者への仲介手数料と、頭金を含む家賃は確実に発生します。
仲介手数料は、法律で貸主と借主に家賃半月分+消費税といった上限が決められています。
ただし、物件の中には仲介手数料が無料と宣伝しているところも珍しくありません。
近年では、借り手がつきやすくするために敷金/礼金ゼロ、もしくはどちらかゼロというような表記にしているところが増えてきています。
引っ越し代に関しても、自分たちで行う場合は費用はかかりませんが業者を雇う場合引っ越し代が発生します。
遠方から引っ越しする人はもちろん、家具や家電など荷物が多い人は当然費用がかさむもの。
依頼業者やシーズン、荷物の量によって料金は変動するので、多少のばらつきは出てくるでしょう。
高知の家賃を安く抑えるコツ
高知に限らず家賃を安く抑えて物件を探したい場合は、初期費用をできる限り抑えるということに重点を置いて探すことをおすすめします。
初期費用は契約する物件によって異なるものの、一般的に以下が挙げられます。
・敷金や礼金がかからない物件や、フリーレント物件を選ぶ
・不動産の繁忙期(引っ越しシーズン)を避ける
・不動産や大家に家賃などを交渉してみる
・最初から家具や家電が付いている物件を探す
まず敷金や礼金は、初月の家賃とは別で発生する初期費用です。
また、フリーレント物件は決められた一定期間内に解約した場合違約金が発生するものの約1ヶ月分の家賃負担がない物件ですので、大幅に初期費用のカットが見込めます。
もっと初期費用を抑えたい場合は、あえて引っ越しシーズンを避けて物件探しから引っ越しまでを行うのがおすすめ。
シーズンを避けるだけでも大体5,000円~1万円程安く引っ越せるのでお得です。
物件探しの段階で良い物件が見つかったら、不動産や大家に家賃などを交渉してみるのも1つの手。
多くの人が提示された金額でそのまま契約に移行することが多いのですが、大家的には空室を出す期間が続くくらいなら多少なりとも安くして借りてほしいという場合があります。
当初の家賃が5万円に対して1万円にしてほしいというような無理のある条件さえ提示しなければ、ある程度検討はしてくれる可能性はあります。
引っ越し後の家具や家電を新しく買い替えなければならないという人は、最初から備え付けの物件を検討してみましょう。
次に引っ越しするまでに資金を貯めておけばいいだけですので、1つ候補として考えてみてはいかがでしょうか。
一人暮らしの家賃を抑えるコツ
家賃をできるだけ安く抑えるコツはいくつか存在していますが、前提として一人暮らしに適した間取り選びが重要です。
一人暮らしだとしても、広々した空間に住みたいと憧れを持っている人は多いもの。
しかし、部屋が多すぎたり広過ぎたりしてしまうと、空間を持て余してしまいます。
家賃が高くなることにも繋がりますので、家賃を抑えたい人はワンルーム~1DK辺りがおすすめです。
1DKだとリビングにはテーブルやテレビなど、人を2~3人呼んでも窮屈にならない家具配置ができるのがベスト。
寝室など別室に関しては、ベッドやパソコンデスクなど置いて自分が快適だと感じてなおかつ程度ゆとりが持てる広さを設けるのが最適です。
賃貸物件は条件次第で自分好みの空間が見つけられるもの。
そのため理想のインテリアや部屋のレイアウトなどを考えると、より良い空間を実現したいがためについ欲張ってしまいがちになります。
ですが住む人のスタイルに合うように物件を選ぶことで、できる限り理想に近くすることは可能です。
大学生がよく利用する路線を選ぶ
大学生がよく利用する路線周辺には、学生向けの物件が多く存在しています。
そのため、家賃が比較的安い物件が多い傾向にあります。
できる限り家賃を抑えて家を探したいという人は、学生がよく利用する路線周辺を狙って探すのがおすすめ。
利用者の少ない路線で物件探す
毎日多くの利用者が集まる路線や駅周辺は需要が高いので、その分家賃も割高になりやすいです。
通勤や通学が不便だと感じないようであれば、エリア候補として検討してみましょう。
1駅違うだけで家賃相場が異なる場合がある
同じ路線を利用したとしても、たった1駅違うだけで家賃相場が異なる場合があります。
A駅周辺の家賃相場は平均4.5万円だったが、隣のB駅は3万~3.5万円だったということがまれにあります。
電車をよく利用する人は、可能であれば前後の駅や路線毎に物件を探してみるのもおすすめです。
駅からの物件までの距離や築年数を気にせず探す
物件の価格は駅からの距離と築年数で家賃相場が変動します。
家賃をとにかく抑えたい場合は、駅からの物件までの距離や築年数を気にしないで探すと見つかりやすいです。
どちらか片方を優先するのも1つの方法で、普段車移動が多いため築年数がやや新しい物件を選ぶのもアリです。
自分で探すのに限界を感じる前にプロに頼る
自分である程度物件を探すのは良いことですが、条件にこだわり過ぎて自分が知らない間にどんどん空室が埋まっていくという状況はよくある話。
根気よく探すのも時には必要ですが、自分で探すのに限界を感じる前にプロに頼るのも大切なことです。
実際に不動産へ足を運んで、プロの力を借りると家賃を抑えつつ条件の良い物件を紹介してもらえます。
高知県で一人暮らしが家族をもった場合の理想の間取りは?相場はどのくらい?
一人暮らしに最適な間取りは、ワンルームから1DK辺りがおすすめということを紹介してきました。
ここでは一人暮らしが家族を持った場合、世帯人数毎に理想的な間取りを紹介していきます。
戸建ての値段相場も併せてチェックしていきましょう。
世帯人数から間取りを考える
世帯人数が増えれば増えるほど、部屋の間取りは比例して増えていくもの。
例えば元々1人で住んでいた1DKの部屋に、結婚相手が住み出して子供が生まれるとなると手狭だと感じてしまいます。
家を建てる際にも同じことが言え、現状だけを考えて間取りを決めてしまうと後々後悔だけが残ります。
将来的な間取りを想定する際には、最終的な世帯人数や年齢層を考慮して考える必要があるのです。
・子供は3人欲しい
・子供1人1人に部屋を与えたい
・家を建てたら親との同居を考えているなど
10年20年先のことも考えて、しっかりと間取りを決めましょう。
世帯人数から考えるおすすめの間取り
具体的な間取りが分からない人のために、ここでは世帯人数毎におすすめの間取りを紹介していきます。
あくまでも一般的に理想とされる間取りですので、参考にしてみてください。
2人暮らしの場合
カップルや夫婦2人で住むことを想定した間取りを考えているのなら、リビングやダイニングといった共有空間と各々1人の時間が確保できる趣味などの居室スペースを設けるのがおすすめ。
寝室を共有にするのも良いですが、ライフスタイルに応じてもう一部屋プライベート空間を設けても良いでしょう。
将来的に子供が欲しいと考えているなら、広めの空間を一部屋用意するのもおすすめです。
広めにしておくと、子供が2人に増えた時に仕切りを作るなどして対応が可能です。
3人暮らしの場合
夫婦に子供1人を想定した間取りを考えているのなら、2LDK以上が理想です。
夫婦と子供の寝室を設けていれば、ある程度子供が大きくなったとしても家族間でプライバシーが守られます。
子供が大きくなると荷物が増えるので、収納スペースが多いに越したことはありません。
現状3人家族で、今後もう1人子供が欲しいと考えている人は、2人暮らしの時同様広めの空間を一部屋用意するのもおすすめです。
今は必要だと感じない3LDKの間取りだとしても、最初から用意しておくと子供が大きくなった時に書斎や趣味の部屋などにすることもできます。
4人暮らしの場合
夫婦に子供2人を想定した4人暮らし用の間取りを考えているのなら、3LDK以上が理想です。
3人暮らし用の間取りに加えて、来客が多い世帯は客間を設けて4LDKにするのもおすすめ。
その内一部屋はリビングに隣接させておくと、来客の有無に限らずゆったり広々とした快適な空間が作り出せます。
世帯人数別・居住面積水準
国土交通省が公開している「住生活基本計画における居住面積水準」では、世帯人数に適した居住面積水準について紹介されています。
世帯人数別の面積例
最低居住面積水準
誘導居住面積水準
2人
30㎡
55㎡~75㎡
3人
40㎡
75㎡~100㎡
4人
50㎡
95㎡~125㎡
近年では荷物を多く持たない家庭が増加傾向になり、「ミニマルライフ」や「断捨離」がブームとなっているとのこと。
シーズン毎に利用するものは、別途レンタル倉庫などを借りてそこに預ける人も少なくありません。
世帯によってはロフトや収納スペースを設けるところもあり、スペースを有効活用して説活しています。
一戸建て相場
高知県で戸建てを検討している人は、部屋数によって価格相場が異なります。
参考程度に目安となる平均相場を以下に記しておきます。
3DK以下
3LDK~4DK
4LDK~5DK
5LDK以上
高知の平均相場
1,737万円
2,508万円
2,524万円
1,831万円
2,395万円
高知では3LDK~4DKの間取りを持った一戸建てが多い傾向にあります。
ですが価格に差があるのは間取りだけのせいではなく、購入時期によっても価格相場が推移しているようです。
間取り別の価格相場推移に関しては以下の通り。
間取り
最低価格相場
最高価格相場
3DK以下
1,342万円(11月)
1,785万円(5月)
3LDK~4DK
2,406万円(6月)
2,541万円(12月)
4LDK~5DK
2,490万円(2月)
2,746万円(7月)
5LDK以上
1,799万円(2月)
2,346万円(8月)
上記は2020年のものですので、不動産とよく相談して購入時期などを検討しましょう。
まとめ
高知県で一人暮らしする際の相場と負担の少ない家賃の決め方を紹介してきました。
高知で新生活を始める際の参考にして頂ければと思います。