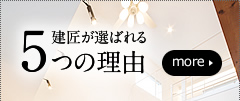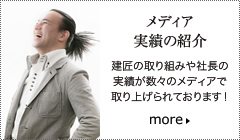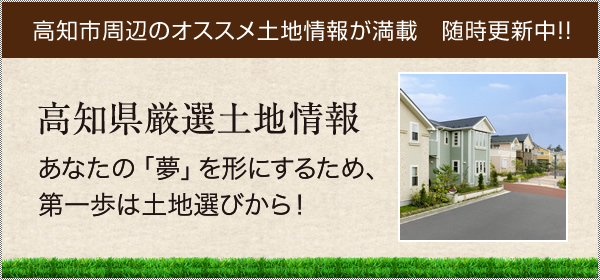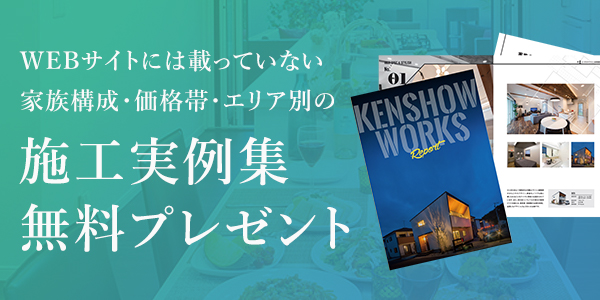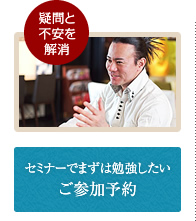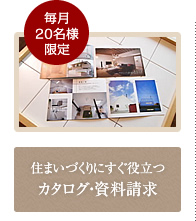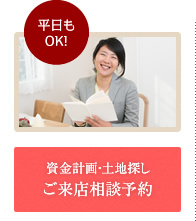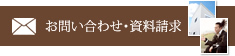家づくりでは、間取りや設備だけでなく床材選びも重要なポイントです。
木質系のフローリング材が一般的ですが、種類によってデザイン性や機能面は様々であり、どのような素材が自分たちの暮らしに合うか悩まれている方も多いでしょう。
そこで今回は、フローリングの種類や選び方について解説します。
マイホーム購入を検討中の方は、ぜひとも最後までお付き合い下さい。
フローリングの種類は大きく2つ
フローリングの種類は大きく以下の2つに分類され、規格住宅では複合フローリングが一般的です。
ただし、自然素材の家では無垢フローリングが使用されています。
無垢フローリング 複合フローリング
それぞれ順番に解説します。
無垢フローリング
無垢フローリングとは、一本の自然木から板を切り出して加工した床材のことであり、広葉樹と針葉樹の二つに分類されます。
木が本来持っている質感や温もりを感じられ、経年による色合いの変化を楽しめることが無垢フローリングの特徴です。
複合フローリング
複合フローリングとは、合板や集成材に薄い木板や化粧シートなどを貼り合わせた床材のことで、突き板タイプや挽き板タイプは無垢フローリングに近い性質を持ちます。
シートタイプの見た目は無垢フローリングに近いものの、自然素材の性質はありません。
いずれも施工がしやすくメンテナンスの手間が少ないため、規格住宅で多く用いられています。
【素材別】フローリングの種類12選の一覧表
フローリングに用いられる木材の種類を、素材別に以下の通りまとめています。
自分たちの住宅イメージに近いものがどれになるか考えてみましょう。
素材
使用用途
特徴
パイン(松)
無垢
針葉樹の中では硬く傷つきにくい
スギ
両方
軽く柔らかく断熱効果が高い
ヒノキ
無垢
硬く反りが少なく耐久性が高い
桐
無垢
軽く柔らかく歩行感が良い
オーク
両方
耐久性・耐水性に優れる
ウォルナット
両方
衝撃に強く耐久性に優れる
ブラックチェリー
両方
経年による色合いの変化に優れる
メープル(カエデ)
両方
強度が高く質感に優れる
チェスナット
無垢
強度が高く耐久性・耐水性に優れる
チーク
両方
油分が多く耐水性に優れ虫害に強い
タモ
両方
弾力があり硬く耐久性に優れる
バーチ
両方
経年による色合いの変化が少ない
【素材別】フローリングの種類12選
フローリングに使われる木材の特性を以下の通りまとめています。
デザイン性だけではなく、機能性にも注目して床材選びの参考にして下さい。
パイン(松) スギ ヒノキ 桐 オーク ウォルナット ブラックチェリー メープル(カエデ) チェスナット チーク タモ バーチ
それぞれ順番に解説します。
パイン(松)
パイン材は優しい肌触りとナチュラルな色合いで人気のある針葉樹の一種です。
比較的安価で、自然素材の家を建てたい方におすすめといえます。
スギ
軽く柔らかいスギ材は断熱性に優れ、素足で歩いても温かみを感じられる日本を代表する木材の一種です。
ヒノキ
美しい木目のヒノキは、湿気に強く耐久性・耐水性に優れた日本を代表する伝統木材です。
その独特の芳香は、リラックス効果にも期待できます。
桐
軽く柔らかい桐は、歩行感が良く調湿効果や防虫効果にも期待できる木材となります。
タンスのイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、床材としてもおすすめです。
オーク
明るい色合いで、比較的硬く耐久性に優れる床材としてポピュラーな広葉樹の一種です。
内装やインテリアに問わず合わせやすいことが特徴です。
ウォルナット
褐色の色や木目が美しいウォルナットは、加工性がよく硬さもあり、世界三大銘木として広く親しまれています。
ブラックチェリー
木肌が滑らかで肌触りの良いブラックチェリーは、経年による色合いの変化を楽しめる木材です。
時間とともにツヤと光沢が増して美しい飴色に変化します。
メープル(カエデ)
硬く衝撃に強いメープルは、全体的に白っぽい色合いで部屋を明るく見せる効果がある人気の木材です。
チェスナット
ハッキリとした木目を持つチェスナットは、高い強度を誇り耐久性だけでなく湿気にも強い特性を持ちます。
水回りのフローリング材としておすすめです。
チーク
硬く強度のあるチークは、油分を多く含み腐食や虫害への耐性が強く、寸法安定性に優れる木材です。
タモ
はっきりとした木目と淡い色合いのタモは、肌触りが柔らかく弾性に富んでいるため、床材として好まれている木材です。
バーチ
肌目が緻密で淡い色合いが特徴であり、強度もあり加工しやすい広葉樹の一種です。
桜に似ているためサクラのフローリングと呼ばれることもあります。
無垢フローリングのメリット3つ
無垢フローリングのメリットをまとめています。
自然素材の家を希望する方は、自分たちの暮らしにどのような良い影響があるかを把握しておきましょう。
部屋に馴染みやすい 質感・肌触りの良さ 足への負担が少ない
それぞれ順番に解説します。
部屋に馴染みやすい
無垢フローリングは、素材により色合いが様々です。
経年による色合いの変化も相まって、部屋に馴染みやすいことがメリットといえるでしょう。
質感・肌触りの良さ
質感・肌触りの良さもメリットの一つです。
冬は暖かく、夏はさらさらと肌触りが良い無垢フローリングは調湿効果にも期待でき、日本の気候に適した床材といえます。
足への負担が少ない
足への負担が少ない点も、無垢フローリングのメリットです。
硬すぎず柔らかすぎず、適度に衝撃を吸収する木材は、歩きやすさに配慮した床材といえるでしょう。
無垢フローリングのデメリット2つ
一方、無垢フローリングにはデメリットも存在します。
自分たちの暮らしにどの程度影響があるかを把握した上で、導入を検討して下さい。
反り・隙間ができやすい 手入れする必要がある
それぞれ順番に解説します。
反り・隙間ができやすい
一つ目のデメリットは、反り・隙間ができやすい点です。
木材の収縮・膨張が原因であり、施工方法に配慮できる実績のある建築会社に施工を任せることで不具合のリスクを下げられます。
手入れする必要がある
手入れをする必要がある点にも注意が必要です。
慣れてしまえば手間にはなりませんが、木材ごとにメンテナンス方法が違いますので、建築会社に適切なメンテナンス方法を確認しておきましょう。
複合フローリングのメリット3つ
複合フローリングのメリットをまとめています。
無垢材と比較しながら、どちらが自分たちの暮らしに合うかを考えて下さい。
コストが低い 様々なデザインが選べる 傷つきにくいものが多い
それぞれ順番に解説します。
コストが低い
規格化された複合フローリングは比較的安価に導入できることがメリットであり、費用対効果の高い床材といえます。
メンテナンスを含めた生涯費用を考えると一概にはいえませんが、導入コストの低さは魅力の一つです。
様々なデザインが選べる
様々なデザインが選べる点もメリットであり、木質系はもちろん、化粧シートを張り合わせたタイプを含め、自分好みのデザインを探してみましょう。
傷つきにくいものが多い
傷つきにくい商品が多いこともメリットの一つであり、ペットの飼養だけでなく車イスでの利用にも対応可能です。
複合フローリングのデメリット2つ
複合フローリングのデメリットも紹介します。
費用面だけでなく多角的な視点から導入を検討して下さい。
無垢フローリングよりも踏み心地が良くない 傷ができたら修繕しにくい
それぞれ順番に解説します。
無垢フローリングよりも踏み心地が良くない
無垢フローリングよりも踏み心地がよくない点はデメリットの一つです。
木質系の床と比較して、衝撃吸収力の低さが理由であり、歩きやすさは無垢材に軍配が上がります。
傷ができたら修繕しにくい
傷ができたら修繕しにくい点にも注意が必要です。
傷自体は付きにくいものの、シートの剥がれなどが起こると部分的な補修が難しく、一部または全体を張り替えなければなりません。
フローリングの選び方4選
フローリングの選び方をまとめています。
床材選びは住宅の印象を決める重要な要素であることを踏まえて慎重に判断して下さい。
フローリング材の種類で選ぶ フローリング材の色で選ぶ フローリング材の特徴で選ぶ フローリング材を購入する際の予算で選ぶ
それぞれ順番に解説します。
フローリング材の種類で選ぶ
フローリング材の種類が様々であることはこれまで述べた通りです。
その特性を把握した上で、自分たちの暮らしに合ったものを選ぶようにして下さい。
フローリング材の色で選ぶ
フローリング材の色は内装の印象に直結しますので、建具や壁との配色を考えて選ぶことが重要です。
経年による色合いの変化も考慮しておくとよいでしょう。
フローリング材の特徴で選ぶ
調湿効果・歩きやすさ・デザイン性などフローリング材の特徴をもとに床材を選ぶことも重要なポイントです。
理想の住まいを実現するためにも、それぞれの特徴を把握しておくことをおすすめします。
フローリング材を購入する際の予算で選ぶ
予算の配分を考えてフローリング材を選ぶことも重要です。
ただし、メンテナンス費用を含めて比較すると、一概に無垢材が高いとは限りません。
他の要素と総合的に判断して下さい。
フローリングの種類に関するよくある質問
フローリングの種類に関するよくある質問をまとめています。
他の方の疑問点を自分たちに置き換えて考えてみましょう。
人気のフローリング材と色はどれ? 部屋や用途によってフローリング材の選び方は変わる? フローリングのメンテナンスのやり方は?
それぞれ順番に解説します。
人気のフローリング材と色はどれ?
人気のフローリング材と色は好みの問題もありますが、メープルなど白い床は空間を広く見せる効果があります。
家具や建具とも合わせやすいためおすすめです。
部屋や用途によってフローリング材の選び方は変わる?
フローリング材の特徴に配慮した配置が求められます。
具体的には、水回りであれば耐水性の高い素材を選ぶなど、ケースごとの使い分けを意識して下さい。
フローリングのメンテナンスのやり方は?
無垢フローリングの場合、仕上げの方法でメンテナンスのやり方が変わりますので、施工店に確認することをおすすめします。
メンテナンスの手間を省きたい方は、ワックスフリーの複合フローリングを検討して下さい。
まとめ:フローリングの種類を知って新築デザインのイメージを膨らませよう
床材といえば多くの方がフローリングを思い浮かべますが、フローリングの種類は多種多様であり、その特性を知ることが床材選びには求められます。
新築デザインのイメージを膨らませる際は、フローリングの種類を把握した上で、理想の住まいのイメージに近いものを選びましょう。
建匠では、ご家族にあったオンリーワンの住宅を提案しています。内装のイメージでお悩みの方は、お気軽にモデルハウスへ足をお運び下さい。
家づくりにおいて、多くの方に共通する悩みが収納に関する問題であり、収納スペースの失敗例は数多くあります。
延床面積との兼ね合いもあり、収納は単純に広ければ良いという話ではないので、難しい問題です。
そこで今回は、新築の収納はどれくらい必要かについて解説します。マイホーム購入を検討中の方は、ぜひとも最後までお付き合い下さい。
新築の収納はどれくらい必要?
新築の収納がどれくらい必要であるかは、家族構成やライフスタイル次第となりますので、人によって最適な広さはそれぞれです。
現在の荷物だけでなく、将来増えると想定される荷物や季節家電などを踏まえて、自分たちに必要な収納の広さをイメージしてみましょう。
建物に対して収納率は10%〜15%程度
収納率とは住宅の床面積に占める収納面積の比率のことであり、戸建てでは延床面積に対して10〜15%程度が目安とされています。
ちなみに、マンションであれば、8%〜10%の収納率が一般的です。
戸建ての延床面積が100㎡であれば、収納量の目安は10〜15㎡となりますので、ライフプランが定まらない内は、収納率を目安にして下さい。
新築の収納を考えるポイント4つ
新築の収納を考えるポイントをまとめていますので、自分たちの家づくりをイメージしながら見ていきましょう。
現在住んでいる家の収納量と比較する 収納面積の他に奥行きや場所を考える どこに何を収納する場所がいるかを考える 部屋や空間に置くモノから収納をイメージする
順番に解説します。
現在住んでいる家の収納量と比較する
一つ目のポイントは、現在住んでいる家の収納量と比較することです。
賃貸では十分な収納スペースを確保できるケースは少ないため、何とかやり繰りしている方が多いでしょう。
ライフステージの変化を考慮に入れつつ、現在の収納量に追加でどれくらいのスペースが必要か検討することをおすすめします。
収納面積の他に奥行きや場所を考える
収納面積の他に奥行きや場所を考えることも重要なポイントです。
ウォークインクローゼットなど奥行きのある収納では、通路に荷物を置けません。単純に広さだけを考えるのではなく、どのような使い方をするかをイメージしておかなければなりません。
どこに何を収納する場所がいるかを考える
どこに何を収納する場所が必要かを考えることも、収納を考えるポイントの一つであり、生活動線を意識した配置プランが求められます。
実際に生活を始めてから、この場所に収納があればと後悔するケースは多いので、間取り図面に家財や荷物を書き込みながら、一年を通した暮らしをイメージしてみるとよいでしょう。
部屋や空間に置くモノから収納をイメージする
新築では、部屋や空間に置くモノから収納を逆算してイメージすることも重要なポイントです。
荷物によって最適な収納の奥行きや高さは違いますので、収まりがよくなるよう設計プランに変更を加えることは、新築住宅の特権といえるでしょう。
新築で人気の収納5選
新築で人気の収納設備を紹介しますので、自分たちの暮らしに合うものがあれば、積極的に取り入れてスペースの有効活用を目指して下さい。
リビングの収納 玄関周りの収納 洗面所収納 パントリー ファミリークローゼット
順番に解説します。
リビングの収納
リビングでは居住スペースを確保するために大きな収納を設けるケースは少ないものの、造作棚の設置をおすすめします。
後になって収納棚を設置するよりも、設計の段階で収納を配置することで、デッドスペースの削減に繋がりますので検討してみましょう。
玄関周りの収納
玄関周りの収納では、シューズクロークの設置をおすすめします。
家族が増えれば収納する靴も増えますし、ベビーカーやゴルフバックなど部屋の中に持ち込みたくない荷物を収納するスペースとして有用です。
洗面所収納
洗面所は家族が増えれば、洗濯物やスキンケアグッズなど収納が足りなくなりがちな場所の一つなので、造作収納棚の設置がおすすめです。
また、ランドリースペースを洗面所と仕切り、収納スペースを確保するのもよいでしょう。
パントリー
パントリーはキッチンに設けられる収納スペースのことで、食品や使用頻度の少ない調理器具の保管に役立ちます。
壁付けタイプやウォークインタイプなど自分たちの暮らしに合った配置プランを考えてみましょう。
ファミリークローゼット
ファミリークローゼットとは、名前の通り家族みんなで使う共用の収納スペースのことです。
収納場所を一カ所にまとめることで、生活動線がシンプルになり家事の効率化も図れますので、リビングの側やランドリールームの側など配置場所を考えてみましょう。
新築の収納の注意点3つ
新築の収納の注意点をまとめていますので、内容を把握して生活を始めてから後悔がないような設計プランを目指して下さい。
必要以上の収納量になっていないか確認する どのような収納タイプにするかを確認する 収納扉の必要性を確認する
順番に解説します。
必要以上の収納量になっていないか確認する
一つ目の注意点は、必要以上の収納量になっていないかを確認することです。
予算に制限のある家づくりでは、収納スペースと居住スペースはトレードオフの関係にありますので、自分たちに必要な収納量と配置場所を見極める必要があります。
どのような収納タイプにするかを確認する
どのような収納タイプを選ぶかも注意すべきポイントの一つです。
壁付けタイプやウォークインタイプなど、間取りや使い勝手を考えて最適な収納プランを家族で相談して下さい。
収納扉の必要性を確認する
収納扉の必要性を確認することも忘れてはいけません。
収納の配置場所によってはオープンクローゼットを設けることで、通気性の確保や部屋を広く見せる効果に期待できます。
予算の削減にも繋がりますので、収納扉を省けないかを検討してみましょう。
まとめ:新築の収納を理解してうまく空間を活用しよう
新築の収納プランを考える上では、適切な収納量を使い勝手の良い場所に配置することが快適な生活に繋がります。
収納が広すぎれば居住スペースを圧迫しますし、使い勝手が悪ければ使用頻度が減り、費用の無駄にもなりかねません。
自分たちに必要な収納スペースと適切な配置を理解した上で、空間を有効利用して理想の住まいを目指しましょう。
建匠では、ご家族にあったオンリーワンの住宅を提案しています。収納スペースの配置など建築プランでお悩みの方は、お気軽にモデルハウスへ足をお運び下さい。
マイホーム購入を検討する上で、どのように予算を決めるかは頭の痛い問題です。
住宅取得費用は高額であり、手元資金だけで賄うことは現実的ではありませんので、多くの方が住宅ローンを利用しています。
住宅ローンは借金なので、どのように返済するかを考えねばならず、借入金額の決定には多角的な視点が必要です。
そこで今回は、年収500万円の住宅ローンはいくら借りられるかについて解説します。借入額の決定に不安を感じている方は、ぜひとも最後までお付き合い下さい。
年収500万円の住宅ローンの借入可能額
年収500万円の住宅ローンの借入可能額の目安を、『2020年度 フラット35利用者調査』を用いて、以下の項目に沿って見ていきます。
借入可能額が返済可能額とは限りませんので、予算を決める上での目安に留めて下さい。
・年収倍率から考える借入可能額
・返済負担率から考える借入可能額
順番に解説します。
年収倍率から考える借入可能額
年収倍率は住宅取得費用が年収の何倍に相当するかを比率で表したもので、5〜7倍が適切な倍率といわれており、全国平均の数値は6.7倍となっています。
年収500万円の場合、借入可能額は2,500〜3,500万円を目安にするとよいでしょう。
ただし、頭金を含めた金額をもとにしているので、単純にこの数値だけで借入額を決めることはおすすめできません。
返済負担率から考える借入可能額
返済負担率は年収に占める住宅ローンの年間返済額の割合のことであり、20〜25%が適切な割合といわれ、全国平均の数値は22.2%となっています。
年収500万円の場合、月々の返済額は8.3〜10.4万円となりますので、家計の収支を洗い出した上で、無理なく返済できるラインを見極めて借入額を検討しましょう。
フラット35の基準で見ると、年収500万円の返済負担率は35%が上限であり、月々の返済額は14.5万円となり、一般的な目安と比較して開きがあることに注意して下さい。
年収500万円の住宅ローンの借入額を決めるポイント
年収500万円の住宅ローンの借入額を決めるポイントをまとめています。最適な借入額の判断は、家計の状況や家族構成などケースバイケースなので、自分たちの暮らしに合った返済プランをたてることが重要です。
・住宅ローンの借入額は年収の5倍~6倍程度にする
・一般的な返済負担率の平均値から考える
・年収500万円の人が用意する頭金の平均額を参考にする
順番に解説します。
住宅ローンの借入額は年収の5倍~6倍程度にする
年収倍率
注文住宅
6.7倍
土地付き注文住宅
7.4倍
建売住宅
6.8倍
マンション
7倍
中古戸建て
5.5倍
中古マンション
5.8倍
※『2020年度 フラット35利用者調査』より
一つ目のポイントは、住宅ローンの借入額を年収の5〜6倍に留めることです。
上記の表は、建物種別ごとの年収倍率をまとめており、平均数値ではありますが、多くの方が5〜7倍程度に借入額を留めていることが分かります。
頭金次第ではあるものの、十分に返済可能なラインであると考えてよいでしょう。
一般的な返済負担率の平均値から考える
返済負担率
注文住宅
20.8%
土地付き注文住宅
24.1%
建売住宅
23.1%
マンション
21.7%
中古戸建て
19.7%
中古マンション
19.6%
※『2020年度 フラット35利用者調査』より
一般的な返済負担率の平均値から考えることもポイントの一つです。
上記の表は、建物種別ごとの返済負担率の平均値をまとめたもので、目安である20〜25%以内に留まっています。
審査基準は30〜35%ですが、上限に近い借入は適切な返済プランとはいえませんので、自分たちが無理なく返済できるラインを把握することが重要です。
注意点として、返済負担率の計算には他の借入も含まれますので、自動車ローンや奨学金などの返済状況を把握しておかなければなりません。
年収500万円の人が用意する頭金の平均額を参考にする
年収500万円の人が用意する頭金の平均額を参考にすることも借入額を決めるポイントです。
頭金の目安は住宅取得費用の1〜2割程度とされていますが、具体的な金額が気になる方も多いでしょう。
2020年度のフラット35利用者調査を見ると、世帯年収602万円で頭金を404万円用意していることが分かります。
頭金の有無は借入額に直結する問題なので、現在の手元資金をもとに予算を決めるとよいでしょう。
金利パターンから考える年収500万円の住宅ローン
住宅ローンは借入金額が高額であり、返済期間も長いため、金利プランの選択も借入額を決める判断に影響を与えます。それぞれの金利タイプの特徴を把握して、自分たちに合ったプランを選びましょう。
・変動金利型の住宅ローン
・固定金利期間選択型の住宅ローン
・固定金利型の住宅ローン
順番に解説します。
変動金利型の住宅ローン
変動金利型は返済途中に定期的に金利が見直されるタイプのローンです。
半年ごとに金利が見直され、毎回の返済額についても、元利均等返済では5年ごと、元金均等返済は金利変動に伴い見直されます。
他のタイプに比べ金利が安いものの、返済開始時に総返済額がいくらになるか分からないため、金利の動向に注意が必要です。
固定金利期間選択型の住宅ローン
固定金利期間選択型は契約時に固定期間を選び、期間終了後に変動金利型へ移行または、再度固定期間を選択できるタイプのローンです。
変動金利型同様に、契約時点では総返済額が分からないものの、固定金利期間中は金利が変わらず、期間が短いほど当初の金利が低くなります。
固定金利型の住宅ローン
固定金利型は返済途中で、借入開始時の金利が変動しないタイプのローンです。
借入開始時点で総返済額が確定するため、返済プランを立てやすいものの、変動金利型に比べると金利が高めに設定されていることが特徴といえます。
今よりも金利が下がる見通しは少ないので、ある意味では理想的な住宅ローンといえますが、金利上昇のリスクを取れば、支払額を抑えられるので、判断が難しいところです。
年収500万円の住宅ローンの返済シミュレーション
年収500万円の住宅ローンの返済シミュレーションを以下のケースごとにまとめています。自分たちの家計の状況を見極めて、無理のない返済プランを立てて下さい。
※返済期間35年、元利均等返済、固定金利1.44%・変動金利0.65%でそれぞれ算出
・年収倍率5倍のケース
・返済負担率25%のケース
・返済期間ごとのケース
順番に解説します。
年収倍率5倍のケース
借入額
総返済額
月々の返済額
固定金利
2,500万円
3,185万円
7.6万円
変動金利
2,500万円
2,796万円
6.7万円
年収倍率を5倍とした際の借入額は2,500万円となり、返済プランは上記の表の通りです。
金利タイプによる返済額の差はありますが、家計にゆとりを持たせたプランといえるでしょう。
他の借入が多く、手元資金が手薄な場合は、月々の返済額を抑えることが望ましいので、借入予算の決定は慎重に対応して下さい。
返済負担率25%のケース
借入額
総返済額
月々の返済額
固定金利
3,429万円
4,368万円
10.4万円
変動金利
3,429万円
3,835万円
9.2万円
返済負担率25%では、借入額は3,429万円となり、返済プランは上記の表の通りです。
年収500万円の手取り月収は約33万円なので、約3割が返済に回る計算となりますが、税金や修繕費用の積み立てなどマイホームの維持費についても考えなければなりません。
生活費などの出費は人それぞれですが、教育費や老後の蓄えを貯金することを考えると、これ以上借入を増やさない方がよいでしょう。
返済期間ごとのケース
借入額
総返済額
月々の返済額
返済期間30年
3,429万円
4,225万円
11.8万円
返済期間25年
3,429万円
4,086万円
13.7万円
上記の返済負担率25%のケース(固定金利)で、返済期間を短く設定した結果は表の通りです。
返済期間を10年短く設定すると、総返済額は282万円下がるものの、月々の返済額は3.3万円増えるので、家計への負担は大きなものとなるでしょう。
返済期間を決める際は、定年を迎えるまでに完済できるようにするなど、注意すべき点は返済額だけではありません。
年収500万円の住宅ローンに関するよくある質問
年収500万円の住宅ローンに関するよくある質問をまとめています。借入額の決定に悩まれてる方は、他の方の疑問点を自分たちに置き換えて考えてみましょう。
・住宅ローンを最大借入可能額まで借りない方がいい?
・年収500万円で住宅ローンを借りる場合どんな生活になる?
・金融機関の審査では年収以外に何が基準になる?
順番に解説します。
住宅ローンを最大借入可能額まで借りない方がいい?
後々の返済のことを考えると、上限近くまで借りることはおすすめできません。
収入は増えることもあれば、減ることもありますので、過度の借入は返済プランの破綻に繋がる可能性があります。
また、金利の上昇により返済額が増えることも想定されますので、余裕を持った返済プランを立てることが重要です。
年収500万円で住宅ローンを借りる場合どんな生活になる?
どんな生活になるかは人それぞれではありますが、平均年収よりも高いので、支出に気を付けておけば問題はないでしょう。
現在の年齢・家族構成・生活レベルを加味した上で、家計の収支を洗い出して、無駄な出費をできるだけ減らす努力が求められます。
金融機関の審査では年収以外に何が基準になる?
金融機関の審査は収入だけでなく、総合的に判断されるものです。
具体的には、健康状態・勤続年数・完済時の年齢・その他の借入状況などが挙げられます。
また、金融機関によっても審査の基準が異なることに注意が必要です。
まとめ:年収500万円の住宅ローンの借入額を知って資金計画を進めよう
マイホームの購入において、予算決めは難しい問題です。初めての家づくりではあれもこれもと要望が多く、予算が増えていきがちですが、過度な借入は快適な暮らしの妨げとなります。
まずは、年収500万円の住宅ローンの一般的な借入額を把握した上で、自分たちの家計に合わせた資金計画を立てることが重要です。
過度な借入により、返済に追われる状況では、快適な暮らしは実現できません。
建匠では、お客様の状況に合わせて、建てた後に困らない資金計画を提案しています。マイホームの資金計画にお悩みの方は、お気軽にモデルハウスへ足をお運び下さい。
離婚するときに住宅ローンの支払いはどうなるのか?という疑問を抱えている人は少なくありません。
そこで実際に離婚するとなると、財産分与のときに住宅ローンはどのような扱いになるのでしょうか。
本記事では離婚時に住宅ローンの支払いがどうなるかを解説し、離婚時にローンが残っているときに考えられるリスクについても紹介します。
そもそも住宅ローンが残っている場合に離婚できる?
「住宅ローンの残債があると離婚できない」と考える人は多いです。
しかし、住宅ローンの残債があったとしても離婚することは可能です。
離婚時に住宅ローンの支払いはどうなる?
離婚時には財産分与や法的な手続きを数多く行う必要がありますが、住宅ローンはどのように処理するのでしょうか。
・離婚後の支払い義務は住宅ローンの名義人
・住宅ローンは財産分与の際に折半しなくてよい
ここでは上記の2点について解説します。
離婚後の支払い義務は住宅ローンの名義人
住宅ローンの残債の支払い義務は、ローンの名義人です。
住宅ローンの名義人のパターンは、以下の5つに分かれます。
・夫の単独名義
・夫の単独名義で妻が連帯保証人
・妻の単独名義で夫が連帯保証人
・夫婦共同名義の連帯債務
・夫婦それぞれが名義人となって、ローンを組むペアローン
いずれのパターンでも、名義人に住宅ローンの支払い義務があるので、ローンの名義人を確認する必要があります。
名義人を確認するためには、ローンを契約した金融機関に問い合わせてみましょう。
住宅ローンは財産分与の際に折半しなくてよい
離婚するときには財産分与を行います。
財産分与とは夫婦が共同生活を送るときに形成した財産を公平に分けることをいい、対象となるのは不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
しかし、住宅ローンに関しては財産分与の対象でないため、折半する必要がありません。住宅ローンは折半したとしても同額ずつ払って返済できるものではないためです。
ただし、折半せずに離婚した場合は名義人の負担だけが重くなってしまうので、住宅ローンの残債は50%に当たる金額を支払うことが一般的です。
【ケース別】離婚時に住宅ローンが残っている場合の返済方法
住宅ローンは性質上、契約形態によって双方が同額ずつ返済できるものではありませんが、離婚後に残債の半額に当たる金額を支払います。
離婚後の返済方法は以下の3つのパターンで異なります。
・離婚後に夫(名義人)が住むケース
・離婚後に妻(非名義人)が住むケース
・離婚時に支払い途中の家を売却するケース
それぞれのパターンで返済方法や対策を解説します。
離婚後に夫(名義人)が住むケース
離婚後に名義人が住むケースは、自分で家のローンを払い続けるのと同意義で、最もトラブルが起きにくいです。
ただし、住宅ローンの名義が単独名義に設定されているかを注意する必要があります。住宅ローンの連帯保証人に配偶者が設定されていると、名義人の返済が遅れてしまったときに、配偶者に支払い命令が下ります。
そのため、連帯保証人を外すか別の親族に変更して対策しましょう。
離婚後に妻(非名義人)が住むケース
離婚後に非名義人が住むケースは、名義人が自分の家のローンを支払っているわけではないため、トラブルが起こりやすく、また手続きも煩雑です。
そのため、あまりおすすめできる返済方法ではありません。
非名義人が家に住み続ける場合、住宅ローンを他の銀行で借り換えて、妻名義にするという返済方法が考えられます。しかし、収入面で難しい条件をクリアしなければならないため、あまり現実的ではありません。
また、非名義人が連帯保証人となっている場合は、連帯保証人の設定を外す必要があります。連帯保証人を外れるにはローンを完済するか、別の金融機関で借り変えましょう。
夫婦それぞれでローンを組むペアローンを組んでいる場合は、単独名義に変更できるか確認しましょう。単独名義に変更できるか確認するには、住宅ローンを借り入れている金融機関に相談します。
単独名義に変更できる条件を満たしていれば、審査に通過した後に、単独名義に変更できます。
離婚時に支払い途中の家を売却するケース
離婚時にローンが残っている状態で、家を売る際には「アンダーローン」か「オーバーローン」かによって対応が変わります。
アンダーローンとはローンの残債よりも家の売却額が高くなることをいいます。住宅ローンを完済でき、財産分与もスムーズに進むため理想的なパターンです。
アンダーローンの場合では売却したお金をローンの返済に充て、もしお金が余った場合には財産分与の対象として、夫婦で分けることができます
オーバーローンとはアンダーローンの反対で、ローンの残債よりも売却額が低いことをいいます。通常不動産を売却するときにはローンを完済して、抵当権を外す必要があります。
しかし、オーバーローンの場合、抵当権を外せられないので、通常の方法では売却できません。
そのため、オーバーローンだと判明したときには自己資金を使って、売却額と合わせてローンを完済するか、任意売却を行って不動産を売却します。
ローンを完済できない場合でも自己資金で補って完済できるのであれば、不動産を売却できます。
また、住宅ローンが残っている状態でも金融機関の合意を得て任意売却をすることで、抵当権が設定されている不動産を売却できます。
離婚時に住宅ローンが残っている場合のリスクと対策
離婚時に住宅ローンが残っていると以下のようなリスクがあります。
・連帯保証人として支払い義務が発生
・家を勝手に売却されてしまう
・使用期限を超えても家を退去しない
・再婚によって住宅ローンの支払いが滞る
ここではリスクについて解説し、それに対処する方法も紹介します。
連帯保証人として支払い義務が発生
仮に妻が連帯保証人に指定されていると、夫のローンの返済が滞ってしまったときに、妻側に支払い義務が発生します。返済が滞った段階で金融機関は連帯保証人に対して返済を要求するでしょう。
対策としては、離婚前に連帯保証人から外れるようにしましょう。連帯保証人を外れるためには名義人の親族で新しい保証人を立てるか、連帯保証人なしで他の金融機関に借り換える方法があります。
ただし、いずれの方法もクリアするのが難しいため、クリアできなかったときのために「公正証書」を作成するのがおすすめです。
公正証書に強制執行許諾事項を記載することで、あらかじめ決めたおいた義務を履行しなかったときに、相手方の財産の差し押さえを強制執行できます。
家を勝手に売却されてしまう
ローンの非名義人が家に住み続ける場合、名義人が勝手に家を売却するリスクがあります。家が売却されてしまうと、所有権が他人に移るので、当然非名義人は住み続けることはできなくなってしまいます。
対策としては、不動産の名義を非名義人に変更することが理想的です。名義変更が難しい場合には離婚協議書を作成して、所有権を手放さないことを記載しましょう。
使用期限を超えても家を退去しない
非名義人を家に住み続けさせる場合は名義人にもリスクがあります。
よくある例としては、子どもが中学生になるまでの間は無料で住み続け、それ以降は引越すという取り決めをしても、使用期限を越えて家を退去しないというケースがあります。
対策として、使用期限を定める場合は離婚協議書に期間や権限の内容を記載しておきましょう。
再婚によって住宅ローンの支払いが滞る
非名義人である妻が家に住み続けて、名義人の夫がローンの支払いを続けるような場合では夫側が再婚するに伴って、ローンの支払いが滞ってしまうことが頻繁にあります。
住宅ローンの返済は金額も大きく、長期間にわたるため、夫側が再婚すると新しい家庭に資金を優先したいため、住宅ローンの返済を止めてしまうことが多くあります。
支払いが滞ってしまうと、家を差し押さえられ、強制的に退去することになり、急に住む場所がなくなる可能性があります。
ローンの返済が滞るのを防ぐには離婚協議書を作成し、離婚時の話し合いを公的な記録で残しておきましょう。ローンの支払い義務について明記しておくと、支払いが滞った際でも相手に支払いを要求できます。
離婚時に住宅ローンが残っている場合にやるべきこと
離婚時に自分がローンの名義人や連帯保証人の場合、以下の4点について確認しておきましょう。
・家の名義人を調べる
・離婚時の家の価値を調べる
・住宅ローンの残債額を調べる
・住宅ローンを組んだ銀行に連絡する
あらかじめやるべきことを確認しておくと、後々トラブルを避けられるので、話し合うのが気まずかったとしても把握しておきましょう。
家の名義人を調べる
非名義人が所有者移転登記をしないまま離婚後に家に住み続ける場合、不利な立場におかれてしまいます。
なぜなら、家の名義人は勝手に家を売ることができますし、名義人に万が一のことがあった場合、相続人に家が相続されてしまうからです。
その場合、離婚時には家の名義人を調べておきましょう。名義人を調べるには法務局で登記簿謄本を取得すると知ることができます。
離婚時の家の価値を調べる
離婚時に家を売却する、しないに関わらず、家の価値がいくらなのかを知っておくことは重要です。
家の価値を知っておくと、万が一家を売らなければいけない状況になったときに住宅ローンを完済できるかを把握できます。
住宅ローンの残債額を調べる
上記と似ていますが、家を売ったときにアンダーローンかオーバーローンになるのか判断できるため、ローンの残債額を調べるのは重要です。
残債額を確認する方法は主に3つあります。
1つ目は返済予定表を確認することです。返済予定表は契約当初に郵送される書類で、ローンが返済されるまでのスケジュールが詳細に記載されています。
2つ目の方法はローンを借り入れている金融機関のウェブサイトでローンの残債額を確認できます。銀行のインターネットサービスに加入している場合、いつでも残債額を把握できます。
3つ目の方法は残高証明書を確認することです。契約時に毎年郵送されるように設定していると10〜11月に設定した住所に書類が届きます。
住宅ローンを組んだ銀行に連絡する
銀行に知らせる前に離婚をしてしまうと、ローンによっては契約違反となる可能性があります。
契約違反になったからといって、一括返済が求められる訳ではありませんが、離婚する前に住宅ローンを組んだ銀行に連絡して、今後の返済計画について相談しておきましょう。
離婚時に住宅ローンを支払ってもらう方法
住宅のローンは離婚したとしても支払い続ける必要があります。
ただし、非名義人が住むケースでは名義人が支払いを拒んでしまうことがあるため、あらかじめ対策しておきましょう。
・一括で残債分を支払ってもらう
・公正証書を作成する
・連帯保証人を外れる
離婚時に住宅ローンを支払ってもらう方法は上記の3つがあります。
一括で残債分を支払ってもらう
住宅ローンの支払いは長期間に渡るため、相手方の都合によって支払われないことがあります。
そこで、離婚時にローンの50%に当たる金額を一括で受け取っておくと、後々トラブルを防ぐことができます。
多額の現金が要求されるため、簡単な方法ではありませんが、資金に余裕がある場合はこの方法を採るのがおすすめです。
公正証書を作成する
公正証書を作成すると、住宅ローンの支払いが滞った際に財産の差押えを強制執行できます。
ローンの支払いを催促できるので、配偶者がローンの支払ってくれるか不安な人は作成しておきましょう。
連帯保証人を外れる
住宅ローンの連帯保証人として指定されていて、相手が家を取得するようなときは、連帯保証人を外しておくと安心です。
新しい連帯保証人と金融機関の了承を得る必要がありますが、連帯保証人が外れたら、名義人の支払いが滞ったとしても、ローンの支払いを要求されることはなくなります。
離婚時の住宅ローンに関するよくある質問
離婚時の住宅ローンについて説明しましたが、ここでよくある質問について解説します。
・住宅ローンで離婚できないケースはある?
・離婚時に住宅ローンは養育費と相殺できる?
・離婚時に住宅ローンの名義変更はできる?
・離婚時に住宅ローンは借り換えできる?
・離婚しても今の家に住み続けられる?
上記の質問について回答します。
住宅ローンで離婚できないケースはある?
住宅ローンは財産分与の対象ではないため、トラブルに発展しやすく離婚できない原因となることがあります。
離婚できないケースとして多いのは、夫婦でペアローンを組んでいることです。
住宅ローンには「ローンの名義人と家の居住者が同じである」という規約があり、ペアローンを借りている状態だと離婚することができません。
離婚するにはペアローンを借りている金融機関から別の金融機関に借り換える必要がありますが、残債額が高額であれば審査に通過しにくくなり、離婚できなくなってしまいます。
離婚時に住宅ローンは養育費と相殺できる?
夫婦間で合意を得ていれば、住宅ローンの支払いを養育費代わりにすることが可能です。
離婚時に住宅ローンの名義変更はできる?
基本的に住宅ローンの名義変更は難しいですが、離婚時においては可能です。ただし新名義人側に返済能力があるときに限ります。
新名義人に返済能力があると金融機関が判断すれば、住宅ローンの名義を変更できます。
離婚時に住宅ローンは借り換えできる?
離婚時に住宅ローンを借り換えることは可能です。
名義変更ができない場合は借り換えを検討しましょう。
離婚しても今の家に住み続けられる?
離婚しても家に住み続けることは可能です。
家に住むのが名義人か非名義人かで必要になる手続きが変わるので、住宅ローンの名義が誰になっているのか確認しましょう。
まとめ:離婚時の住宅ローンはリスクをしっかり把握しておこう
離婚にはさまざまな手続きが必要になり、精神的な負担となります。
特に住宅ローンが残っている家をどうするかという問題を解決するには時間がかかります。離婚することになったら、家の価値や名義人を調べて、どのように対応するかを把握しておきましょう。
建匠では、住みやすい住宅を提供するだけでなく、お客様の資金計画のお手伝いもしております。どんなに些細なお悩みについてもお客様に寄り添ってご対応いたします。
お気軽にご相談ください。
家づくりにおいて、家族構成や子供の成長などを考え、生活空間が確保しやすい3階建て住宅を検討している人は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、3階建て住宅のメリットやデメリット、後悔しないためのポイントを詳しく解説していきます。
「3階建て住宅って実際、住みやすいの?」
上記のような疑問を持っている方は、ぜひ本記事を最後までご覧くださいませ。
そもそも3階建て住宅とは?
3階建て住宅とは、3つのフロアがある住宅のことです。
3階建て住宅は2階建て住宅と異なり建築費用が割高になり、災害時の安全性を確保するために「構造計算書」の提出が義務になっています。
主に3階建ては地方の広い土地に建てるケースは少なく、都市部の住宅が密集した地域に、居住スペースを確保するために建てることが多いです。
3階建て住宅のメリット4つ
3階建ての住宅は狭い土地だったとしても有効活用できますが、他にもメリットはあります。
ここでは、以下4つの3階建て住宅のメリットについて解説します。
・日当たりや見晴らしが良好
・風通しが良好
・フロアごとに生活空間を工夫できる
・狭い土地でもスペースを確保できる
3階建て住宅のメリットを知って、これからの家づくりの参考にしてみてください。
日当たりや見晴らしが良好
3階建て住宅の大きな魅力は「見晴らし」にあります。
3階部分にバルコニーやベランダを設けることで2階建ての家とは違った景色を楽しむことができます。
さらに屋上を作ることで、広く街を見渡すことができ、開放感を味わえるでしょう。
風通しが良好
3階建ての住宅は高い位置にあるので、風通しが良くなります。
さらに窓の配置を工夫することで、より快適な風通しを実現できるでしょう。
周囲にある建物や家の向きによって風向きは変わるので、設計段階で風通しがどのように変化するか話し合いましょう。
フロアごとに生活空間を工夫できる
3階建ては3つのフロアがあるので、1階はお風呂などの水回り、2階はリビング、のようにフロアごとに生活空間を分けることができます。
階ごとに壁紙や床の色を変えることができるので、同じ家の中でもフロアごとに雰囲気をガラッと変化させられます。
1階部分は親世帯の家、2階以上は夫婦と子どもの家というように2世帯住宅に活用することもできます。
狭い土地でもスペースを確保できる
3階建て住宅最大のメリットは「土地を最大限に活用できる」ことです。
土地には建ぺい率、容積率といって建てられる家の大きさがあらかじめ決められています。
2階建て住宅の多くは土地の条件を生かし切れておらず、有効活用できていないことが多いです。
しかし、3階建て住宅では土地の条件が許す限り上に伸ばすことができ、居住スペースを増やすことができるため土地の条件を有効活用できます。
3階建て住宅のデメリット3つ
3階建て住宅には多くのメリットがあり、都市部に家を建てるのであれば利便性も高くおすすめですが、反対にデメリットもあります。
3階建て住宅には以下の3つのデメリットがあります。
・家事動線や生活動線が不便
・建築費用が割高になる
・冷暖房効率が悪く電気代もかかる
デメリットを補うような対策も解説するので、3階建て住宅を検討している人は参考にしてみてください。
家事動線や生活動線が不便
3階建て住宅はそれぞれのフロアで生活空間を分けられますが、フロアを行ったり来たりする手間がかかってしまいます。
たとえば、1階にある洗濯機を回している間に2階のキッチンで洗い物をして、洗濯が終わったら1階に取りに行き、洗濯物をまた2階に持っていくというような手間が発生します。
また階段での移動が多いため、老後の生活では負担に感じるかもしれません。
そのため、洗濯物を置く場所と干す場所を同じフロアにするなど、生活動線をなるべく短くするような間取りにするのがおすすめです。
建築費用が割高になる
3階建ての住宅は2階建て住宅に比べて以下の費用が追加でかかります。
・構造計算費用(約20万円)
・地盤改良費用(約70万円)
・2箇所の階段設置費用
・地震対策費用
上記の費用が追加でかかるので、建築費用は割高になってしまいます。
建築費用を抑えるには、デザインをシンプルにする方法があり、凹凸の少ない箱形のデザインであれば費用を抑えることができます。
また水回り設備の配置をまとめたり、設備のグレードを上げすぎたりしないなど、工夫すれば建築費用を抑えることができます。
冷暖房効率が悪く電気代もかかる
3階建て住宅で冷暖房を効かせようとすると3フロア分の電気代とエアコンなどの設備が必要です。
さらに、空気は暖かければ上に向かいますが、冷たければ下の方に貯まります。
そのため、夏は3階部分の日当たりが良く、家全体の暖かい空気が上に集まるため3階が暑くなります。
反対に冬には下の方に冷たい空気が集まり、日当たりも悪いので1階は寒くなってしまうでしょう。
季節によってフロアごとの温度が変化するので、2階をメインで過ごす空間にするなどの工夫が必要です。
3階建て購入で後悔しないためのポイント4つ
3階建て住宅を建てるときには後悔しないためのポイントを押さえることが大切です。
後悔しないためのポイントは以下の4つです。
・自分の地域の建築規制を調べる
・耐熱性を上げる
・間取りを工夫する
・実績のあるハウスメーカーに依頼する
ポイントを押さえて、理想の3階建て住宅をつくりましょう。
自分の地域の建築規制を調べる
3階建て住宅を建てる前に、住みたいエリアの建築規制を確認してから土地を購入しましょう。
住む地域によって建てられる建物の制限が異なり、制限に該当すると天井が低くなったり、部屋数を確保できなかったりすることがあります。
耐熱性を上げる
3階建て住宅は夏暑く、冬寒くなりやすいので断熱性能を高めることがおすすめです。
特に3階部分は熱が集まりやすいので、断熱材を厚くするなど、工夫しましょう。
間取りを工夫する
3階建て住宅は階段の行き来が多くなるので、家事動線を考えて間取りを工夫しましょう。
将来どのような生活を送るかをイメージしながら、間取りを設計することで老後も暮らしやすい家を作ることができるでしょう。
実績のあるハウスメーカーに依頼する
3階建ての住宅が得意なハウスメーカーであれば、地域の規制や土地の条件を考慮しながらも暮らしやすい建築プランを提案してくれます。
モデルハウスなどの建築実例も見られるので、実際の生活をイメージしやすくなるでしょう。
3階建て住宅の施工実例
ここでは、建匠で取り扱った3階建ての施工実例を紹介します。
3階建て住宅を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
開放的な屋上バルコニーでいつでもリゾート気分なお家
建匠では3階建て住宅を提供しており、朝倉米田にリゾート住宅を完成させました。
1階に居室を3部屋とトイレを、2階にLDKとバス・トイレをおいて生活動線が工夫された作りになっています。
また、3階部分は屋上となっており、いつでも大空を見渡すことができる住宅になっています。
開放的な屋上バルコニーでいつでもリゾート気分なお家♫
3階建て住宅に関するよくある質問4つ
家づくりは多額の資金が必要になるため、慎重に計画を進めていかなければなりません。
ここでは、3階建て住宅に関するよくある質問について解説します。
・木造3階建て住宅は危ないって本当?
・3階建て住宅は売れない?
・3階建て住宅はやめた方がいい?
・3階建て住宅で隣人トラブルが起きることはある?
3階建て住宅に関する上記4点の疑問を解消して、家づくりを成功させましょう。
木造3階建て住宅は危ないって本当?
結論、木造3階建て住宅は危ないというのは事実ではありません。
3階建て住宅は2階建て住宅よりも揺れやすいため、耐震性を高めるために、地震に強い材料を使うのがおすすめです。
耐震性能の高い材料を使用することで大幅なコストアップにつながると考えられがちですが、2022年現在では手頃な価格で入手できます。
これらの材料をうまく活用すれば、優れた耐震性能のある家を実現できるでしょう。
3階建て住宅は売れない?
3階建て住宅は2階建てに比べて室内の上下の移動が多いため、売れにくいと言われていますが、それは立地によります。
3階建ては立地を買うとも言われており、周囲に3階建てが多い都市部では立地が良いため売れやすいです。
売却を見据えて3階建てを建てるのであれば、なるべく立地の良い土地に建てることをおすすめします。
3階建て住宅はやめた方がいい?
ネット上で3階建て住宅の評判は良いものばかりではないですが、土地の利便性や日当たりなどを考えるとやめておいた方がいいということはありません。
土地が狭かったとしても居住空間を広げることができ、なおかつ利便性の高い地域に住むことができるので、メリットは大きいといえるでしょう。
3階建て住宅で隣人トラブルが起きることはある?
3階建て住宅は周囲の住宅に比べて高くなるため日当たりを巡って、隣人トラブルが起きるのではないかと思われがちです。
しかし、隣人の資産価値は下がるわけではなく、北側の家の日当たりも工夫することができるため、トラブルを未然に防ぐことはできます。
まとめ:3階建て住宅のメリットを理解して後悔しない家づくりを
3階建て住宅には2階建てにはないメリットが多くあり、開放的な暮らしを実現できます。
一方でデメリットもあるため、デメリットを抑えるような設計や間取りにする必要があります。
設計や間取りを工夫して、快適な家を作りましょう。
建匠は家族の思いを込めたオンリーワンのお家づくりを提案しています。
賃貸住宅に満足できない方は、お気軽にモデルハウスへお越し下さいませ。
家を買うというのは大きな買い物なので、いつ買えば良いのか悩む人も少なくありません。
本記事では、家を買う人の平均年齢や年収について解説し、それぞれの年齢で家を買った時のメリット・デメリットについても紹介します。
家の購入を検討している人は参考にしてみてください。
そもそも家を買う人の平均年齢とは?
家を買うタイミングは「結婚を機に」「子供が生まれたときに」という人が多いですが、家を買う年齢の目安は知っておきたいものです。
ここではフラット35の「利用者調査」の内容を参考に以下の2つについて解説します。
・家を買う人の平均年齢
・家を買う人の平均年収
家を買う年齢や年収を知って、マイホーム購入の参考にしてください。
家を買う人の平均年齢
最初に、家を買う人の平均年齢について、フラット35「利用者調査」を基に解説していきます。
20~29歳
30~39歳
40~49歳
50~59歳
60~64歳
65歳~
平均年齢
全国
15.3%
41.0%
25.4%
12.0%
3.5%
3.8%
40.3歳
東京都
12.7%
39.2%
27.8%
12.8%
3.6%
3.7%
41.0歳
高知県
15.1%
42.7%
30.2%
7%
1.6%
3.2%
38.9歳
引用:フラット35「利用者調査」
いずれの地域においても30代で購入した人が一番多く、その次に40代の人が多いです。
全国の世帯主の平均年齢は40.3歳で、東京も同じような平均年齢となっています。
しかし高知県では家を購入する平均年齢が38.9歳となっていて、全国平均と比べると少し若い人が建てる傾向にあります。
家を買う人の平均年収
次に、家を買う人の平均年収について、フラット35「利用者調査」を基に解説していきます。
400万円以下
400~600万円
600~800万円
800~1,000万円
1,000~1,200万円
1,200~1,400万円
1,400万円以上
平均年収
全国
38.0%
37.8%
13.7%
5.1%
2.1%
1.1%
1.9%
515万円
東京都
25.1%
38.5%
18.6%
8.4%
3.9%
2.1%
3.4%
606万円
高知県
42.4%
38.9%
10.9%
1.2%
0.3%
1.9%
0.9%
464万円
引用:フラット35「利用者調査」
家を買う人の平均年収は全国と高知県では400万円以下という人が最も多く、次に400~600万円の人が多いです。
東京では400〜600万円という人が一番多く25.1%です。
その次に多いのが400万円以下となっているので、全国のデータとは少し異なります。
家を購入するときに、住宅ローンの利用は不可欠ですが、ローンを組むときには自分の年収から逆算して、余裕のある返済計画を練らなければいけません。
家を買う年齢は30歳が理想的
上の表を見ても分かる通り、家を買う年齢に一番適しているのは「30代」です。
住宅ローンには金融機関によって完済年齢が決まっており、75〜80歳までを目安に完済する期限を設けています。
そのため住宅ローンの返済期間を35年として、70歳までに完済したいと考えると35歳で住宅ローンを契約する必要があります。
返済期間をなるべく長くしたいので、30代でマイホームの購入を決める人が多くなるのでしょう。
また30代では20代の人と比べると生活が安定しており、結婚して家族が増えている人もいます。
そのため今までに住んでいた家が手狭になり、マイホームの購入へと踏み切る人も多いです。
【年齢別】20代で家を買う場合のメリット・デメリット
20代では結婚を機にマイホームを購入する人が多いです。ここでは20代で家を購入するメリット・デメリットについて解説します。
・20代で家を買う場合のメリット
・20代で家を買う場合のデメリット
20代で家を買う場合のメリット
20代で家を購入するメリットは以下の2つです。
・定年退職前に住宅ローンを完済できる
・ペアローンが組みやすい
【定年退職前に住宅ローンを完済できる】
20代で家を購入する大きなメリットは定年退職前に住宅ローンを完済できることです。
例えば25歳で35年ローンを組んだとすると60歳で完済できます。
所属する会社によって役職や定年退職の年齢などは変わりますが、完済後は老後の資金を蓄えられるでしょう。
【ペアローンを利用しやすい】
住宅ローンを借り入れるときに年収が低いとローンを組めないことがあります。
そんなときはパートナーの年収を合算してペアローンを組むことを考えてみましょう。
夫婦で利用するペアローンでは2人の年収を合算した金額で住宅ローンが借りられるので、購入する家の選択肢が多くなります。
金融機関によっては結婚前でも婚約していれば合算できるという場合もあるため、相談してみましょう。
20代で家を買う場合のデメリット
20代で家を購入するデメリットは以下の1つです。
・家族の人数が増える可能性が高い
夫婦2人と子ども1人の3人家族を想定して家を購入すると、思いがけず子供が2人生まれて家が手狭になってしまうことがあります。
そのため、少し広めの家を購入することをおすすめします。
【年齢別】30代前半で家を買う場合のメリット・デメリット
30代は結婚や出産を迎える人も多く、家を購入する適齢期です。
ここでは30代前半で家を購入するメリット・デメリットについて解説します。
・30代前半で家を買う場合のメリット
・30代前半で家を買う場合のデメリット
30代前半で家を買う場合のメリット
30代前半で家を買うメリットは以下の2つです。
・購入できる家の選択肢が増える
・家賃を節約できる
【購入できる家の選択肢が増える】
30代では20代の人と比べると仕事と収入が安定していて、購入できる家の選択肢が増えます。
仕事によっては年収500万円を超える場合も多く、ペアローンを利用するとさらに希望に近い家を購入できるでしょう。
【家賃を節約できる】
賃貸住宅ではいくら家賃を払ったとしても自分の資産になることはありません。
ライフスタイルによっては賃貸住宅に住み続けるほうが良いこともありますが、家賃が無駄になってしまうと考えることもできます。
30代で家を購入すると、早期に自分の資産を作ることができます。
30代前半で家を買う場合のデメリット
30代前半で家を買う場合のデメリットは以下の1つです。
・ライフスタイルが変化することがある
30代前半で家を買うと購入後にライフスタイルが変化して、せっかく買った家がライフスタイルに合わなくなることがあります。
ライフスタイルが変化する原因としては子どもが生まれたり、転勤で勤務地が変わったりすることがあります。
家を購入するときには現状のライフスタイルだけでなく、「将来どのようにライフスタイルが変化していくか」を考えながら購入するようにしましょう。
【年齢別】30代後半で家を買う場合のメリット・デメリット
30代後半では収入が安定していることも多く、住宅ローンの審査に通過しやすいタイミングといえるでしょう。
ここでは30代後半で家を買うメリット・デメリットについて解説します。
・30代前半で家を買う場合のメリット
・30代前半で家を買う場合のデメリット
30代後半で家を買う場合のメリット
30代後半で家を買うメリットは以下の1つです。
・希望に近い家を購入できる
30代後半では経験やスキルによって収入が高くなっていることが多く、より多くの住宅ローンを組んだとしても余裕を持って返済することができます。
さらに頭金として支払える金額も増えるため、希望に近い家を購入できたり、ローンの審査に通過しやすくなったりします。
30代後半で家を買う場合のデメリット
30代後半で家を買うデメリットは以下の1つです。
・老後の生活を圧迫する恐れがある
35~39歳で35年のローンを組むと70~74歳で完済することになります。
定年後にも住宅ローンの支払いが続くこともあり、収入が減った老後の生活を圧迫する恐れがあります。
そうならないように毎月の返済額とは別にまとまった金額を支払う「繰り上げ返済」を行いましょう。
繰り上げ返済を行うタイミングは人それぞれですが、ボーナスが入ったときや相続などで資産が増えたときに行う人が多いです。
【年齢別】40代で家を買う場合のメリット・デメリット
家を買うときの平均年齢が40歳前後である通り、40代で家を買う人も多いです。
ここでは40代で家を買うメリット・デメリットについて解説します。
・40代で家を買う場合のメリット
・40代で家を買う場合のデメリット
40代で家を買う場合のメリット
40代で家を買うメリットは以下の2つです。
・ライフスタイルが変わりにくい
・頭金を多く用意できる
【ライフスタイルが変わりにくい】
20代〜30代では転職、結婚、出産といったイベントが多く、ライフスタイルが変化しやすいです。
それに比べると40代では生活が安定している人が多く、家を買ったとしてもライフスタイルと合わなくなるということは少ないでしょう。
【頭金を多く用意できる】
40代になると貯金を利用して、頭金を1,000万円以上用意できるということがあります。
頭金を多く支払うと返済期間を短く設定できる上に、総返済額も減らすことができます。
40代で家を買う場合のデメリット
40代で家を買うデメリットは以下の1つです。
・返済計画をしっかり立てる必要がある
40代で家を買う場合、返済計画をしっかり立てる必要があります。
35年ローンを組んだとすると80歳前後までローンを払い続けなければいけないので、老後の生活を圧迫する可能性があります。
そのため頭金を多く支払ったり、返済期間を短く設定したりして、完済する時期を早めるという対策が必要になります。
【年齢別】50代で家を買う場合のメリット・デメリット
50代で家を買うと老後の資金に不安が残りますが、返済計画を工夫することでリスクを抑えることができます。
ここでは50代で家を買うメリット・デメリットについて解説します。
50代で家を買う場合のメリット
50代で家を買うメリットは以下の1つです。
・最小限の大きさで家を買える
50代を迎えると子供が独立していることが多いため、そこまで広い家を買う必要がないでしょう。
夫婦2人だけが住む家となるとかなりコストを抑えることができます。
さらに老後の生活を見越してあらかじめバリアフリーな作りにすることもできます。
通常の住宅ではバリアフリーのためのリフォーム費用がかかりますが、そのコストも抑えることができます。
50代で家を買う場合のデメリット
50代で家を買うデメリットは以下の1つです。
・住宅ローンが組めない可能性が高い
金融機関はローンを貸し出すときに、80歳までに完済することを条件にしていることが多いです。
そのため、50代は完済年齢がすぎるため住宅ローンが組めない可能性があります。
住宅ローンを組む際は金融機関に事前に相談してみましょう。
家を買う年齢に関するよくある質問
家を買うときは多額の資金が必要になるため慎重に選ぶことが大切です。
ここでは家を買う年齢に関する以下の質問について解説します。
・年齢が45歳で家は買うべき?
・年齢が35歳で家を買うのは遅い?
・家を建ててはいけない年齢はある?
・20代で家を買う際に頭金なしはきつい?
年齢が45歳で家は買うべき?
40代で家を買うことは十分可能で、むしろ住宅を購入する平均年齢といえます。
頭金を多くしたり、繰り上げ返済をおこなったりなど対策は必要ですが、借入金額によっては無理なくローンを完済できるでしょう。
年齢が35歳で家を買うのは遅い?
35歳で家を買うのは遅くないです。
20代の人と比べると生活も安定していて、収入も上がっていることが多いので30代で家を買う人は非常に多いです。
家を建ててはいけない年齢はある?
家を建ててはいけない年齢はありません。
しかし、年齢と借入金額によってはリスクが高くなることがあります。
住宅ローンを借り入れる金額と完済時の年齢を考慮に入れて返済計画を立てましょう。
20代で家を買う際に頭金なしはきつい?
20代で頭金なしで家を買うことはできます。
30代で頭金を貯めて、返済を楽にするという考え方もありますが、お金を貯めている間にも家賃は払い続けています。
しっかりとした返済計画を立てて、余裕を持って返済できるのなら、頭金なしで購入するのもいいでしょう。
まとめ:自分の年齢に見合った資金計画でマイホームを検討しよう
家を買う人は30代が最も多いですが、これは一般的なデータの話で、必ずしも30代で家を買うのが良いというわけではありません。
ご家庭の収入や貯蓄などのライフスタイルを考えて、家を買う適切な年齢を見極めましょう。
建匠は家族の思いを込めたオンリーワンのお家づくりを提案しています。
賃貸住宅に満足できない方は、お気軽にモデルハウスへお越し下さいませ。
マイホームを購入する上で、多くの方がお金の問題で思い悩んでいます。
建築費用に加え、土地取得費用のことを考えると、マイホーム購入に踏ん切りがつかない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、予算問題を解決する選択肢として、ローコスト住宅を紹介してまいります。
メリット・デメリットや後悔しないためのポイントも解説していますので、マイホーム購入をお考えの方は、ぜひとも最後までお付き合いください。
そもそもローコスト住宅とは?
ローコスト住宅とは、名前の通り低価格で購入できる住宅のことです。
価格帯は1,000万円前後であり、坪単価の目安は30万円前後となります。
大手ハウスメーカーや工務店などが手掛けており、選択肢が多いので、それぞれの特徴や違いを比較して自分たちに合った建築会社を選びましょう。
ローコスト住宅が安い理由
ローコスト住宅が安い理由は、スケールメリットを活かした建材や住宅設備のコストカットにあります。
規格化による施工の効率化なども挙げられますが、重要なポイントは住宅性能を犠牲にしていないかどうかです。
耐震性能や断熱性能を明示していることが、建築会社を選ぶための判断基準といってよいでしょう。
金額の安さに不安を感じる方もいるかもしれませんが、ローコストを実現する理由が分かれば安心です。
ローコスト住宅のメリット
ローコスト住宅のメリットは価格だけではありません。
金額以外のメリットも把握して、自分たちの暮らしに合うかどうか判断しましょう。
建築費用が抑えられる 工期が短い 住み替えや建て替えしやすい 住宅ローンを組みやすい 予算に合わせてオプションを追加できる
順番に解説します。
建築費用が抑えられる
ローコスト住宅の一番のメリットは、建築費用が抑えられることです。
土地取得費用に予算を圧迫される場合、建物の価格を抑えざるを得ません。
いたずらに予算を増やすことは悪手であるため、ローコスト住宅での予算調整をおすすめします。
工期が短い
工期が短い点もメリットの一つです。
一般的な注文住宅が4〜6ヶ月に対して、ローコスト住宅の工期は3ヶ月程度となります。
新生活を早く始めたい方にとっては魅力といえるでしょう。
住み替えや建て替えしやすい
住み替えや建て替えがしやすいことも魅力の一つです。ライフステージが変われば、最適な間取りも変わります。
将来の建て替えを見越して、若いうちにローコスト住宅を建てるのもおすすめの住まい方です。
住宅ローンを組みやすい
住宅ローンを組みやすい点もメリットといえるでしょう。住宅ローンの借入金額を抑えられることが理由です。
家計に無理のある返済プランでは、快適な暮らしは実現できません。
予算を意識したお家作りでは、ローコスト住宅もおすすめの選択肢です。
予算に合わせてオプションを追加できる
予算に合わせてオプションを追加できる点も忘れてはいけません。
標準仕様にオプションを組み合わせることで、より満足できる生活空間を作れます。
そのため、予め優先順位を付けておくとよいでしょう。
ローコスト住宅のデメリット
一方、ローコスト住宅にはデメリットも存在します。
他の住宅と比較する場合、悪い面も把握することで、より自分たちに合った住宅を選べます。
間取りや設備の自由度が低い 耐震性・耐久性などの住宅性能が劣る場合がある オプションを追加しすぎると割高になる メンテナンス費用がかかりやすい
順番に解説します。
間取りや設備の自由度が低い
間取りや設備の自由度が低いことはデメリットの一つです。
ローコストを実現するためには致し方ない部分ですが、建築会社によっては複数のプランから自分たちに合ったものが選べます。
選択肢の多い建築会社を見つけることで対応しましょう。
耐震性・耐久性などの住宅性能が劣る場合がある
耐震性・耐久性などの住宅性能が劣る場合があることにも注意が必要です。
ローコスト住宅とはいえ、耐震性・耐久性などの住宅性能が劣る住宅はコストカットの悪い例であり、そういった住宅を選んではいけません。
住宅性能と耐震性能を明記している建築会社を選ぶなどの対策が求められます。
オプションを追加しすぎると割高になる
オプションを追加しすぎると割高になる点もデメリットといえるでしょう。
標準仕様のグレードが低い場合、オプションの追加で結果割高となるケースがあります。
建築会社ごとの標準仕様を比較することで、コストパフォーマンスの高いローコスト住宅を選びましょう。
メンテナンス費用がかかりやすい
メンテナンス費用がかかりやすいケースにも注意が必要です。
使われる建材の耐久性が低い場合、劣化のスピードが速くなり、トータルのメンテナンス費用が割高になる可能性があります。
屋根や外壁の仕様について建築会社に確認して対応して下さい。
ローコスト住宅で後悔しないためのポイント
ローコスト住宅で後悔しないためのポイントをまとめていますので、自分たちのお家づくりをイメージしながら見ていきましょう。
余裕を持って資金計画を立てる 10年・20年間のトータルコストを考える 住宅性能や各部材・品質の違いを知っておく 複数の物件と比較して十分な時間をかける
順番に解説します。
余裕を持って資金計画を立てる
余裕をもって資金計画を立てることが、後悔しないためのポイントの一つです。
毎月の返済に無理のない範囲で予算を決めて下さい。
返済に追われる状況では、快適な暮らしとはいえません。
10年・20年間のトータルコストを考える
ローコスト住宅で後悔しないためには、10年・20年間のトータルコストを考えることも重要です。
具体的には、省エネ性能の高い家は冷暖房効率が高く、光熱費がお得になります。
積み重なれば大きな金額となるので、イニシャルコストだけを考えたお家作りではいけません。
住宅性能や各部材・品質の違いを知っておく
住宅性能や各部材・品質の違いを知っておくことも、後悔しないためのポイントです。
「ローコスト住宅=住宅性能が低い家」というわけではありません。
コストパフォーマンスの高い住宅を見つけるためにも、最低限の知識が求められます。
複数の物件と比較して十分な時間をかける
複数の物件と比較して十分な時間をかけることも重要なポイントです。
建築会社ごとに価格帯やセールスポイントは異なります。
一社だけで検討するのではなく、色々な住宅と比較して、自分たちの暮らしに合った住宅を探しましょう。
ローコスト住宅が向いている人
若くしてマイホームを持ちたいと考える方に、ローコスト住宅は向いています。
20代は年収も低く、住宅ローンで借入可能な金額が少ないことが理由です。
ローコスト住宅であれば、頭金の準備が無くとも、無理のない資金計画が立てやすいといえるでしょう。
また、住宅のデザインにこだわらない方にも、シンプルな形状のローコスト住宅は向いています。
シンプルなデザインは流行に左右されないことがおすすめの理由です。
ローコスト住宅に関するよくある質問
ローコスト住宅に関するよくある質問をまとめていますので、自分たちのお家づくりの参考にして下さい。
・ローコスト住宅はやばいって本当?
・ローコスト住宅に危険性はある?
・ローコスト住宅の寿命は何年?
順番に解説します。
ローコスト住宅はやばいって本当?
ローコスト住宅がやばいという話は、本当ではありません。
企業努力によりローコストを実現している住宅は安全・安心です。
一方で、コストパフォーマンスの高いローコスト住宅を選ぶためには、購入者側にも知識や努力が求められます。
選択肢は多いので、自分たちの暮らしに合った建築会社を選ぶようにして下さい。
ローコスト住宅に危険性はある?
ローコスト住宅に危険性はありませんが、安心して暮らすためには、信頼できる建築会社をパートナーに選びましょう。
長く実績があれば、ローコストを実現する改善の積み重ねに期待できる点が理由です。
ローコスト住宅の寿命は何年?
ローコスト住宅の寿命は他の住宅と変わらず、木造住宅であれば30年程度とされています。
メンテナンスを怠らなければ、さらに長い期間住めるので、寿命はメンテナンス次第といえるでしょう。
まとめ:高品質なローコスト住宅なら建匠
ここまで、ローコスト住宅について解説してまいりました。予算を調整するためにも、ローコスト住宅はおすすめの選択肢の一つです。
メリット・デメリットや特徴を把握した上で、他の住宅と比較して、自分たちの暮らしに合うかどうかを検討してみましょう。
建匠では、888万円から建てられるローコスト住宅「Zero+」を提案しています。
耐震性能や住宅性能に優れたコストパフォーマンスの高いお家です。
ローコスト住宅に不安をお持ちの方は、お気軽にモデルハウスへ足をお運び下さいませ。
本記事では、工務店とハウスメーカーとの違いについて解説しています。
マイホームの購入を考えた時、建築会社の選び方は頭を抱える問題の一つです。
建物の建築だけでなく、資金計画や土地探しなどを含め、建築会社は家づくりの大事なパートナーといえるでしょう。
建築会社には、工務店、ハウスメーカー、設計事務所など多くの種類があり、自分たちの建てたい家に合わせて建築会社を選ぶことが重要です。
そこで今回は、工務店に焦点を当てて、工務店を選ぶメリットやハウスメーカーとの違いを解説します。
家づくりでお悩みの方は、ぜひ最後までお付き合い下さい。
工務店とは
工務店とは地域密着の建築会社のことです。
しかしながら、時代の流れと共に工務店の様態は変化を遂げ、一口に説明することが難しくなりました。
数人規模の工務店から、地域をまたいでサービスを提供する中堅ビルダー規模の工務店まで様態は様々です。
また、フランチャイズに加盟する工務店も増えており、商品力で大手ハウスメーカーと遜色がないケースも少なくありません。
大手ハウスメーカー並みの商品力と、地域密着の丁寧な施工を組み合わせた強みがあります。
一方で、地域密着が故に、他府県でどんなに気に入った工務店が見つかっても、お住まいの地域がサービス提供エリアでなければ建築を依頼できません。
工務店とハウスメーカーの違い
工務店とハウスメーカーの違いを以下の表にまとめています。
工務店
ハウスメーカー
企業規模・施工エリア
県内のみ、近隣の県までの地域密着でサービスを提供
会社にもよるが全国エリアでサービスを提供
プランの自由度
比較的、設計の自由度が高い傾向にある
規格の標準化により設計の自由度が低い傾向にある
建築物の精度
職人による品質のばらつきがあるが、精度は会社により異なる
規格の標準化及び工業化により一定以上の品質に期待できる
工期(同規模の住宅)
ハウスメーカーに比べると工期が長い傾向にある
規格の標準化及び工業化により工期は短い
アフターメンテナンス
会社によりばらつきがあるが、スピード感のある対応に期待できる
定期点検や報告などマニュアル化された一定の標準が期待できる
企業規模、施工エリア プランの自由度 アフターメンテナンス
上記3点の内容をさらに詳しく解説していきます。
企業規模、施工エリア
企業規模、施工エリアは工務店よりハウスメーカーが多いです。
工務店の場合、サービスの提供エリアは、事業所所在地の県内や、近隣の都道府県に留まります。
その分、地域に密着した工務店はエリアに精通しているため、地元ならではの提案や建築様式に期待できます。
プランの自由度
工務店の方が、ハウスメーカーよりも自由度が高いです。
工務店では、自分たちの理想の形を一緒に考えて作り上げていくため、設計の幅が広がります。
ハウスメーカーでは、標準化された規格を変更することが難しかったり、費用が割高になったりすることがあるので事前に必要事項を確認しておきましょう。
アフターメンテナンス
アフターメンテナンスについては、会社による違いがあるため、比較が難しいポイントです。
経営基盤の面から見て、10年以上の実績があり成長している工務店であれば、アフターメンテナンスにも期待できるといえるでしょう。
工務店の種類
工務店の種類について、以下の2つの特徴から解説します。
地域密着型 フランチャイズの加盟店
地域密着型
地域密着型の工務店は、拠点のある市内や県内でサービスを提供します。
会社の規模はまちまちですが、その地域で育った従業員の方が多くエリア情報に精通しています。
地域や風土にマッチした建築様式の提案が魅力で、地域のネットワークを生かした土地情報にも期待できます。
フランチャイズの加盟店
フランチャイズの加盟店では、本部の開発した商品を地域の工務店が施工します。
技術開発や建材の仕入れを共有することで、品質の高い家をお手頃な価格で提供。
複数のフランチャイズに加盟している工務店もあり、自社ブランドだけでなく、商品のラインナップが魅力です。
工務店を選ぶメリット
建築会社選びに迷っている方向けに、工務店を選ぶメリットをお伝えします。
施工の自由度が高い コスパが良い 地域密着型のため親身に対応
それでは、順番に見ていきます。
施工の自由度が高い
工務店を選ぶメリットは施工の自由度が高い点です。
念願のマイホームは自分たちの理想を形にしたいものです。
希望を伝えて、間取りを作ってもらいましょう。相談するうちに、もっと良いプランができるかもしれません。
自由な設計を希望する方には、工務店がおすすめといえます。
コスパが良い
コスパが良い点も工務店におけるメリットの一つです。
工務店の販売価格には、大きな宣伝広告費も技術開発費用も入っていません。
もちろんゼロではありませんが、大手ハウスメーカーに比べれば微々たるものです。
コスパを考えるなら、口コミで評判の良い工務店がおすすめといえます。
地域密着型のため親身に対応
工務店における3つ目のメリットは、地域密着型のため親身に対応してくれることです。
家を建てる時はもちろん、建てた後もお付き合いは続きます。
長いお付き合いで安心したい方には、工務店をおすすめします。
工務店を選ぶデメリットはほぼない
工務店の様態が変化した現在では、工務店を選ぶデメリットはほぼありません。
気を付けるべきポイントは、自分たちが希望する家に合った工務店を選ぶことです。
そのためにも、どんな家に住みたいかを家族でよく相談しておきましょう。
デメリットを挙げるとすれば、インターネットで気に入った工務店が見つかっても、お住まいの地域から遠く離れていると、建築の依頼ができない場合があるという点です。
まとめ:工務店を検討するなら建匠
ここまで、工務店についてハウスメーカーとの違いを解説しました。
工務店の様態にはいくつも種類があり、一口に説明できるものではありません。
工務店を選ぶメリットはお伝えした通りですが、それぞれの工務店の持つ特色を比べた上で、自分たちに合うパートナーを選ぶ必要があります。
フランチャイズによる商品力なのか、それともアフターメンテナンスの手厚さなのか、優先するポイントは人それぞれです。
工務店で家を建てるなら建匠にお任せ下さい。建匠では、お客様一組ひと組のご家族にあったオンリーワンの家づくりをご提案します。
ご家族の理想の暮らし像を共有して、ワンチームでマイホームを作っていきましょう。
本記事では、建築面積の概要と注意すべきポイントを解説しています。
家づくりを始めると、新しい言葉に触れる機会が増えてきますが、これまでの生活で耳慣れない専門用語も多く、似た響きの言葉が多いことに苦労します。
建築面積というワードは、土地探しに始まり、家づくりの打ち合わせの中でも多く登場します。
似たような響きの言葉も多く、混乱する方も多いのではないでしょうか。
そんな中で、言葉の取り違えは大きなトラブルを招く原因となりかねません。
そこで今回は、建築面積に焦点を当て、言葉の意味と気を付けておきたいポイントを説明していきます。
これからお家づくりをお考えの方は、ぜひとも最後までお付き合い頂ければ幸いです。
建築面積とは?
建築面積とは、建築物の外壁と柱の中心線で囲まれた部分を指します。
しかしながら、上記の情報だけではピンとこない人の方が多いのではないでしょうか。
さらに少し詳しく解説していきます。
建築面積は建物を真上から見た場合の面積
建築面積は、建物を真上から見下ろした場合の面積を指します。
一般的な住宅では、1階部分が該当しますが、デザインによっては2階部分が張り出して、面積が広くなるケースがあります。
その場合は、2階部分を地面に投影した面積が該当します。外観のデザインや室内の形状にこだわりのある方は注意して下さい。
また、制限により自分の土地だからといって、好き勝手には建てられません。
詳細は後述しますが、土地探しにもかかわる事柄なので、気を付けておきましょう。
建築面積の計算方法
建築面積の計算方法は、以下の通りです。
建築面積=敷地面積×建ぺい率
先に述べた通り、建築面積は建ぺい率によって制限を受けることとなります。
規制の厳しいエリアでは、同じ大きさの家でも、必要な土地が多くなります。
その分、土地取得費用が予算を圧迫し、建築費用を下げる工夫が必要になるかもしれません。
気を付けておきたいのは、建物本体だけでなく独立ガレージなども建築面積に含まれるという点です。
家を建てる時に、上限ぎりぎりの設定をして、後付けでガレージの設置ができないという事態は避けなければなりません。
建築面積と延床面積・土地面積の違い
建築面積と延床面積・土地面積の違いを、以下の通りまとめています。
自分たちで情報を集めたり、打ち合わせをしたりといった際に、言葉を取り違えると大きなトラブルを招く可能性があります。
延床面積(建物面積) 土地面積(敷地面積)
順番に見ていきます。
延床面積(建物面積)
延床面積(建物面積)とは、建物各階の面積の合計を指し、全体の広さを表します。
ロフトや吹き抜けなどは含まれませんので、算入されない範囲を上手に利用して下さい。
自分たちに合った工夫を取り入れることで、開放的で伸びやかな空間を演出することが可能となります。
ただし、一定の要件を満たす必要があるので、専門家に相談することをおすすめします。
賃貸でも登場する言葉なので、家づくりが初めての方でも、比較的馴染みのある言葉といえるでしょう。
土地面積(敷地面積)
土地面積(敷地面積)とは、土地を真上から見下ろして計測した面積のことで、土地の広さを表します。
傾斜や高低差を考慮しないため、実際よりも土地が狭くなるケースに注意して下さい。
また、前面道路の広さによって、有効敷地面積が狭くなるので、土地を探す際は建築とセットで相談することが望ましいといえるでしょう。
建築面積にバルコニーやテラスは含まれる?
建築面積を見ていく際はバルコニーやテラスのように、建物から飛び出している部分の扱いが気になるところです。
1m以下の場合は建築面積に含まれない 地下や屋外階段は建築面積に含まれる?
上記2点を順番に説明します。
1m以下の場合は建築面積に含まれない
バルコニーやひさしなどで、突き出した部分が1m以下の場合は建築面積に含まれません。
ただし、バルコニーを支える柱が付いている場合はその限りではありません。壁で囲われているケースも同じ扱いとなります。
幅1m以上突き出しているケースでは、先端から1m後退したところまでが含まれます。テラスや玄関ポーチなども同様の扱いとなります。
地下や屋外階段は建築面積に含まれる?
地下室は、地盤面から1m以下に当たる部分は建築面積に含まれません。
地下室を取り入れる方はまだまだ少ないのですが、空間の有効利用などメリットもたくさんありますので、検討してみてはいかがでしょうか。
屋外階段は、バルコニーと同じように、先端から1m後退した範囲までは建築面積に含まれません。
階段を支える柱がある場合は、無条件で含まれますので注意が必要です。
完全分離型の二世帯住での設置が想定されますが、専門家に設置基準を含め相談することが望ましいといえるでしょう。
建築面積は建ぺい率で制限される
これまでに述べた通り、建築面積は建ぺい率により制限されるので、概要を把握しておかなければなりません。
用意した土地に、自分たちが希望する家が建てられない事態は避けたいものです。制限の概要は以下の通りです。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積 建ぺい率は地域によって数値が異なる
順番に説明しますので、ポイントをしっかりと押さえて下さい。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合のことを指し、建物の大きさを一定の割合に制限します。
空地を確保することで、住宅の密集を避け、防火対策としても有効です。
また、風通しや採光の面で、良好な住宅環境の維持を目的としています。
一定の要件を満たすことで、緩和措置が認められるので、上手に利用すれば、土地の有効活用に繋がります。
建ぺい率は地域によって数値が異なる
建ぺい率は、地域によって数値が異なります。
地域によって建ぺい率の制限に違いがある理由は、建物のサイズを制限する目的が地域ごとに異なっているからです。
以下の表は、住居系の用途地域をまとめたものですが、住居系以外にも工業系や商業系を合わせると全部で13種類あります。
用途地域
建ぺい率
第一種低層住居専用地域
30,40,50,60のいずれか
第二種低層住居専用地域
30,40,50,60のいずれか
第一種中高層住居専用地域
30,40,50,60のいずれか
第二種中高層住居専用地域
30,40,50,60のいずれか
田園住居地域
30,40,50,60のいずれか
第一種住居地域
50,60,80のいずれか
第二種住居地域
50,60,80のいずれか
準住居地域
50,60,80のいずれか
例えば、第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るために、建ぺい率以外にも高さ制限などが設けられており、他の住居系用途地域と比較して厳しい規制がかけられています。
このように、自分たちが住みたいエリアごとに、必要な土地の広さが変わってきます。
理想の家を実現するためにも、土地探しの段階で建ぺい率についての理解を深めておく必要があります。
建ぺい率の確認には、お住まいの自治体に確認する方法が一番確実です。
まとめ
ここまで、建築面積について紹介しました。
基本的な内容になりますが、土地探しだけでなく、建築にもかかわることなので、きちんと理解しておくべき事柄です。
似たような言葉が出てきましたが、情報を集めたり打ち合わせをしたりする際に、言葉の意味を取り違えると大きなトラブルを招くことになりかねません。
特に、用途地域による制限は、自分たちが希望する家を建築できるかどうかに直結する問題です。
満足できる家を建てるためにも、確認しすぎて困ることはありません。
自分たちだけで調べて分からない時は、専門家に相談して意見を取り入れることをおすすめします。
建匠では、資金計画や土地探しのなど家を建てるための話はもちろんですが、それ以上に家族のこれからの話を大事にしています。理想の暮らしを考えることで、良い家ができると考えているからです。
家づくりでお悩みの方は、お気軽にモデルハウスへ足をお運び下さいませ。
ワンチームでお家づくりをサポート致します。
この記事では、坪単価の定義や注意点について詳しく解説しています。
マイホーム購入を考えた時、建築会社を選ぶ基準に坪単価を用いるケースは珍しくありません。
自分たちが希望する広さと坪単価からおおよその建築費用の把握ができるため、有用な目安といえるでしょう。
しかしながら、坪単価だけを基準に建築会社を選ぶ方法はおすすめできません。
疑問に感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、坪単価の定義や注意点を知ることでその理由が分かります。
家づくりをお考えの方は最後までお付き合い下さい。
坪単価とは
坪単価とは、家を建てる時の1坪当たりの建築費用のことを指した言葉です。
「坪単価〇〇万円」という広告を目にしたことがある方は多いでしょうが、坪単価だけでは正確な建築費用を掴むことはできません。
坪単価の計算方法は以下の通りです。
坪単価の計算方法
建物本体価格÷延床面積(坪数)=坪単価
上記の計算式から坪単価が導けるのですが、目安として用いる上、気を付けておきたいポイントが2点あります。
1点目が、建物本体価格に含まれる工事の範囲を把握することです。
一般的に、建物本体工事が総費用に占める割合は7割程度で、残りが付帯工事とその他諸費用となります。
建物本体工事の中に、インテリア関連費用など付帯工事の一部が含まれていると、坪単価は高くなります。
このように、総額費用で比べなければ、本当の意味で比較することができません。
2点目が、延床面積ではなく施工面積を用いるケースです。
施工面積には、バルコニーや吹き抜けなどが含まれるため、延床面積より大きな数値となります。
結果、坪単価が安く見えることになります。
坪単価の算出基準は工務店やハウスメーカーごとに異なりますので、目安として用いる際には正確に条件を確認して、比較しなければなりません。
坪単価の費用相場
坪単価の費用相場は、坪単価の定義や建築会社により前後します。
坪単価には諸費用も含まれませんので、その範囲を確認して比較することが重要です。
坪単価の目安としては有用なので、地域別の坪単価を例に、建築会社による費用相場の違いについて解説します。
坪単価に諸費用は含まれない 地域別の坪単価
それでは、順番に見ていきましょう。
坪単価に諸費用は含まれない
坪単価は本体工事費を用いて算出するため、諸費用は含まれません。
総費用の一割程度が諸費用の目安となります。
諸費用には登記費用、印紙費用、住宅ローン手続き費用などが含まれ、住宅ローンではまかなえないため現金で用意しておく必要があります。
地域別の坪単価
地域別の坪単価は平均62万円であり、地域による大きな違いはありません。
3つの地域を比較すると、平均延床面積が小さい地域では、平均建築費用も低くなる傾向にあり、地域間の坪単価はいずれも平均値に近い数値となっています。
地域別の坪単価の詳細は、以下の表の通りです。
坪単価 ※1
建築費用 ※2
延床面積(坪数)※2
高知県
63万円(90×0.7)
2,883万円
32坪
兵庫県
62万円(89×0.7)
3,023万円
34坪
東京都
61万円(88×0.7)
2,648万円
30坪
※1 本体工事費を総費用の7割として算出
※2 土地付き注文住宅
住宅金融公庫の2020年度フラット35利用者調査を見ると、平均した坪単価は全国的に見ても大きな違いがないことが分かります。
同時に、土地の取得費用で建築に回せる予算が変わることも見て取れます。
坪単価の費用相場は建築会社ごとに特徴があります。
工務店の費用相場は、坪単価40万円~50万円となり、同規模の住宅で比較すると、大手ハウスメーカーの7割程度が目安です。
工務店の中でも、得意とする価格帯が異なりますので、自分たちに合った工務店を探しましょう。
ハウスメーカーの場合、ローコスト帯を得意とするメーカーも多く、費用相場は坪単価30万~80万円とかなり幅があります。
このように、坪単価は地域による違いはほとんどなく、施工する会社によって変わることが分かります。
大切なポイントは、自分たちの理想の家に合った建築会社を選ぶことであり、そのためにも建築会社ごとの特徴や強みを知る必要があります。
坪単価を見る際の注意点
坪単価を見る際の注意点は、以下の通りです。
家の形状 家の大きさ 本体価格 延床面積や施工床面積の違い
順番に解説していきます。
家の形状
家の形状により坪単価は変化します。
一般的に、坪単価はシンプルな形状の家で安くなり、デザイン性の高い複雑な形状で高くなります。
理由はシンプルな形状ほど、壁や屋根の面積が少なくなり、使用する建材が減り、施工の手間も少なく済むためです。
デザインよりも機能性を重視するなら、正方形に近い総2階建てがおすすめです。
家の大きさ
本体工事には、基礎工事など多くの工事が含まれますが、家のサイズによって金額に影響がある工事と無い工事に分かれます。
そのため、家の大きさだけで坪単価を比較すべきではありません。
なぜなら、標準装備や建材のグレードでも坪単価は変動するからです。
本体価格
本体価格により坪単価は決まりますが、気を付けるべきポイントは、本体価格の範囲と標準装備の内容です。
本体価格に含まれる工事と標準装備のグレードを加味しつつ、他の物件と比較しましょう。
より自分たちに合った建築会社が選べます。
延床面積や施工床面積の違い
物件ごとの坪単価を比較する上で、延床面積と施工面積の違いに注意して下さい。
先に述べた通り、延床面積と比較して、施工面積で算出した坪単価は安価になります。
2階建てや平屋の坪単価は?
2階建てと平屋の坪単価を比べると、平屋が多少高くなる傾向にあります。
一概には言えませんが、土台となる基礎工事や使用する屋根材が増えることで、建築費が上がるためです。
デザインによっては、2階建ての方が高くなるケースもありますので、それぞれのケースで判断が必要です。
まとめ
ここまで、坪単価の定義や、目安として用いる際の注意点について紹介しました。
物件を比較する目安として、一定の有用性はありますが、建築会社ごとに坪単価の算出基準が異なることを忘れてはいけません。
会社ごとの前提条件や標準装備を把握して比較することで、より自分たちに合った家が見つかる可能性が高くなります。
ホームページで物件情報を見る時は、金額だけでなく標準装備のグレードにも注目するとよいでしょう。
建匠では、価格帯ごとに豊富なプランを用意しています。坪数ごとに金額の決まったプランは分かりやすいと好評です。
家づくりをお考えの方は、お気軽にモデルハウスへ足をお運び下さい。